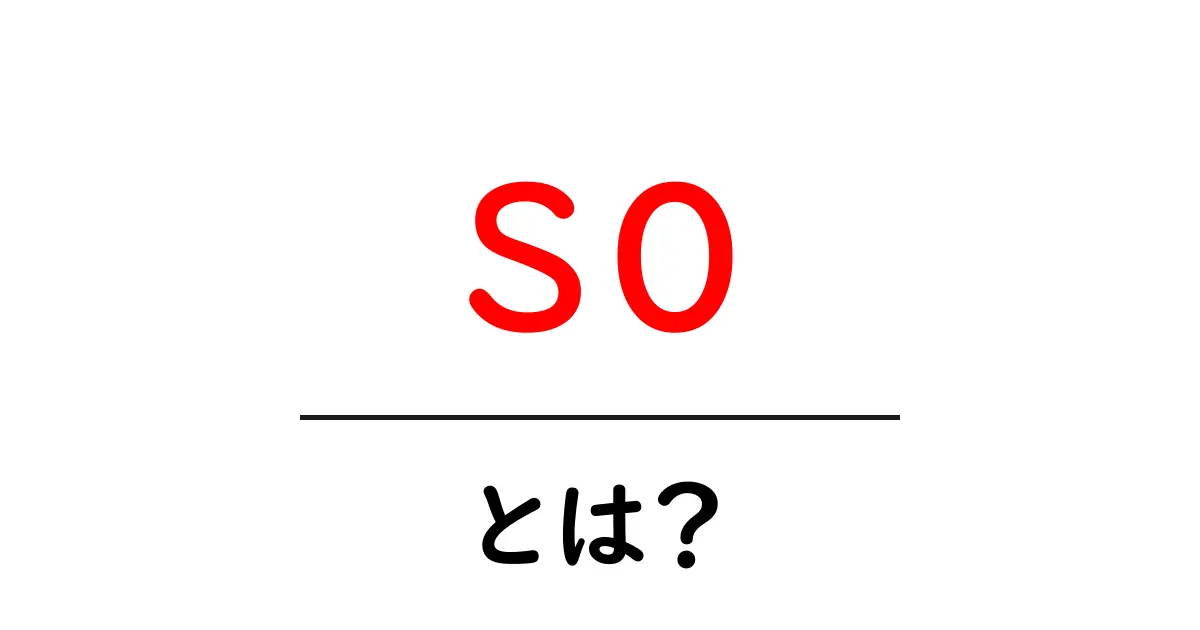

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
so・とは?
so は英語で「だから」「それで」という意味の接続詞としてよく使われます。前の情報の結果をつなぐ役割を持ち、日常会話や文章の中でとても頻繁に現れます。また副詞としても使われ、程度を強調する働きもあります。日本語の感覚でいうと「だから」「それほど」「とても…」のようなニュアンスを出すための言葉です。
so の三つの基本的な使い方
1. 接続詞としての so …前の文の結果をつなぐ。例: I was tired, so I went home. 疲れていたので、家に帰りました。
他の例: So you decided to join us? など、会話の転換にも使われます。口語的には文頭に置かれ、カンマを伴うことが多いです。
2. 副詞としての so …形容詞・副詞を強調する。「とても」「かなり」という意味合い。
例: It was so beautiful. それはとても美しかった。
3. 熟語的表現としての so … so far, so good, so-called など。これらは決まった意味を持つ表現です。
例: So far, so good. これまでのところ順調だ。
よくある注意点と発音
発音は英語で /soʊ/。日本語には長音の「ソー」という音に近く、母音の長さを意識して発音します。
表現のニュアンスは文全体の意味で決まります。例えば「so … that ...」の形では「…すぎて〜になる」という意味の強調になります。
学習とSEOのヒント
日本語話者が英語の so を検索する場合、よく使われるクエリは「so の意味」「so の使い方」「so とは」「so 例文」などです。記事内でこれらの語を自然に織り込むと検索エンジンに読みやすくなります。
まとめとして、so は英語学習の初期段階で覚えると文のつながり方が分かりやすくなります。初心者はまず意味と用法を区別して覚え、例文を声に出して読むと理解が深まります。使い方の幅を広げるには、日常会話の中で so がどのように転用されているかを観察することが一番の近道です。
他の例とニュアンスの違い
so は文脈次第で意味が変わることがあります。例えば「so」自体を話の導入として使い、次の話題へつなぐこともあります。英語では状況判断の要素を含むことが多く、同じ so でも前後の語や句読点によって「結果」「強調」「転換」など意味が異なります。練習には自分の身の回りの会話を観察し、so がどの位置で使われているかをメモするのがおすすめです。
soの関連サジェスト解説
- so とは it
- この文章では英語の so と代名詞 it の基本を中学生にもわかる言葉で解説します。so には副詞・接続詞・so… that 構文という三つの主な役割があります。まず副詞として使うときには意味を強める働きをします。例: This is so easy。日本語ではこの意味はこの課題はとても簡単だというニュアンスです。次に接続詞として使うときには理由や結果をつなぎます。例: I was tired, so I went home。眠くなってそれで家に帰ったという意味です。三つ目は so … that という形で程度の大きさを強調して、ある結果を生み出す構文です。例: She spoke so softly that I could hardly hear her。ここでは so が程度を強く表しています。次に it とは 英語の代名詞で、文の主語や目的語として「それ」や「それ自体」を指すことが多いです。天気や時間・状況を述べるときは It is raining や It is time のようにダミー主語として使われることもあります。長い名詞句を主語に置くときも文全体のリズムを整える役割を果たします。総括すれば so とは it の関係は別々の語として理解するのが基本です。so は意味を強調したり結果を示したりする語、it は文の主語代名詞として使われる語です。よくある誤解として is の後に so を置く表現は自然ですが、It is so good のほか It is such a good idea の形も覚えると英語の表現の幅が広がります。
- 蘇 とは
- 蘇 とは、日本語で“蘇る”という動詞の語源となる漢字のことを指します。日常会話では単独で使うことは少なく、多くは蘇生・蘇るといった複数語の形で現れます。意味は“生き返る・よみがえる・死からよみがえる”など広く、“再び生きる状態になる”ことを表します。代表的な用語としては蘇生(そせい)と蘇る(よみがえる)があります。蘇生は医療やファンタジー、文学など幅広い場面で使われ、患者が心肺停止から回復する場面を指すことが多いです。一方、蘇るは記憶・感情・昔の出来事が再び頭に浮かぶという意味合いで使われることが多く、比喩的な表現としても親しまれています。語源については、中国語の字形が日本語に取り入れられ、復活や生き返りのイメージと結びついたと考えられています。読み方は主に音読みの“ソ”と“セイ”を組み合わせた蘇生のような形、そして訓読みの“よみがえる”が使われます。具体的な例としては「古い友人のことを思い出し、昔の記憶が蘇る」「戦場の記憶が蘇生して胸が熱くなる」「医師が蘇生術を行って患者を救おうとする」といった文で使います。中学生にも伝わるポイントとしては、蘇るは日常会話で使われる柔らかい表現になり、蘇生は医療・科学的な場面でよく使われる専門性の高い語だと覚えるとよいという点です。さらに、関連語の理解を深めることで検索エンジンに対しても“蘇 とは”の理解を深め、関連キーワードの取りこみも自然に行えるようになります。
- 祖 とは
- この記事では「祖 とは」というキーワードを、中学生にも分かる言葉で解説します。祖とは、家族の系図の中で自分より前の世代の人を指す言葉で、特に祖先や祖父母といった関係を表すときに使われます。漢字としての「祖」は、親族の上位の代を示す意味を持ち、日常の会話で使われることは少ない一方、正式な文章や歴史の話、遺伝や系図の説明などで頻繁に現れます。よく出てくる熟語には「祖先(そせん)」「祖父(そふ)」「祖母(そぼ)」「祖国(そこく)」があります。これらはすべて『祖』という字が「前の世代・起源・故郷」を指す意味を共通して持つ例です。使い方のコツは、家庭の話題や歴史の説明で「祖」を使うときの敬語・丁寧さに注意することです。口語では『おじいさん/おばあさん』と呼ぶのが自然ですが、文章や歴史の話では『祖父』『祖母』『祖先』と書くと適切です。文章の流れとしては、祖先を辿る話題を出して、家族の伝統や地域の歴史に結びつけると読み手に伝わりやすくなります。
- そ とは
- そ とは、日本語で『外のこと』を指す語で、文法的には名詞の『そと』に助詞の『は』をつけて『そとは』と読みます。『は』は話題を示す助詞で、これから話す話題を聴き手に知らせる役割をします。つまり『そとは~だ/です/ですか』という形で、外側の情報を中心に述べるときに使います。使い方のコツは、比べる相手を明確にすることです。例えば「家の中は暖かい。外は寒い。」のように、内と外を対比する場面でよく使われます。例文:- そとは寒いです。- 外は雨が降っています。- 公園は賑わっていますが、家の中は静かです。注意点として、日常会話では『そと』を主語として使い、『そとは~だ』と断定するより『そとは~です』『そとが~です』といった柔らかい表現を使うと自然です。漢字の『外』とひらがなの『そと』を使い分ける練習をすると、意味の理解が深まります。このように、そ とは外の情報を話題にするときの基本表現です。
- 租 とは
- この記事では『租 とは』という言葉の意味を、初心者でもわかるように解説します。租は日常会話ではあまり使われない漢字で、単独で出てくることは少ないです。主に熟語の形で現れ、意味は“借りる・貸す・税金や料金の関係”といったニュアンスに分かれます。代表的な熟語には、租税、租借、租界などがあります。租税は国や自治体に支払う税金のことを指し、社会の仕組みを作るための収入源としての役割を持ちます。つまり、租の意味は“使う権利に対する対価を納める制度のこと”と考えると理解しやすいです。租借は物を借りること、期間や条件を取り決める契約の文脈で使われ、民法や契約の話題でよく登場します。租界は歴史的・地理的な概念で、外国勢力が一部の都市を統治した区域のことを指します。現代日本語の日常会話でこの語を耳にする機会は少なく、主に歴史の授業やニュース、学術論文で見られます。漢字の成り立ちは古代中国の税制を表す語彙と関係が深く、禾といった部首の意味と結びついています。覚え方としては“税や料金に関係する語に現れやすい”という特徴を覚えると、意味を思い出しやすいです。租と似た意味の語として賃や税がありますが、賃は日常の家賃の意味でよく使われ、租は公式・専門的な場面で用いられる点が違います。以上を踏まえると、租 とは税や料金・借用の制度的な意味合いを含む漢字であり、単独で使われるよりも熟語として意味を持つことが多い、という点が理解の要点です。
- 塑 とは
- 塑 とは、物を型に合わせて形を作ること、またはその性質を表す漢字です。日常会話で頻繁に使われる語ではありませんが、美術や工学、材料科学の分野でよく登場します。以下に初心者にも分かるポイントを分かりやすくまとめます。 ・意味その1:形を作ること・成形すること。粘土や石膏、金属などの材料を型に入れて希望の形に整える作業を指すことが多いです。例として、粘土を練って動物の形を塑形する、という表現を見かけます。 ・意味その2:可塑性・塑性の性質。力を加えられても元の形にすぐ戻らず、新しい形に変形してしまう性質を指します。学習用語として“塑性(そせい)”と読むことが多く、工学や材料の説明で登場します。例:金属は塑性変形を利用して加工されます。 ・意味その3:関連語との関係。日本語では“塑”を語根として使われる語があり、塑形・塑性・プラスチックに関連した話題で出てくることがあります。ただし日常語としては“プラスチック”の方が一般的です。技術的な文章では“塑性”などの用語が多く使われます。 ・使い分けのポイント。塑は“形を作る”というイメージから始まり、文脈によって成形作業・材料の性質・語源的なつながりへと意味が広がります。初学者はまず「形を作る/変形する」という核となる意味を押さえ、具体的な語とセットで覚えると理解が早くなります。 学習のコツとして、具体的な例文を作ってみるとよいです。粘土を塑形する、材料が塑性を示す、プラスチック(塑料)と関連づけて覚えるなど、身近な言葉と結びつけると記憶に残りやすいでしょう。
- ソ とは
- ソ とは、単独では特定の意味を指す固有名詞ではなく、前後の文脈によって意味が変わる言葉です。実務でよくある誤解として、「ソ とは」と検索しても答えが一つではないことがあります。この記事では初心者向けに、ソ とはに対する考え方と、よく使われる解釈の例と、意味を特定するためのコツを解説します。まず、よくある解釈のパターンを挙げます。1) SEO とは: ウェブサイトの検索順位を上げるための工夫全般を指します。2) ソース/ソースコードとは: プログラムの元になるコードのこと。3) ソーシャルとは: SNSの話題や戦略を指すことも。4) その他の略語: 部署名や商品名の頭文字を指す場合もあります。意味を特定するコツは3つです。1) 文脈を読む: その語が何について話されているかを前後の文章から推測します。2) 検索の仕方を工夫する: 「ソ とは 意味」や「ソ とは 〜 とは?」のように、クエリを絞る。3) 公式情報を探す: もし特定の分野を指す場合、公式サイトや辞典を参照します。もしあなたが「ソ とは」というキーワードで記事を書きたいなら、最初に読者が何を知りたいのかを決めるのが大切です。ここでは SEO とはを主題にする場合の例を挙げます。SEO とは、検索エンジンの仕組みを理解し、ウェブサイトを検索結果で上位表示させるための工夫の総称です。具体的には、適切なキーワード選定、質の高いコンテンツ作成、内部リンク・外部リンクの活用、メタデータの整備などが含まれます。
- 曽 とは
- 曽 とは、日本語の漢字の一つです。現代の日本語では、単独で意味を持つ言葉として使われることは少なく、主に固有名詞(姓・地名など)や古い文献に現れます。曽は、別の字「曾(そ)」の異体字のひとつとされ、読み方や用法は地域や文脈によって異なります。つまり、日常会話で「曽」を見かけても、それだけで意味を取りにくい場合が多いのです。主な使われ方としては、名前・姓に現れることが多い点が特徴です。実際、日本語の姓には曽根(そね)、曽我(そが)といった読み方のものがあり、学校の同級生や地元の人にも見かけることがあります。地名にも使われることがありますが、それは珍しくなく、漢字の形として覚えておくとよいでしょう。そして、曾と曽の関係について知っておくと便利です。曾は現代日本語でより一般的に使われる字で、意味としては“かつて・以前”といったニュアンスがあり、語としては曾祖父(そうそふ)などの熟語に現れます。一方、曽は曾の一種の異体字として、日常の語彙では使われず、主に姓名・地名・文学的・歴史的文献で見られることが多いです。読み方の整理ですが、姓として現れる場合は人名ごとに読みが異なります。例えば曽根は「そね」、曽我は「そが」と読みます。読み方は必ずしも字の形だけで決まらず、名字の慣用読みを確認するのが安全です。漢字練習としては、思い出すコツとして“名字に多い、日常語では使われにくい”と覚えることが役立ちます。要点をまとめると、曽 とは現代日本語で単独の意味を持つ語としては使われず、主に人名・地名に現れる異体字です。曾と字が似ていて混同しやすいですが、使われ方の場面が違います。名前を覚えるときは実際の読み方を確認するのが大切です。
- 楚 とは
- 楚 とは、日本語で使われる漢字の一つです。主に二つの側面で登場します。第一は古代中国の国名「楚国」やその人々を指す意味です。春秋戦国時代に存在したこの国は、現在の湖北省と湖南省の周辺を中心に勢力を持ち、長い歴史の中で独自の文化を築いていました。第二は文学・歴史の用語として使われる点です。代表的なのが『楚辞(そじ)』という中国古典詩集で、楚の地域の詩人たちの作品を集めたものとされています。日本でも歴史や文学の話題で頻繁に出てくる語です。日常会話ではあまり使われませんが、学校の授業や読書で出会う機会が多い漢字です。読み方は文脈によって異なり、固有名詞として「楚国」や「楚人」を指す場合と、文学語として用いられる場合があります。例として『楚辞(そじ)』や『楚風』といった語を挙げられます。覚えるコツとしては、古代中国の南方の国名としてのイメージと、文学用語としての古典的響きを結びつけることです。歴史の分野では楚と秦、楚漢戦争などの話題がよく出てきます。
soの同意語
- thus
- したがって。前後の文を結び、前の情報から結論を導く接続副詞。
- therefore
- それゆえ。結論を示す接続副詞。
- hence
- したがって。フォーマルな場面で結論を示す副詞。
- consequently
- 結果として。因果関係を示す接続副詞。
- thereby
- それによって。前述の手段や理由を使って結果を生むときに使う副詞。
- accordingly
- それに応じて。前提条件に沿って行動や説明を整えるときに使う副詞。
- as_a_result
- 結果として。口語・書き言葉双方で広く使われる表現。
- in_consequence
- その結果として。硬めの表現。
- thus_far
- これまでのところ。前提と現在の状況をつなぐ表現。
- very
- とても。程度を強調する副詞。
- really
- 本当に。口語的な強調。
- extremely
- 極めて。高い程度を示す。
- quite
- かなり。比較的強い程度。
- utterly
- 全く/完全に。強い強調。
- totally
- 完全に。強い肯定。
- absolutely
- 完全に/まったく。
- incredibly
- 信じられないほど。強い感嘆や強調。
- hugely
- 非常に。大きな程度を表す。
- tremendously
- 甚しく。非常に大きい程度。
- immensely
- 計り知れないほど。大きな程度。
soの対義語・反対語
- not so
- 意味: それほど〜ではない、〜ほどではない。例: I am not so tired. 使い方のヒント: 程度を控えめに伝えたいときに使う。
- not very
- 意味: あまり〜ではない。例: not very happy(あまり幸せではない)。
- barely
- 意味: かろうじて、ほとんど〜ない。例: barely enough(ぎりぎり足りる/ほとんど足りない)。
- hardly
- 意味: ほとんど〜ない。例: hardly ever(ほとんど決して〜ない)。
- little
- 意味: ごく少し、わずか。例: little chance(ごく小さな可能性)。
- slightly
- 意味: わずかに、少し。例: slightly better(少し良くなる)。
- however
- 意味: 逆接を示す接続詞。例: He is tall; however, he is not strong.(彼は背が高い。ところが彼は強くない)。
- nevertheless
- 意味: それにもかかわらず。例: It was raining; nevertheless we went out.(雨が降っていた。それでも私たちは外出した)。
- but
- 意味: 対比・逆接の接続詞。例: I like it, but I don’t have time.(好きだけれど時間がない)。
- on the other hand
- 意味: 一方では…、他方では。例: On the one hand〜; on the other hand〜。
- yet
- 意味: それでも、しかし。例: It’s early, yet I feel tired.(まだ早いが、疲れている)。
soの共起語
- so many
- 数えられる名詞が多数あることを強調する副詞句。
- so much
- 数えられない名詞の量を強調する表現。
- so little
- ごく少ないことを表す表現。
- so far
- ここまで、これまでの時点を意味する副詞。
- so long
- 長い期間を指す表現。別れの挨拶にも使われることがある。
- so long as
- 〜である限り、条件を示す接続表現。
- so that
- 結果・目的を示す接続表現。例: so that you can…
- so as to
- 目的を丁寧に示す表現。
- so-called
- いわゆる、名付けられているとされることを表す形容詞。
- so forth
- など、などと続く意味の表現。
- so on
- など、〜などを指す表現。
- so good
- とても良いことを表す強調表現。
- so well
- とても上手に、順調にという意味で使われる副詞。
- so bad
- とても悪い・ひどい状態を表す表現。
- so easy
- とても簡単だという意味。
- so difficult
- とても難しいという意味。
- so beautiful
- とても美しいという意味。
- so delicious
- とても美味しいという意味。
- so interesting
- とても興味深いという意味。
- so funny
- とても面白いという意味。
- so happy
- とても幸せだという意味。
- so sad
- とても悲しいという意味。
- so kind
- とても親切だという意味。
- so polite
- とても丁寧だという意味。
- so far so good
- ここまで順調だ、という意味の定型表現。
- so what
- それがどうした、という意味の口語表現。
- so that you can
- 〜できるように、目的を示す接続の一部。
- so to speak
- いわば、言い換えればという意味の表現。
- so be it
- それで良い、そうなるがままという意味の表現。
soの関連用語
- SEO
- 検索エンジン最適化(SEO)とは、検索結果で自サイトの表示順位を高め、自然検索からの訪問者を増やす施策の総称です。
- SERP
- 検索エンジン結果ページ(SERP)とは、検索キーワードに対して表示される結果の一覧ページのことです。
- オンページSEO
- ページ内部の最適化。タイトル・見出し・本文・内部リンク・画像のaltなどを整えて、検索エンジンとユーザーの理解を高めます。
- オフページSEO
- サイト外部での評価を高める施策。主に被リンク獲得やブランドの認知度向上、ソーシャル信号が含まれます。
- テクニカルSEO
- サイトの技術的な最適化。クロール・インデックス、サイト速度、モバイル対応などを整えます。
- キーワードリサーチ
- 検索需要のある語句を調べ、狙うべきキーワードを選定する作業です。
- 検索意図
- ユーザーがその語で何を知りたいのか、目的を理解すること。高品質なコンテンツ作成の指針になります。
- ロングテールキーワード
- 競合が比較的低く、具体的な検索意図を持つ長いキーワードのことです。
- メタタイトル
- 検索結果に表示されるページのタイトル。主要キーワードを含め、クリックされやすく作成します。
- メタディスクリプション
- 検索結果に表示される説明文。クリック率を高めるため、要点と魅力を簡潔に伝えます。
- 代替テキスト(Alt)
- 画像の内容を説明するテキスト。画像が表示されない場合にも内容を伝え、アクセシビリティ向上にも役立ちます。
- カノニカルURL
- 重複ページがある場合、正規のURLを検索エンジンに伝えるための措置です。
- サイトマップ
- サイト内の全ページを一覧化したファイル。クローラーの発見を助けます。
- robots.txt
- 検索エンジンのクローラーに対して、どのページを巡回してよいかを指示するファイルです。
- 構造化データ(Schema.org)
- ページの内容を機械的に理解させるためのマークアップ。リッチリザルトの表示にも寄与します。
- リッチリザルト
- 検索結果に星評価、価格、イベント情報などの情報を表示する拡張表示のことです。
- 特徴的な抜粋
- 検索結果の上部に表示され、質問に直接回答する抜粋のことです。
- コアウェブバイタル
- ユーザー体験を評価する3つの指標(LCP・CLS・FID)を指します。
- LCP(Largest Contentful Paint)
- ページの主要コンテンツが描画されるまでの時間を測る指標です。
- CLS(Cumulative Layout Shift)
- ページ読み込み中の視覚的ずれの合計を測る指標です。
- FID(First Input Delay)
- ユーザーの最初の操作に対する反応遅延を測る指標です。
- ページスピード
- ページの表示速度。高速化はUXと直結します。
- モバイルファーストインデックス
- モバイル版サイトを優先して評価・インデックスするGoogleの方針です。
- クローラビリティ
- クローラーがページを発見・巡回しやすい状態を指します。
- インデックス化
- 検索エンジンがページをデータベースに登録することです。
- 被リンク(バックリンク)
- 他サイトから自サイトへ張られたリンク。SEOの重要な評価要因です。
- 内部リンク
- 自サイト内の別ページへつなぐリンク。サイト内の巡回性と情報伝達を高めます。
- サイト構造/URL構造
- サイトの階層設計とURLの付け方。検索エンジンとユーザーの理解を助けます。
- 301リダイレクト
- 恒久的なURLの移動を示すHTTPステータス。移転後のSEO影響を適切に処理します。
- 404エラーページ
- 見つからないページが表示されるエラー画面。適切な対処が必要です。
- noindex
- ページを検索結果に表示させない指示です。
- nofollow
- リンクの評価を渡さない指示です。
- ロボットメタタグ
- ページ単位でクローラーの挙動を指示するHTMLタグです。
- ローカルSEO
- 地域情報での露出を高める施策。Googleマップ対策などを含みます。
- 国際SEO
- 言語・地域を跨いだサイトの最適化。hreflangの活用などを含みます。
- 音声検索最適化
- 音声検索の特性に合わせて、質問形式のコンテンツやFAQを整える施策です。
- セマンティックSEO
- 意味・文脈を重視して、検索エンジンに意図を正しく伝える最適化です。
- コンテンツ新鮮さ
- 情報の更新頻度と新鮮さを保つことです。
- 重複コンテンツ
- 同一または類似内容が複数ページにある状態。検索エンジンはペナルティを避けるため対処します。
- SEO監査
- サイト全体のSEOを点検し、改善点を洗い出す作業です。
- パンダ/ペンギン/ハミングバード
- Googleのアルゴリズム更新。パンダは品質、ペンギンはリンク、ハミングバードは意味理解を強化します。
- ソーシャルシグナル
- ソーシャルメディアでの言及・共有などの指標。直接のランキング要因ではないことが多いですが影響があります。
- ソーシャルシェア
- ソーシャルメディアでの共有。間接的にトラフィックや認知度を高めます。
- Share of Voice(SOV)
- 自社の話題量が市場内でどの程度あるかを表す指標。ブランド力の目安にもなります。
- ソフト404
- 実質的には404ではないが、検索エンジンに価値がないと判断されるページの状態です。
- コンテンツギャップ分析
- 競合と自サイトの差を分析して埋めるべきテーマを見つけ出す作業です。
- AMP
- Accelerated Mobile Pagesの略。モバイルで高速表示を目指す軽量ページ形式です。
- CTR(クリック率)
- 検索結果や広告でのクリック回数を表示回数で割った割合です。
- CRO(コンバージョン率最適化)
- 訪問者を商品購入や会員登録など目的の行動へ誘導する最適化です。
- UX(ユーザー体験)
- サイトを利用する人の体験全体を指します。SEOと深く関係します。
- SEO指標
- トラフィック、順位、クリック率、被リンク数など、SEOの評価指標全般です。



















