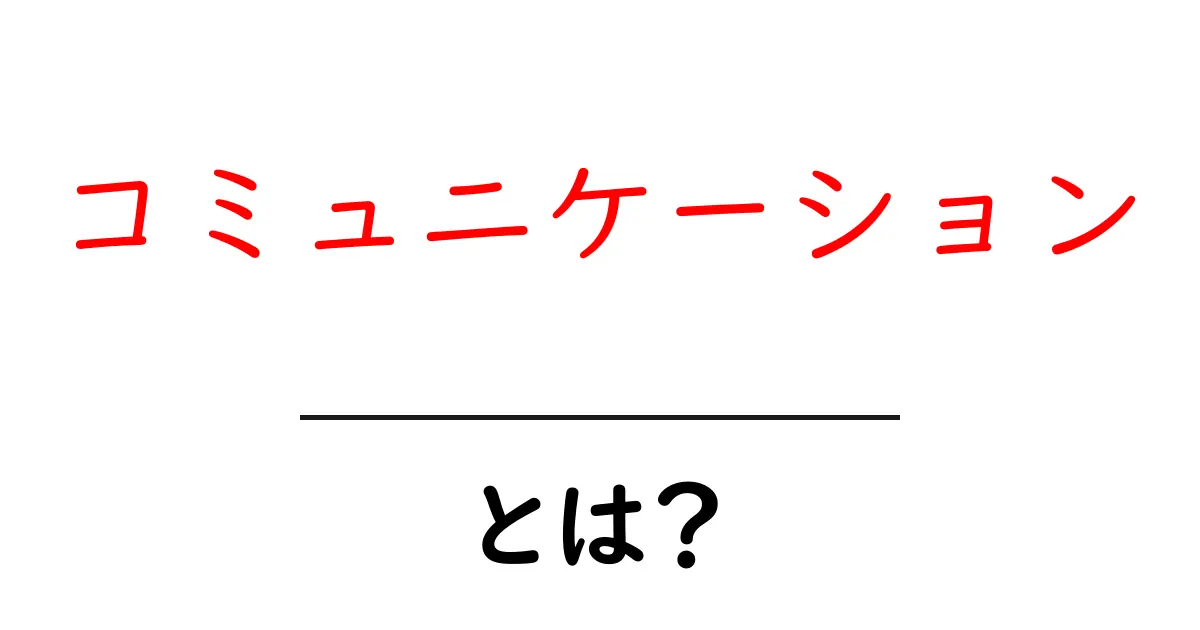

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
コミュニケーションとは何か
コミュニケーションとは、情報を伝え合い、相手と理解を共有するための行動です。話すだけでなく、聞く、書く、体の動きや表情、声のトーンも含めて相手に意味を伝える作業です。目的は意味を伝えることと信頼を築くことであり、日常の会話から仕事の場面まで幅広く使われます。
コミュニケーションの基本要素
基本は三つの柱です。まず一つ目は送る側の情報、つまり言葉や絵、文字で伝える内容です。次に二つ目は受け取る側の解釈、相手が意味として受け取ることです。三つ目は伝える仕方、話し方や表情、相手の話を聞く姿勢です。実際には言葉だけでなく声の大きさやリズム、沈黙の使い方も大切で、伝わる伝え方を意識することが成否を分けます。
良いコミュニケーションには次のコツがあります。まずは相手の話を最後まで聴くこと。途中で遮らず、要点を質問で確認します。次に自分の考えを簡潔に伝えること。長くなりすぎず、要点を絞る練習をすると伝わりやすくなります。さらに非言語の情報にも気を配ること。表情や姿勢、相手の視線の向きなどは言葉以上に伝わる場合があります。
よくある障害と対策
会話の障害にはノイズや誤解、先入観、文化差などがあります。例えば話す内容が長すぎて相手が要点を見失うと伝わりづらくなります。対策としては短い文に分けて伝えること、要点を最初に示すこと、要約して相手に返してもらうことが効果的です。
日常での実践ヒント
日常生活で試せる基本は、挨拶を丁寧にすること、相手の話を遮らずに聞くこと、話の要点を相手に要約して返すことです。わからない点は質問して確認しましょう。メッセージのやり取りでも、絵文字や感情を伝える表現を使うと誤解を減らせます。
まとめ
コミュニケーションは人と人をつなぐ基本的な行動です。言葉だけでなく声のトーン、表情、視線、沈黙などの非言語情報も大切にしましょう。相手の話を聴き、自分の考えを簡潔に伝え、障害を意識して対策をとることで、学びや仕事、友人関係においてよりよい関係を築くことができます。
コミュニケーションの関連サジェスト解説
- コミュニケーション とは何か
- コミュニケーションとは、人と人が意味を伝え合う行動のことです。言葉だけで伝わる場合もあれば、表情・声のトーン・身振り・距離感などの非言語情報を通じて伝わる場合もあります。伝えたい内容が何かをはっきりさせ、受け取る側が理解できる形に整えることが大切です。伝え方には、送り手と受け手の二者だけでなく、場の雰囲気や使う道具、文化的な背景も影響します。基本の流れは、送り手がメッセージを作り、適切なチャンネルで伝え、受け手が受け取り、反応するフィードバックを返す、という循環です。途中にノイズと呼ばれる雑音や誤解が入ると、伝わり方が変わってしまいます。タイプとしては、口頭で話す、書く、聴く、読むなどの方法があります。日常の会話、授業での説明、友達とのLINEやメール、SNSの投稿、プレゼンテーションなど、さまざまな場面で使われます。わかりやすい伝え方のコツは、相手の立場を想像して伝えること、難しい言葉を避けて短い文で伝えること、事実と自分の意見を分けること、伝えたことを相手に確認することです。相手の話をよく聴く姿勢も大切で、途中で話を遮らずに相づちや合いの手で理解を促します。非言語のサインにも気をつけましょう。表情や声の高さ、間の取り方は伝わり方を大きく左右します。相手の表情が困惑していると感じたら、説明をくり返すか質問して理解を深めましょう。練習のヒントとしては、日常の会話で短い話題を丁寧に伝える練習を繰り返すこと、相手に質問をして確認すること、相手の反応を見て自分の伝え方を改善することです。このような基本を押さえると、家族や友だち、学校の仲間とのコミュニケーションがスムーズになり、間違いやすい誤解を減らすことができます。
- コミュニケーション とは看護
- 看護の現場では、患者さんや家族、そして同じチームのスタッフと、正しく伝え合う力がとても大切です。ここでいう「コミュニケーション とは看護」は、相手の気持ちを理解し、自分の伝えたいことを分かりやすく伝える行為のことを指します。患者さんが痛みや不安を訴えるとき、適切な言葉選びと優しい声かけが治療への信頼を作ります。以下のポイントを意識すると、初心者でも看護の現場で役立つコミュニケーションが身につきます。- 傾聴を意識する: 相手の話を途中で遮らず、相手の言葉に耳を傾けます。うなずきや短い相づち、要約して返すと話しやすくなります。- 話す力を鍛える: 専門用語を避け、日常的な言葉で説明します。病名は伝えつつ、治療の目的や次の予定を分かりやすく伝えます。- 非言語コミュニケーション: 表情や声のトーン、視線、身振りに気を配ります。緊張している患者には穏やかな声のトーンと正面からの姿勢が安心感を作ります。- チームとの連携: 情報共有はカルテ記録や伝達、途中経過の報告を丁寧に行い、他のスタッフと協力します。- よくある場面の練習例: 痛みの訴えを5段階で聴き取り、家族へ状況を簡潔に伝える練習を繰り返します。- 実践のコツ: 毎日1回、短い声かけの練習を取り入れ、患者さんの安心につながる言葉を見つける習慣を作ります。
- コミュニケーション とは 広辞苑
- 広辞苑ではコミュニケーションを意思の伝達を目的とした相互作用の過程と説明します。つまり人と人が情報や感情を伝え合い、理解し合う活動のことを指します。日常生活では会話だけでなく、メールやチャット、授業中の発表、友達とのLINE、表情や身ぶりといった非言語的な伝え方も含まれます。コミュニケーションは一方が話すだけでは成り立たず、相手の話を聞く受け手の役割がとても大切です。話す内容だけでなく伝え方、場の雰囲気、相手の背景や気持ちを配慮する姿勢も重要です。ポイントは伝えること・伝わること・誤解を減らすことです。伝えるには明確な言葉選び、具体的な例、適切な話す速さが必要です。伝わるには相手の反応を見て言い換える、質問をして確認する、相手の立場を想像することが役立ちます。非言語コミュニケーションは言葉よりも多くを伝えることがあり、表情・目線・姿勢・声のトーンなどが大きな役割を果たします。広辞苑が示すもう一つのポイントは相手との信頼関係です。相手を尊重し、間違いを認める姿勢や、適切な場を選ぶことも良いコミュニケーションには欠かせません。誤解が起きたときは落ち着いて再確認することが大切です。身近な練習法としては家族や友人と話すときに相手の話を最後まで聞く、要点を簡潔にまとめる練習、相手の反応を観察して伝え方を変えてみる、分からない言葉は尋ねる、などがあります。学校の授業や部活、グループ作業で意識すると、伝えたいことが伝わりやすくなり、トラブルも少なくなります。
- コミュニケーション とは 辞書
- コミュニケーションとは、相手に自分の考えや気持ちを伝え、同時に相手の伝えたことを理解し、必要なら反応を返す一連の行為です。言葉だけでなく、表情や身ぶり、声の大きさ、距離感といった非言語的な要素も含まれます。つまり、情報を伝える人と受け取る人の、双方が関わる「つながり」のプロセスです。辞書とは、言葉の意味や読み方、品詞、使い方、例文、語源などを載せた本やオンラインの資料のことを指します。「コミュニケーション」という言葉を辞書で調べると、まず意味が「人と情報を伝え合い、理解し合う行為」と説明されますが、場面によって使い方が少し異なる場合があります。辞書には通常、用法の欄や例文が付いており、似た表現との違いをつかむ手助けになります。たとえば「コミュニケーションを取る」「コミュニケーション能力」「コミュニケーションを図る」といった表現は、ニュアンスが微妙に違います。実際の使い方を身につけるには、辞書の例文を音読してみたり、友だちや家族との会話で使ってみたりすると効果的です。日常生活では、口頭での会話だけでなく、メモやメール、LINEなどの文字のやり取りも立派なコミュニケーションです。相手の話を最後までよく聞く、相手の意図を読み取ろうとする、そして自分の伝えたいことを分かりやすく整理して伝える、これらのコツを意識することが、辞書の学習と同じくらい大切です。辞書を活用するコツは、意味だけでなく使い方のヒントを探すこと、同義語や反対語にも目を向けること、そして例文を日常の場面に置き換えて練習することです。
- アサーティブ コミュニケーション とは
- アサーティブ コミュニケーション とは、相手を傷つけずに自分の気持ちや意見を伝える話し方のことです。例えば友だちが約束を守れない場合に、黙って我慢するのではなく「約束の時間を守ってほしい。今日は予定があるから待つのが難しい」と伝えるのがアサーティブです。この伝え方は、受け身(何も言わずに従う)や攻撃的(相手を責める怒り方)と対照的です。アサーティブな表現は相手を尊重しつつ自分の立場を明確にします。こうすると関係が壊れにくくなり、誤解も減ります。さらに自分の感情を言葉にする練習を重ねると、ストレスが減り自己肯定感が高まることが多いです。実践のコツは4つのステップです。1つ目は状況を短く説明すること。2つ目は自分の感情を“Iメッセージ”で伝えることです。例として「私はこの状況でこう感じます」と言い換えると伝わりやすくなります。3つ目は具体的なお願いや提案をすること。4つ目は相手の言い分を聞き、合意点を探すことです。練習としては日常の小さな場面から始め、短いIメッセージを使えるように練習します。声のトーンや表情にも気をつけ、相手を批判せずに共感を示すことが大切です。例えば親に「私は睡眠と勉強の時間を守りたいので、夜はスマホを控えたい。協力してくれると助かります」という伝え方や、友だちに「遅刻したら連絡してね」と伝える例など、実践的な練習を重ねると自然と身についていきます。初めは小さな一言から始め、徐々に状況を広げていくと良いでしょう。
- マーケティング コミュニケーション とは
- マーケティング コミュニケーション とは、商品やサービスを世の中に伝え、消費者と信頼できる関係をつくるための“伝える活動”の総称です。広告だけでなく、PR・販売促進・ダイレクトマーケティング・パーソナルセリング・イベント・店舗の接客・公式サイトやSNSなど、さまざまな方法を組み合わせて使います。目的は、商品を知ってもらい、理解してもらい、興味を持ってもらい、最終的に購買や利用、そしてリピート・ファンづくりにつなげることです。マーケティング コミュニケーションは、チームで統一されたメッセージを作ることが大切です。チャネルごとに伝え方を変えつつ、伝える内容は同じ意味を持つようにします。例えば新製品を紹介する場合、テレビCMでは視覚的な魅力を伝え、SNSでは使い方のヒントや感想を共有し、公式サイトでは詳しいスペックと購入方法を案内します。イベントや店舗では実際に体験してもらい、口コミが広がるようにします。初心者が押さえるべきポイントは三つです。第一に「伝えたいメッセージを一つに絞る」こと。二つ目は「対象の人が何を知りたいか、どんな言葉で伝えると伝わるかを考える」こと。三つ目は「結果を測ること」です。アクセス数、広告のクリック、SNSのいいねやシェア、問い合わせの数など、どのチャネルが効果的かを少しずつ確認します。この考え方は、企業の規模や業界を問わず使えます。日常の学生や保護者向けイベント、地域のお店のプロモーションなど、身近な場面でも練習できます。マーケティング コミュニケーションを理解することで、ただ「売る」ことだけでなく、「伝える力」を身につけ、信頼される情報の発信者になれます。
- 対話 的 コミュニケーション とは
- 対話 的 コミュニケーション とは、話す人と聞く人が互いに意見を交換し、理解を深めるコミュニケーションのことです。一方的に話を伝えるだけでなく、相手の話をよく聴き、疑問を投げかけ、自分の考えを丁寧に伝え合います。これにより、すれ違いを減らし、みんなが納得できる結論に近づきます。対比として、一方的な伝達は情報をただ渡すだけで、相手の反応を見ずに終わることが多いです。対話 的 コミュニケーション とは、相手の反応を観察し、必要なときに補足や修正を行う点が大きな特徴です。実践のコツとしては、まず相手の話を最後まで聴くこと。途中で遮らず、要点を自分の言葉で確認し直すと誤解が減ります。次に開かれた質問を使い、相手の考えや感情を引き出します。例えば「この部分はどう感じましたか?」や「他に考えられる方法はありますか?」と尋ねると会話が深まります。自分の意見を伝えるときは、相手を否定せず「私は〜と感じます」という形のIメッセージを使うと受け入れやすくなります。非言語の要素も重要です。相槌を打つ、視線を合わせる、表情を穏やかにするなど、言葉以外のサインで相手に関心を示します。場の雰囲気づくりも大切で、相手を尊重する姿勢が信頼感を生みます。練習の場としては、日常の会話やグループ討議で意識的に使うことがおすすめです。授業の発言練習、家族の会話、友達とのディスカッションなど、短時間でも毎日続けると効果が出ます。
- ダイバーシティ コミュニケーション とは
- ダイバーシティ コミュニケーション とは、異なる背景を持つ人たちが互いを理解し合い、対話を通じて協力して成果を出すための話し方や考え方のことです。たとえば年齢、性別、国籍、文化、障がいの有無、考え方の癖など、さまざまな違いを前提にします。違いを隠すのではなく活かすことで、アイデアが広がり、誤解や対立を減らせます。学校や部活、会社のチームでのミーティングを想像してください。違う意見が出たとき、反対意見は邪魔だと決めつけるのではなく「なぜそう思うのか」を丁寧に聞き、短くわかりやすい言葉で自分の意見を伝える練習をします。重要なのは配慮と公正さです。専門用語を使いすぎない、難しい言い回しを避ける、誰もが発言しやすい雰囲気を作る、発言の順番を平等にする、などの基本ルールを決めることです。また相手の言葉を確認するリフレーズ技術や、沈黙を恐れず待つ姿勢、文化的背景に配慮した場面の対応も学びます。具体的な場面の例としては、海外の友人と話すときの言葉選び、職場の多様なチームでの会議運営、授業でのディスカッションなどが挙げられます。国や文化が違っても共通の目的はみんなが参加できる場を作ることです。誰の意見も大切にする姿勢を意識し、相手の話を最後まで聴く練習を欠かさないことが大事です。実践のコツとしては、相手の言葉をリフレーズで要点確認する、理解できないときは素直に質問する、分かりやすい言い方に直すリライト、そして合意点を少しずつ積み上げていくことがあります。このような取り組みを続けると、チームの信頼が深まり、生産性や創造性も高まります。
- 介護 コミュニケーション とは
- 介護 コミュニケーション とは、介護を必要とする人と介護をする人が、情報や気持ちをやりとりして、相手の安心感や尊厳を保つことです。高齢者や認知症の方と接する場面では、言葉だけでなく表情や声のトーン、身のこなしなどの非言語も大切になります。話す内容だけでなく、どう伝えるか、どんな雰囲気で話すかが、相手の心を左右します。具体的には、相手の話をよく聴くこと、ゆっくり話すこと、専門用語を避けること、敬意を持って接することが基本です。うなずきや目を合わせるなどのリアクションで信頼を作り、静かで落ち着いた環境を整えることも効果的です。伝えたいことを短く区切って話し、要点を繰り返して確認します。筆談やメモを活用してコミュニケーションの負担を減らす工夫も有効です。また、家族の協力を得ることも大切です。利用者の過去の記憶や好みを知っておくと、会話がしやすく、安心感が高まります。認知症の人や難しい感情が出る人には、急がず落ち着いて対処する姿勢が求められます。むりなく続けられる目標を設定し、記録をつけて改善点を見つけましょう。介護の現場での良いコミュニケーションは、安全と自立を支える土台です。誤解を避けるために、話した内容を相手と確認する癖をつけましょう。
コミュニケーションの同意語
- 意思疎通
- 相手と自分の意志や情報を互いに伝えあい、理解を共有する過程。言語だけでなく表情や身振りなどの非言語情報も含む広い概念。
- 対話
- 二者以上が互いに発話を交わし、意見・情報を交換するコミュニケーションの形態。双方向のやり取りを重視。
- 会話
- 日常的で自然な話し合いのやり取り。場面を問わず使われる基本的な情報交換の形態。
- 交流
- 人と人・組織間の接触・関係づくりと情報のやり取りを含む、広い意味でのコミュニケーション。
- 連絡
- 情報を知らせ合い、つながりを保つ行為。緊急度の高い連絡や日常の連絡など、実務的な伝達を含むことが多い。
- 伝達
- 情報・意図を相手に伝えること。言語・非言語を問わず、伝える行為そのものを指す。
- 情報共有
- 情報を相手と共有して共通の理解をつくる行為。協働や意思決定の土台となる。
- やりとり
- 発信と受信の双方が関与する情報の交換。テンポよく繰り返される実務的なやり取りを指すことが多い。
- 話し合い
- 問題解決や方針決定のため、複数人が意見を出し合う討議の過程。合意形成を目指す場面で用いられる。
- 意思伝達
- 自分の意思・意図を相手に伝えること。意思決定や指示の場面で特に重要。
- 言語コミュニケーション
- 言語を用いて情報や意思を伝える形態。会話・説明・プレゼンなど言葉のやり取りを含む。
- 非言語コミュニケーション
- 言葉以外の手掛かり(表情・身振り・姿勢・声のトーンなど)を通じて伝える情報伝達の形態。
コミュニケーションの対義語・反対語
- 沈黙
- 言葉を発さず、情報の交換が起きない状態。相手と意味を共有する機会がなく、コミュニケーションの基本が欠如している。
- 無言
- 話すことを意図的に避けている状態。会話が成立していない、口をつぐんでいる状況。
- 黙秘
- 話すことを拒む、口を閉ざしている状態。開かれた対話を避ける姿勢。
- 一方通行
- 情報が片方向だけ伝わり、受け手の反応や対話が発生しない状態。
- 独り言
- 自分自身に話しかける状態で、他者との意思疎通が生まれない。
- 不対話
- 対話が成立していない、相手と意味の共有がない状態。
- 遮断
- 情報の伝達が遮断され、コミュニケーションが途切れる状態。
- 孤立
- 周囲とのつながりが断たれ、情報交換の機会が減少している状態。
- 断絶
- 交流やつながりが途切れ、相互理解が生まれない状態。
- 伝達不能
- 伝えたい情報が相手に届かない、意思疎通が成立しない状態。
- 非対話的
- 対話を前提としない、言葉のやり取りが不足している状況。
コミュニケーションの共起語
- 対話
- 相手と発言を交わし情報や意図を共有する、双方向の意思疎通信の基本形。
- 会話
- 日常的な口頭でのやり取り。気軽に情報を伝え合う基本的なやり取り。
- 傾聴
- 相手の話を途中で遮らず、意図や感情を理解しようと耳を傾ける姿勢。
- 聴く
- 相手の言葉を正しく受け止め、理解する行為全般。
- 非言語コミュニケーション
- 言葉以外の手段(表情・声の抑揚・身振りなど)で伝える情報。
- 非言語
- 言葉以外の伝達手段全般。表情や姿勢などが含まれる。
- 表情
- 顔の表情で感情や反応を伝えるサイン。
- ジェスチャー
- 手や体の動きで意味を伝える身振り。
- ボディランゲージ
- 体全体の動きや姿勢で情報を伝える表現。
- 言語コミュニケーション
- 言語を使って情報を伝える基本的な手段。
- コミュニケーション能力
- 効果的に伝え、理解を得るための分かりやすく整った能力。
- 意思疎通
- 自分の意思を相手と共有して理解を得ること。
- 伝達
- 情報を相手に届け、意味を共有する行為。
- 伝達手段
- 情報を送る方法。メール・電話・チャット・対面など。
- フィードバック
- 伝えた内容に対して返ってくる反応・意見・評価。
- 共感
- 相手の立場や感情を理解し、寄り添う姿勢。
- 信頼
- 安心して情報を共有できる関係の基盤となる信用。
- 説得
- 相手の考えや行動を論理的・感情的に動かす伝え方。
- 交渉
- 互いの利害を調整して合意を取り付ける対話過程。
- 伝える力
- 相手に意図を明確かつ説得力ある形で伝える能力。
- メッセージ
- 伝えたい内容の中核となる情報そのもの。
- 受け手
- メッセージを受け取る側の人。
- 発信者
- メッセージを発信する側の人。
- コンテキスト
- 背景や状況、前提となる情報のこと。
- 異文化コミュニケーション
- 文化の違いが影響するコミュニケーション。
- 文化差
- 文化的背景の違いが意味の解釈や反応に影響を与える点。
- 透明性
- 情報を隠さず開示し、誤解を減らす姿勢。
- アサーティブネス
- 自分の権利を尊重しつつ他者の権利も尊重する表現のスタイル。
- 問題解決
- 会話を通じて課題を特定し、解決策を見つけること。
- マナー
- 話し方や場の作法、礼儀正しい振る舞い。
- 文章力
- 書く力。メールや報告書などを分かりやすく伝える能力。
- ライティング
- 文章を書く技術。明確さ・簡潔さを意識する。
- デジタルコミュニケーション
- オンライン上の情報伝達・交流全般。
- オンライン
- ネット上での対話・伝達。
- オフライン
- 対面や非デジタル環境での対話・伝達。
- メール
- 正式・半正式な文章での伝達手段。
- チャット
- リアルタイムのテキスト対話ツール。
- SNS
- ソーシャルネットワークサービスを通じた交流。
- ミーティング
- 会議形式の集まりでの話し合い。
- 会議
- 正式な討議の場。目的を共有し結論を目指す。
- プレゼンテーション
- 情報を分かりやすく伝えるための発表・説明。
- ファシリテーション
- 議論を円滑に進行させ、合意形成を支援する技術。
- 場づくり
- 会話がしやすい雰囲気や環境を整える工夫。
- 報告・連絡・相談
- ビジネスで基本となる情報共有の3つの柱(ほうれんそう)。
コミュニケーションの関連用語
- コミュニケーション
- 人と人が情報や感情を伝え合い、意味を共有する過程。言語と非言語の両方の要素を含む。
- 発信
- 自分の考えや情報を相手に伝える行為。
- 受信
- 相手の言葉や情報を受け取り、解釈する行為。
- 傾聴
- 相手の話を遮らず、理解を深めるために注意深く聴く姿勢と技術。
- アクティブリスニング
- 相手の話を要約・確認しながら聴く、理解を深める聴取技法。
- 非言語コミュニケーション
- 言葉以外の手段で意味を伝える。表情・視線・姿勢・ジェスチャー・声のトーンなど。
- 表情
- 感情や意図を顔の表情で伝える非言語サイン。
- ジェスチャー
- 手や体の動きで意味を伝える非言語表現。
- ボディランゲージ
- 身体全体を使った非言語コミュニケーションの総称。
- トーン
- 声の高低・抑揚・リズムなど、意味を左右する話し方の要素。
- イントネーション
- 声の抑揚のパターン。意味を変える要因のひとつ。
- 言語的コミュニケーション
- 言葉を使って伝える伝達。語彙・文法・表現の質が影響。
- 要約
- 相手の話の要点を短く整理して伝える技法。
- クラリフィケーション
- 相手の意図を確認し、誤解を防ぐための明確化・確認作業。
- 質問技法
- 理解を深めるための問いかけの技術全般。
- オープンエンド質問
- 相手に自由回答を促す質問形式。
- クローズドクエスチョン
- はい・いいえで答える限定的な質問形式。
- フィードバック
- 相手の伝え方や内容に対し、改善点や感想を伝える返答。
- 建設的フィードバック
- 具体的で前向きな改善点を示すフィードバック。
- アサーティブコミュニケーション
- 自己主張と他者の権利を尊重する伝え方。
- 共感
- 相手の感情を理解し、寄り添う姿勢。
- 受容
- 相手の感情・意見を受け止める姿勢。
- 共感的コミュニケーション
- 相手の立場や感情を理解して伝える、思いやりのある話し方のスタイル。
- コンフリクト解決
- 対立を解消し、合意形成へ導く話し合いの技術。
- 説得
- 論拠を提示し、相手を納得させる伝え方。
- 説得力
- 伝え方や根拠の強さ・信頼性。
- コンテキスト
- 伝える場面の背景・状況。意味を左右する要素。
- 文脈
- 発言が置かれている前後関係・状況。
- 異文化コミュニケーション
- 異なる文化的背景を持つ相手と行うコミュニケーション。
- 文化的背景への配慮
- 文化の違いを認識し、配慮した伝え方を心掛けること。
- デジタルコミュニケーション
- オンラインやデジタルツールを用いた情報伝達。
- オンラインコミュニケーション
- ネット上でのやり取り。
- テキストコミュニケーション
- 文字情報を中心に伝える形式のコミュニケーション。
- メールコミュニケーション
- 電子メールを用いた情報伝達。
- タイミング
- 伝えるのに適切な時機を見極める能力。
- クリアな表現
- 分かりやすく、誤解を生まない言い回しを心掛けること。
- 言語表現
- 語彙選択・表現方法を整えて効果的に伝えること。
- 関係性構築
- 信頼と関係性を築くためのコミュニケーション活動。
- ミラーリング
- 相手の姿勢や話し方をさりげなく真似て親近感を高める技法。
- パラフレーズ
- 相手の言葉を自分の言い換えで言い直して確認する技法。
- インクルーシブコミュニケーション
- 誰も排除せず、包摂的に伝える工夫。
コミュニケーションのおすすめ参考サイト
- コミュニケーションとは|意味や種類、鍛える方法を解説 - Schoo
- コミュニケーションとは? 大切な理由、円滑にするポイントを解説
- コミュニケーションとは?円滑に行う方法やメリットを紹介 - Slack



















