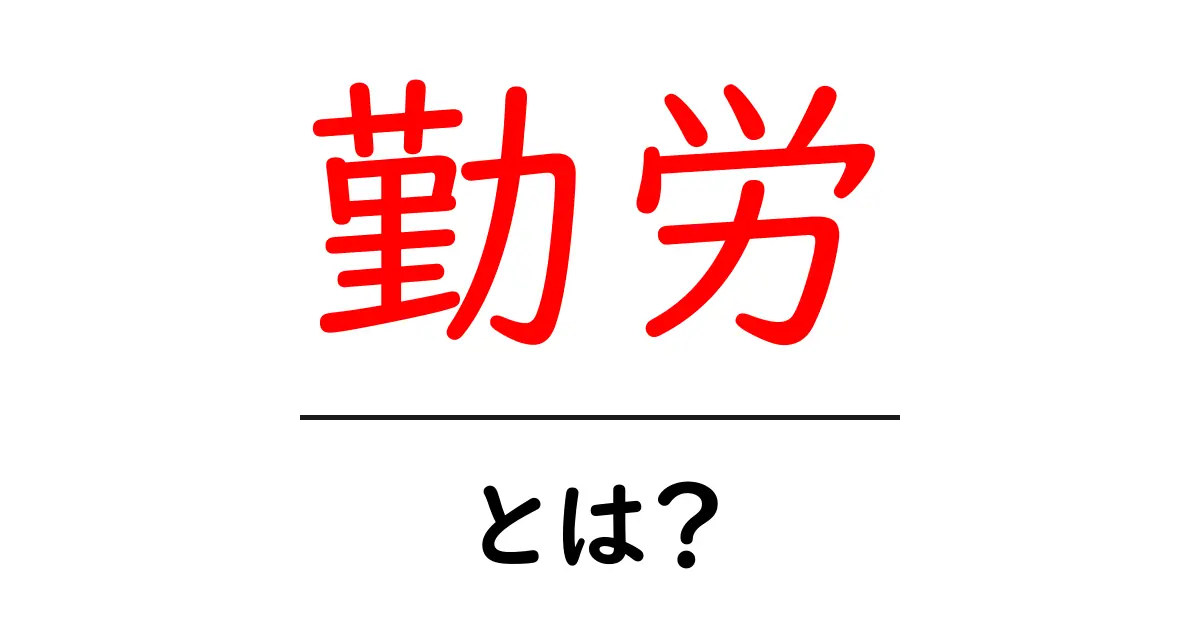この記事を書いた人
岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ)
ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」
年齢:28歳
性別:男性
職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動)
居住地:東京都(都心のワンルームマンション)
出身地:千葉県船橋市
身長:175cm
血液型:O型
誕生日:1997年4月3日
趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集
性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。
1日(平日)のタイムスケジュール
7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。
7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。
8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。
9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。
12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。
14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。
16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。
19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。
21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。
22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。
24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
勤労・とは?基本の意味
勤労とは、体を使って働くこと、あるいは社会のために働くこと全般を指す言葉です。日常語としては「働くこと」「仕事をすること」という意味で使われることが多いです。意味の幅が広く、文脈によって捉え方が変わることに注意しましょう。
勤労と労働の違い
似た言葉に「労働」があります。勤労は仏教や倫理、教育の文脈で宗教的・道徳的なニュアンスを含むことが多く、勤労観は「働くことを美徳とする価値観」です。一方、労働は経済的な側面を強く指す語で、雇用の場面や賃金、労働時間と結びつくことが多いです。日常会話では勤労と労働を区別せずに使うこともありますが、正確な場面で使い分けると伝わりやすいです。
なぜ勤労が大切なのか
勤労は社会の仕組みを動かす原動力です。人が働くことで、商品やサービスが生まれ、生活に必要なものが手に入ります。学校教育では勤労観を養うことが重視され、協力・責任感・粘り強さといった価値観を育てます。勤労を通じて自立心や社会性が育つと考えられています。
日常での勤労の使い方と例
日常の会話では「勤労」は教育的・倫理的な話題として使うことが多いです。例を挙げると、学校の作文で「勤労の尊さ」をテーマにしたり、歴史の授業で昔の勤労観を学んだりします。ビジネスの場面では「勤労」という語は少し堅い印象になるため、「働く」や「仕事をする」という言い方がよく使われます。
よくある誤解と正しい使い方
誤解のひとつは、勤労と労働を厳密に区別せず使うことです。正しくは、場面に応じて使い分けると伝わりやすくなります。もう一つは、勤労を「疲れること」や「つらいこと」の代名詞として使ってしまうことです。勤労は尊敬や価値観を含む語で、必ずしもつらさだけを意味しません。
表で学ぶポイント
ding='6'> | 語の意味 | 体を使って働くこと全般、または社会のために働くこと。 |
| 使われ方の特徴 | 倫理・教育・歴史文脈で使われることが多い。堅い言い回し。 |
| 対義語・関連語 | 対義語は「怠惰」や「休憩」。関連語は「働く」や「労働」。 |
able>まとめ
勤労とは何かを正しく理解することは、日常の会話や学習、将来のキャリア設計にも役立ちます。意味を押さえたうえで、場面に合わせた適切な言葉選びをすることが大切です。
勤労の関連サジェスト解説
- 勤労 奉仕 とは
- 勤労 奉仕 とは、労働と奉仕の意味を合わせて使う言葉です。元々は国や社会のために自分の労力を提供するという意味で使われてきました。現代ではこの言葉は必ずしも戦時的な意味だけでなく、地域社会のボランティア活動や学校の施設整備、清掃、福祉の手伝いといった奉仕活動全般を指すことが多くなっています。歴史的には戦時中に国民が工場や農作業、公共の仕事を手伝う形で推奨された時期があり、このときの「勤労奉仕」は協力と忍耐の価値を強調しました。しかし現在は「義務」というより「社会へ貢献する意欲的な参加」という意味合いが強く、硬い響きを避けて日常的なボランティア活動として語られることも多いです。学校では生徒がクラス活動の一環として校内外の清掃や花壇づくり、地域のお祭りの手伝いなどを行う場面が一般的です。地域の清掃活動や高齢者の見守り、イベントの運営補助といった活動も含まれます。参加のしかたは地域のボランティアセンターや学校のクラブ活動を通じて探すのがよいでしょう。準備としては動きやすい服装、手袋、飲み物、活動場所の安全ルールの確認が大切です。安全第一で進めること、無理をしないことを心がけましょう。このように勤労奉仕は、個人と地域をつなぐ橋渡しとなる体験です。人と協力して役割を分担し、地域をよりよくする喜びを学ぶ機会となります。
勤労の同意語
- 労働
- 働くこと全般。肉体・精神を使って生産的な作業を行う行為を指す最も一般的な語。
- 就労
- 仕事につくこと。雇用されて働く状態・行為を表すややフォーマルな語。
- 就業
- 雇用されて働くこと。就労している状態を指す語。就労と似るが、文脈で「就業機会」などの表現で使われることが多い。
- 勤務
- 職場で定められた職務を果たすこと。勤務時間や勤務先に関する語。
- 従事
- 特定の仕事や分野に携わって働くこと。熱心に取り組むニュアンスを含む。
- 労務
- 労働に関する作業・業務。組織運営や労務管理の文脈で使われる語。
- 労役
- 労働を課されること、または重労働を指す語。文語的・強いニュアンス。
- 作業
- 具体的な作業・工程を指す語。労働の一部を表す語。
- 仕事
- 職業で行う業務全般。日常語として広く使われる勤労の代替語。
- 働くこと
- 人が働くという行為そのものを指す一般的表現。文脈で語感が柔らかい。
- 職務
- 職場で担うべき任務・責任。就労・就業のニュアンスと重なるが、役割を強調する語。
- 業務
- 職場で行われる業務全般。責任・作業内容を指すビジネス寄りの語。
- 労働行為
- 労働を行う具体的な行為の総称。肉体・精神を使って働くことを指す表現。
勤労の対義語・反対語
- 怠惰
- 努力を惜しみ、勤労を嫌う性質・態度。日常的に働くことを避け、ぐうたらと過ごす状態。
- 無為
- 何もしないこと。行動を起こさず放置する状態で、勤労の対極としての非活動・不活発。
- 安逸
- 困難を避け、安楽な生活を求めて労働を避る暮らしぶり。
- 自堕落
- 自分の責務を怠り、だらしなく過ごすこと。勤労を選ばない生活態度。
- 怠慢
- 義務や職務を怠る傾向のある態度。真剣さが欠け、仕事を後回しにしがちな性格。
- 楽をする
- 労働を避け、楽を優先する行動・考え方。働くよりも楽を取ることを選ぶ
勤労の共起語
- 労働
- 働くこと全般。生活のために体・頭を使って価値を生み出す行為の総称です。
- 勤勉
- こつこつと真面目に働く性格や姿勢。努力を重ねることを指します。
- 労働者
- 雇用契約の下で働く人。現場で労働を提供する主体。
- 就労
- 仕事に就くこと。雇用に結びつく行為を指します。
- 就業
- 職に就いて働いている状態。勤務していることを指す語。
- 労働力
- 働く力。人の能力や体力、時間を指す総称。
- 雇用
- 人を雇って働かせること。雇用契約の成立と状態を指します。
- 賃金
- 労働の対価として支払われる金銭。報酬の一種。
- 給与
- 毎月や毎期支払われる賃金・報酬の総称。
- 働く
- 身体を動かして作業すること。最も一般的な動詞。
- 働き方
- どのように働くかというスタイル。時短勤務・リモート等を含む。
- 労働法
- 労働条件や権利を保護する法制度。就業ルールを定めます。
- 労働市場
- 労働力の需給が行われる市場。賃金・雇用機会が決まる場。
- 労働条件
- 賃金、労働時間、休日、福利厚生など、就労の条件全般。
- 労働時間
- 働く総時間。法定労働時間や実働時間を指します。
- 残業
- 通常の勤務時間を超えて働くこと。時間外労働を指す語。
- 福利厚生
- 給与以外の福利・支援制度。保険・休暇・福利厚生サービス等。
- 労働組合
- 労働者が組織する団体。待遇改善などを交渉する組織。
- 労災
- 労働に起因する事故や疾病の補償・保険制度。
- 安全衛生
- 職場の安全と健康を守る管理。安全対策・衛生管理を指す。
- 就職活動
- 就職先を探して応募する活動。エントリー・面接準備など。
- 失業
- 就業していない状態。職を失うこと、求職が必要な状態。
- 労働生産性
- 労働投入量あたりの生産量。効率性を表す指標。
- 待遇
- 給与・福利厚生・地位など、働く条件の総称。
- 労働力人口
- 就労可能な人口。就業者と完全失業者を合わせた集団。
- 労働契約
- 雇用者と労働者の間の契約。勤務条件・期間を定める合意。
勤労の関連用語
- 労働
- 人が身体や心を使って生計を立てる目的で行う活動。賃金を得るための活動を総称した概念。
- 労働者
- 賃金を得るために雇用されて働く人。企業と雇用契約を結ぶ当事者。
- 労働力
- 人が提供できる働く能力の総称。供給される労働資源のこと。
- 労働条件
- 賃金・就業時間・休暇など、働く環境や契約内容の条件のこと。
- 労働時間
- 働いている時間の長さ。法定労働時間を中心に管理される。
- 残業
- 所定労働時間を超えて働くこと。割増賃金の対象になることが多い。
- 長時間労働
- 通常の勤務時間を大幅に超えて働く状態を指す概念。
- 有給休暇
- 給与が支払われる形で取得できる休暇。公的権利として認められることが多い。
- 休日
- 法定休日や祝日など、仕事を休む日。働く人の休息日。
- 休暇
- 病欠・私用・産前産後など、特定の目的で取得する休みの総称。
- 賃金
- 労働の対価として支払われる報酬。基本給に加え各種手当が含まれることが多い。
- 給与
- 一定期間ごとに支払われる賃金の総称。月給・年給など。
- 手当
- 役職・資格・勤務地・扶養などに対する追加の報酬。
- 最低賃金
- 地域・産業別に法定される最低賃金水準。
- 雇用
- 人を雇って働いてもらうこと、就業関係の開始。
- 就労
- 就職して働くこと。日常的な労働の実践を指す。
- 就業
- 仕事に就くこと。実際に働き始める状態。
- 雇用形態
- 正社員・契約社員・派遣など、雇用の形のこと。
- 正社員
- 期間の定めがなく雇用される常用の従業員。
- 非正規雇用
- 契約社員・派遣・アルバイトなど、正社員以外の雇用形態。
- アルバイト
- 短時間で働く学生などの非正規の就労形態。
- パートタイム
- 短時間勤務の非正規の就労形態。
- 終身雇用
- 長期間同一企業で勤めることを前提とした雇用慣行。
- 年功序列
- 年齢や勤続年数に応じて昇給・昇進が決まる給与制度。
- 労働市場
- 働く人と雇い主の需要と供給が結びつく市場。
- 労働生産性
- 労働者一人あたりの生産量や付加価値を示す指標。
- 人材
- 企業が必要とする能力を持つ人。人材育成の対象。
- 人材育成
- 人材の能力を高める教育・訓練のこと。
- 人材市場
- 人材の供給と需要が動く市場。
- 雇用機会均等法
- 雇用機会の均等を図る法律。差別の禁止などを定める。
- 労働法
- 労働関係を規律する法律の総称。
- 労働基準法
- 労働条件の最低基準を定める主要法。
- 労働契約法
- 労働契約の基本原則・解雇等を規定する法律。
- 労働組合法
- 労働組合の権利と組織の規定を定める法律。
- 労働関係調整法
- 労使関係の紛争を調整する法律。
- 労働組合
- 労働者が団結して集団交渉を行う組織。
- 労働災害
- 労働中の事故・疾病による被害。
- 労働安全衛生法
- 労働環境の安全と衛生を確保する法規。
- 労働安全衛生
- 労働環境の安全と健康を守るための取り組み。
- 安全衛生
- 職場の安全と衛生を指す総称。
- テレワーク
- 自宅など離れた場所での就労形態。
- 在宅勤務
- 自宅での勤務形態。
- 働き方改革
- 長時間労働の是正など働き方を改革する政策・取り組み。
- ワークライフバランス
- 仕事と私生活の両立を重視する考え方。
- 派遣
- 人材を他社へ派遣する雇用形態。
- 労働者派遣法
- 派遣労働者に関する法律。
- 派遣社員
- 派遣会社に雇われ、他社で働く雇用形態の人。
- 労働訴訟
- 労働関連の紛争を裁判で解決する法的手続き。
- 労働審判
- 労働紛争の簡易裁判手続。迅速な解決を目指す。
- 就業規則
- 企業が従業員に適用する就業の規則。
- 職業訓練
- 職業能力を高める訓練・教育。
- 失業
- 働く意思と能力があるが職を得られない状態。
- ブラック企業
- 過重労働・低待遇など従業員にとって健全でない企業を指す俗称。
勤労のおすすめ参考サイト
社会・経済の人気記事

398viws

327viws

226viws

188viws

171viws

163viws

128viws

127viws

124viws

115viws

112viws

99viws

84viws

83viws

83viws

81viws

81viws

81viws

79viws

78viws
新着記事
社会・経済の関連記事