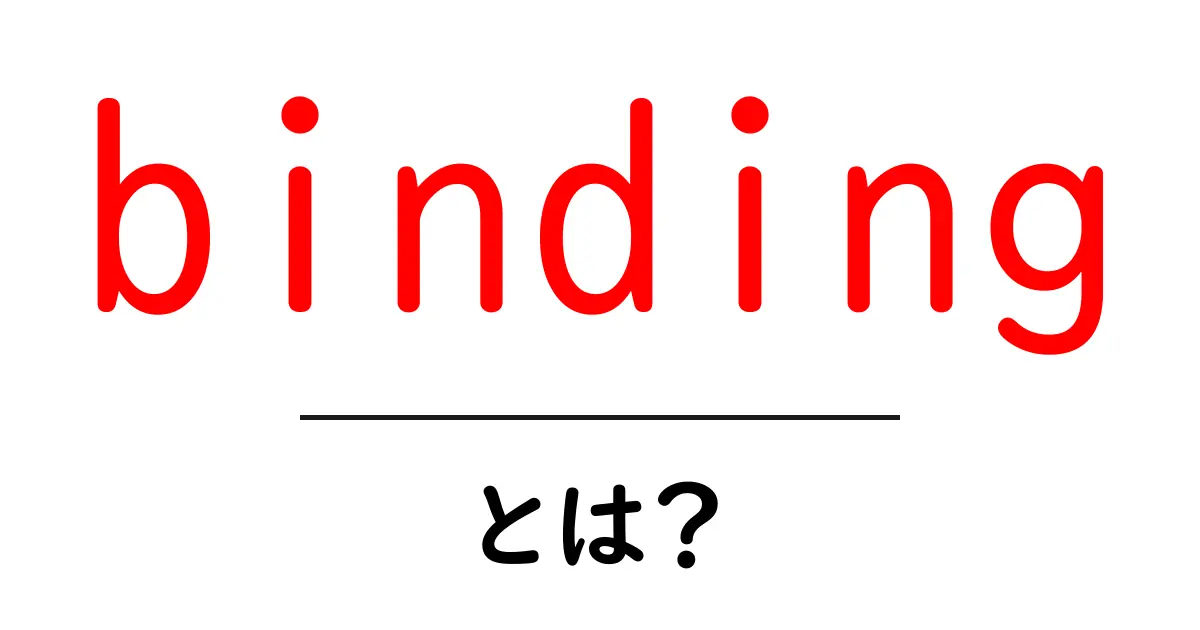

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
bindingとは何かをわかりやすく解説します
bindingとは英語の動詞 bind の名詞形で結びつけることを意味します。IT の分野では何かを別のものと結びつけて扱えるようにする考え方を指します。本稿では初心者向けに binding の基本と日常的な使い方を分かりやすく解説します。
まず押さえるべき点は三つです 一つ目は結びつける対象が何かを決めること 二つ目は結びつける仕組みがどのように動くかを理解すること 三つ目はその結びつけを活用して作業を効率化することです
1 binding の基本となる考え方
binding の基本は 名前と実体を結ぶことです プログラミングの世界では変数に値を割り当てる作業や UI とデータを結びつける作業がつねに登場します
変数の束縛 とはプログラミングで使う用語で変数とその値の関係を作ることを指します 例えば ユーザーの得点を保存する変数 n に点数を格納する というイメージです
2 代表的な使い方
binding にはいくつかの場面があります ここでは代表的な三つを紹介します
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 変数の束縛 | プログラミングで変数名と実際の値を結びつけること |
| データバインディング | ユーザーが入力したデータと画面上の表示を連携させる仕組み |
| イベントバインディング | イベントと処理を結びつけ クリックなどの動作に反応させる |
3 具体例でイメージをつかもう
例1 人物名と年齢を結ぶ場面を考えます 画面には名簿があり そこに表示する名前を bindings により決定しています もし名前が変われば表示も自動で更新される 想像してみてください
例2 Web ページの入力欄と表示欄をバインディングすると ユーザーが入力するたびに表示が変わっていきます このときプログラムは 入力と表示を結びつける橋渡しの役割をします
4 よくある誤解と注意点
binding はただの結びつけ操作だけではありません 実装の仕方によって動作の速度や読みやすさに差が出ます 無理にたくさんのデータを同時に結びつけようとすると処理が遅くなることもあります
5 まとめ
binding とは 何かと何かを結びつけて扱える状態をつくる考え方です 変数の束縛からデータの連携 さらにイベントのつなぎ方まで 広く使われます 初心者はまず日常の例を思い浮かべて 具体的な場面を見つけて練習すると理解が進みます
最後に 実務で binding を使うときのコツとしては 目的を明確にし 適切な結合レベルを選ぶこと 読みやすさと保守性を優先すること です
bindingの関連サジェスト解説
- binding とは プログラミング
- binding とは プログラミングの中で、何かを別のものと結ぶ作業のことです。プログラミングでは、主に「名前と値を結びつけること」「データと表示を結びつけること」「呼び出す機能をどの形で結びつけるか」という意味で使われます。初心者には、まず『名前を値に結びつける』感覚から理解すると良いです。名前のバインディングの例として、Python や JavaScript のような言語で x = 5 と書くと、名前 x が値 5 に結びつきます。これを「名前を値に結びつける」作業と考えると、プログラムがどう動くかを想像しやすくなります。次に静的バインディングと動的バインディングについてです。静的バインディングは、どの関数が呼ばれるかがコンパイル時や書き方の時点で決まっていることを指します。動的バインディングは、実行時にどの関数が呼ばれるかが決まる仕組みで、オブジェクト指向の多態(ポリモーフィズム)の基礎にもなります。データバインディングは、UI開発でよく使われる考え方です。入力欄に文字を打つと、その文字が自動で表示エリアに反映されるといった“結びつけ”の仕組みを指します。これにより、プログラムの見た目が直感的に動くようになり、作業の効率も上がります。プログラム全体を考えるとき、バインディングは「どの情報をどこに結ぶか」を整理するための便利な考え方です。初心者の方は、まず変数へ値を割り当てる名前のバインディングを練習し、次に動的と静的の違い、そしてデータバインディングの考え方へと進むとよいでしょう。
- non-binding とは
- non-binding とは、英語で『拘束力がない』という意味です。つまり、ある約束や文書が法的に強制される義務を生じさせない状態を指します。日常では、商取引の交渉段階や提案、覚書(MOU)、見積もりなどによく使われ、後で正式な契約を結ぶかどうかを決める前の“前提条件”的な合意として扱われます。非拘束的な文言が入っていると、相手は「この案が絶対に成立する」とは言えず、相手の承諾や署名が法的拘束力を持つ契約へと移行することを意味します。実務では、覚書や提案書に「この文書は非拘束的です」「本提案は将来の契約締結を意図するものであり、法的拘束力を生じません」といった表現が使われます。こうした表現の目的は、双方が自由に交渉の範囲や条件を探ることを可能にする点です。ただし“非拘束的”だからといって、倫理的な責任や商業的信頼が消えるわけではありません。発言や提示した情報が不正確であれば信頼を傷つけることもあり得ます。また、入札や公共契約、業界慣行などの場面では、特定の部分だけが binding だったり、条件付きで拘束力を持つ場合もあるため、契約書の文言をよく確認することが重要です。まとめると、non-binding は「今はまだ法的な義務を生じさせない状態」を指す用語で、交渉の段階を進める際に使われる便利な表現です。
- intentional binding とは
- intentional binding とは、自分が意図して行った行為とその結果が時間的に近く感じられる現象のことです。私たちは普段、行動した後に結果が起きるまでの時間を実際のように感じますが、この現象ではその感じ方が短くなるのです。つまり、行動と結果を“つながっている”と感じやすくなります。研究では、被験者がボタンを押すと数百ミリ秒後に音が鳴るようにします。被験者には「自分の行動と音のどちらが早く起きたと感じたか」を答えてもらいます。多くの場合、実際の間隔よりも短く感じられて、行動の時刻が音の時刻に近づき、結果として二つの出来事の間の時間感覚が短くなるのです。この現象は、私たちが自分の意思で動いたと感じる気持ち(自己のコントロール感=自己感覚)を研究する手がかりになります。予測が正確なときや結果が予想どおりだとき、結合は強くなることが分かっています。日常の場面でも、自分の操作が結果につながるとき、時間の感じ方が変わることがあります。ゲームをして操作と結果のつながりを強く感じると、時間が短く感じられることがあるでしょう。脳の中では、動かす計画を立てる部分と結果を予測する部分が協力して働くと考えられています。これを詳しく知ると、自己意識の乱れをもつ病気のときの理解が進む可能性もあります。要するに、intentional binding とは、私たちの行動と結果の関係を“近く感じる”現象のことです。意図や予測が関係しており、日常生活や心理学・神経科学の研究にも役立つ大切な考え方です。
- http post binding とは
- http post binding とは、ウェブ上のやり取りで使われる「取り決め」の一つで、データをどう伝えるかを決めるルールです。binding は“取り決め”という意味で、HTTPという通信手段と、データの形式や配置の約束を組み合わせたものを指します。特に HTTP POST を使う binding は、クライアントがサーバへデータを「ボディ」として送り、サーバが処理結果を返す形をとります。日常の API 利用では、何かを新しく作るときや情報を送るときに POST が使われます。例えば、ウェブサイトの会員登録で名前やメールアドレスを送るとき、データは URL には載らず、リクエストの body に入ります。これが POST binding の基本です。POST でデータを送る利点は、大量の情報を送れることと、配列やファイルなど複雑なデータを送れる点です。欠点は、URL での閲覧履歴が残らない代わりに、リクエストの中身を適切に保護する必要がある点です。セキュリティの観点では HTTPS を使い、データの形式を Content-Type ヘッダで伝えます。代表的な形式として JSON(application/json)、フォームデータ(application/x-www-form-urlencoded)、ファイルを含む場合の multipart/form-data があります。使い方の流れは、1) エンドポイント(API の URL)を決める、2) HTTP メソッドを POST にする、3) ヘッダで Content-Type を指定する、4) ボディに送るデータを用意して送信する、5) サーバ側が処理結果やエラーメッセージを返す、という順です。実際の例として curl を使うと、curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"太郎","age":15}' https://example.com/api/users のように送ります。GET との違いは、GET が URL にデータを載せるのに対し、POST はボディに載せる点、データ量の制限が少なく、機密性を保つには HTTPS が必須である点です。初心者でもこれを押さえれば、Web API の基本的なデータ送信が理解できます。
- data binding とは
- data binding とは、データと表示を結びつけて、データが変わると画面も自動で変わる仕組みのことです。ウェブやスマホアプリのUIづくりで、入力した値をそのまま表示に反映させたり、表示を見ただけでデータの状態を把握したりする場面でよく使われます。例えば「名前を入力する欄」と「挨拶の表示」のような場合、名前が変わると挨拶の文も自動で変わると便利です。データと表示を結び付ける方法には主に二つの考え方があります。一つは一方向のデータバインディングで、データの変更は表示にのみ伝わり、表示を変更してもデータには影響を与えません。もう一つは双方向のデータバインディングで、データが変わると表示が変わるだけでなく、表示を変えるとデータも変わります。現代の多くのフレームワークはこの二つを組み合わせて使います。実務では、画面の初期表示をデータから作るワンウェイのバインディングと、ユーザーが入力するたびにデータを同期させる双方向のバインディングを使い分けるのが基本です。初心者が覚えるべきポイントは、データとUIの関係を「結びつける設定」を理解することと、どの変化をどの順序で更新するかを意識することです。バインディングを正しく使えば、コードの重複を減らし、UIとデータの整合性を保つのが楽になります。ただし過度に多くのバインディングを一箇所に集めすぎると、どこがデータを変えたのか分かりにくくなるため、適度な範囲で使うのがコツです。初めて学ぶときは、身近な例を用意して小さなアプリから練習すると良いでしょう。
- wpf binding とは
- WPF binding とは、Windows Presentation Foundation(WPF)で使われるデータとUIを結ぶ仕組みのことです。データの変更を自動で画面に反映させたり、画面の操作をデータに伝えたりするためのしくみで、UIとデータを分離して開発を楽にします。基本の考え方は、UIの表示部分をデータの値に“結びつける”ことです。UI要素のプロパティを、別の場所のデータに合わせて自動的に更新できるので、手動で画面を書き換える必要が少なくなります。DataContext というデータの置き場所を決め、それを UI の近くに置くのが普通です。DataContext に設定したデータの中にある Name や Age のようなプロパティを、UI の各部品が参照します。Path は、データの中のどのプロパティを使うかを指します。例えば Name という名前のプロパティを使いたいときは Path となり、実際の XAML では省略されることがあります。Binding には方向性があり、OneWay はデータが変化すると UI が自動で更新されます。TwoWay は UI で値を変えたとき、データ側にも反映します。TwoWay を使うと、フォームの入力欄とデータが常に同期します。ただし、データ側が変わったことを UI に知らせる仕組みも必要です。通常はプロパティが値を変えたときに通知する INotifyPropertyChanged を実装します。これにより、データの更新がすばやく画面に伝わります。変換の仕組みも重要です。IValueConverter を使うと、データの値を表示用に変換できます。Boolean を文字列に変えるなど、表示を柔軟に調整することができます。UI の検証や条件付き表示を実現する場面でも役立ちます。日常のコツとしては、まず DataContext の設定場所を意識すること、Path の指定が実データのプロパティ名と合っているかを確認すること、UI 側とデータ側の更新の流れを意識することです。難しく見える binding ですが、慣れると UI の更新を自動化でき、アプリの保守性が高まります。よくある失敗としては、DataContext が想定外の場所にある、Path が間違っている、TwoWay の時に値が変わらない などです。これらはデバッグを重ねるうちに解決できます。このように WPF binding とは、データと UI をつなぎ、画面の表示を自動で保つ大切な仕組みです。正しく使えば、入力・表示・データの連携がスムーズになり、初心者でも洗練されたアプリを作る第一歩になります。
- library binding とは
- library binding とは、図書館用に作られる本の製本方法のことを指します。図書館では本が何千回も貸し出され、棚の出し入れや移動、返却の際の摩擦に耐える必要があるため、一般の書店用の製本より耐久性を重視した作りになります。具体的には、紙の綴じ方に糸で縫う“糸綴じ”を採用し、見返しや中身のページをしっかりと支える強度を確保します。表紙は硬いボードで作られることが多く、布やビニール素材のカバーで覆われることもあります。背には補強テープを貼ることが多く、長く使っても背が曲がりにくい設計です。図書館向けの製本では、耐水性や耐摩耗性のある紙を選ぶことや、長時間の貸出にも耐えられるよう接着剤の選択を工夫する場合があります。さらに図書館独自のラベルや識別用の加工、返却時のダメージを防ぐ角の保護など、現場で使いやすい工夫も盛り込まれます。このように library binding は、耐久性と長寿命を両立させる製本方法として広く用いられ、家庭用の製本に比べて制作コストが高くなることが多いですが、頻繁に扱われる本を長くきれいな状態で保つことができます。
- legally binding とは
- legally binding とは、法的に守らなければいけない約束のことを指します。難しく感じるかもしれませんが、実は身の回りの契約に多く関係しています。一般に、約束を守らせる力が法律によって与えられている状態をさすのが legally binding です。たとえば家を借りるときの賃貸契約、アルバイトの雇用契約、車をローンで買うときの契約、スマホの利用規約などが挙げられます。これらは「約束したことを守るべきだ」という法的な義務を伴います。読者が誤解しやすい点として、オンラインの利用規約すべてが必ず法的拘束力を持つわけではないことがあります。読みやすく明確に示され、同意した証拠がある場合に、法的な力が生まれることが多いです。どうして法的拘束力が生まれるのかというと、契約の中に約束と対価、双方の合意、そして有効な形がそろうと、裁判所が介入して問題解決を助けられるからです。身近な例としては賃貸契約、雇用契約、ローン契約、アプリの利用規約などがあります。注意点として、すべてのオンライン約束が自動的に法的拘束力を持つわけではありません。場合によっては証拠が必要です。署名、日付、相手の正確な情報がそろって初めて拘束力が強くなることも多いです。中学生が気をつけるポイントは次のとおりです。約束の内容をよく読み、いつまでに何をどうするのかを確認する。自分が同意したことを証明できる記録を保つ。相手が信頼できる人や組織かを考える。分からない点は大人や先生、法律の専門家に質問する。まとめとして、legally binding とは法的に守られるべき約束のこと。身の回りの契約を理解して正しく扱えば、困ったときに自分を守る力になります。
- dhcp binding とは
- dhcp binding とは、DHCP サーバーと端末の間でこの端末にはこの IP を使ってくださいと結びつける仕組みのことです。家庭のルータでも、パソコンやスマホ、プリンタなどは自動で IP が割り当てられます。しかし、プリンタの IP が変わると印刷設定が面倒になることがあります。そこで、機器の識別に使われる MAC アドレスと、割り当てたい IP アドレスをセットで覚えさせておくと、同じ端末には次回も同じ IP が返ってくるようになります。これを DHCP の予約、固定割当、あるいはバインディングと呼びます。動的割り当ては機器がネットワークに接続するたびに DHCP が空いている IP を割り当て、再接続時には IP が変わることもあります。一方で予約を使えば、同じ端末には常に同じ IP が割り当てられる保証が得られます。設定はルータや DHCP サーバーの管理画面で、端末の MAC アドレスと希望の IP を登録します。手順は機器ごとに異なりますが、基本は MAC アドレスを確認 → DHCP の予約リストに追加 → 保存・適用 の3ステップです。注意点としては、同じネットワーク内で IP が衝突しないよう、割り当てる IP が既に使われていない範囲を選ぶことと、リース時間の設定にも気をつけることです。DHCP binding を理解しておくと、ネットワークの管理が楽になり、機器の接続トラブルを減らすことができます。
bindingの同意語
- 縛り
- 物理的・比喩的に結び付けて動作を制限すること。規則や条件が自由を抑制するニュアンスで使われる。
- 拘束
- 動作や選択を抑制・制限すること。法的・倫理的な拘束力を伴う場面で用いられる。
- 束縛
- 自由を大きく制限する状態や行為。厳しい制約を表す語。
- 結束
- 人や団体が結びついてまとまる状態。協力・団結の強さを表す。
- 結合
- 二つ以上のものが結びつくこと。化学的・物理的・情報的な連携を含む総称。
- 結びつける
- 異なる要素を結びつけて関連づけること。データ・概念・事象を結びつける動作。
- 結びつき
- 結びついた状態・関係性。関連性が成立していることを指す。
- 紐付け
- 情報やデータを紐づけて関連づけること。データ管理で頻繁に使われる表現。
- データ紐付け
- データ同士を結びつけ、関連性を持たせる作業・技術。データ統合の基本。
- データ結合
- データを結合して新しいデータ構造を作ること。複数データの統合を意味する。
- リンク付け
- ウェブやデータ間の関連付け・参照を設定すること。
- 連携
- 複数の要素が協力して機能する状態。結びつきを強化する意味で使われる。
- 契約
- 法的に拘束力のある取り決め。契約は当事者を結びつけ、義務を生み出す。
- 契約書の拘束力
- 契約の内容が法的に守られる力。契約が持つ拘束力の具体的な表現。
- 拘束力
- 行動を制限する力・義務づける力の総称。
- 法的拘束力
- 法によって義務が課される力。契約・規程が持つ強さを指す。
- 法的効力
- 法的に認められた効力・影響。契約や規則が与える実務上の影響。
- 制約
- 自由や選択を制限する条件やルール。デザイン・計画・学習など幅広い場面で使われる概念。
- 制約力
- 規則や条件がもたらす、自由の抑制力。
- 製本
- 本を綴じて一冊の本として仕上げる工程。物理的な本の組み立てを指す用語。
- 綴じ
- 紙を糊・糸・針などで束ねて綴じる作業。
- 中綴じ
- 背を内側で綴じる製本法の一つ。
- 平綴じ
- 背を平らにして綴じる製本法の一つ。
- 装丁
- 本の外観を整えるデザイン・構成。外部の見た目を決定づける要素。
- 縛る
- 紐やロープで強く結ぶこと。比喩的に規制・抑制を表すこともある。
- 束ねる
- 複数のものをまとめて束にすること。整理・統合のニュアンス。
- 結び目
- 結んだ箇所の形・場所。物理的な結び目を指す語。
- バインディング
- 英語の binding のカタカナ表記。IT・プログラミングでデータとUIの結びつけを指す技術用語。
- バインド
- bind の名詞化・動詞形として使われる表現。データや機能を結びつける動作を指す。
- 結合エネルギー
- 原子・分子間の結合を作るのに必要なエネルギー。科学用語。
- 結合力
- 結合を保つ力。物理的・化学的な結合を表す基本語。
bindingの対義語・反対語
- ほどく
- 結び目を解いて縛りを外す行為。物理的な解放を指す。
- 解く
- 結び目・束縛を外す行為。一般的な解放の動作。
- ほどける
- 結び目・縛りが外れる状態。自然にほどける。
- 解放
- 束縛・拘束から解き放たれ、自由になる状態。
- 自由
- 他者の制約がなく、行動・思考を自由に選択できる状態。
- 自由化
- 制度・規制・拘束を緩和して自由度を高めること。
- 非拘束
- 拘束・束縛がない性質・状態。
- 非拘束的
- 拘束を生じさせない性質。
- 無拘束
- 拘束が全くない状態。
- 拘束されない
- 拘束を受けない状態。
- 非結合
- 化学的には結合していない、結合を持たない状態。
- 緩める
- 結び目・締めつけを緩めて拘束を弱める動作。
- 緩む
- 締めつけが弱まる、拘束が解かれていく状態。
- 開放
- 束縛を解除して外へ開く状態。自由に開く意味合い。
- 解き放つ
- 束縛を取り除き、積極的に解放する行為。
- 離す
- 束縛を物理的・比喩的に解く・解放する行為。
bindingの共起語
- 静的束縛
- プログラムにおいて、名前と値の結びつきがコンパイル時に決定され、実行時には変更されない性質。
- 動的束縛
- 実行時に名前と値の結びつきが決定され、実行中に変更され得る性質。
- 早期束縛
- 結びつきを可能な限り早い段階で確定させる設計・現象。
- 遅延束縛
- 結びつきを実行時まで遅らせる設計・現象。
- バインド変数
- SQLやプリペアドステートメントで、値を割り当てるためのプレースホルダ(仮の変数)。
- データバインディング
- データと表示要素(UI)を自動的に結びつけて同期させる仕組み。
- 変数束縛
- プログラミングで変数と値を対応づけること。
- 束縛条件
- 変数や表現が適用される際の条件・規則のこと。
- 拘束力
- 契約・規則が相手に強制的な効力を持つ性質。
- 拘束条件
- 何かを成立させるための制約条件。
- 結合エネルギー
- 2つの分子が結びつく際に必要なエネルギーの量。
- 結合親和性
- 分子が結合する力の強さを示す指標。
- 結合部位
- 分子が化学結合を形成する具体的な場所(部位)。
- 結合サイト
- 結合が起きる特定の部位(サイト)。
- 結合ポケット
- 結合が起きる局所的な空間領域。
- 結合
- 物理・化学での“結びつき”や、複数要素のつながりを指す一般用語。
- 製本
- 本を表紙・背表紙と綴じ具で綴じて冊子にする工程。
- 装丁
- 本の表紙・見た目を整えるデザイン・加工。製本とセットで使われることが多い。
- 中綴じ
- 冊子を中央で綴じる製本方法。
- 平綴じ
- 背を平らにして綴じる製本方法。
- 包帯
- 傷口を保護・固定するための布製の巻き方。
- 束縛時期
- プログラムで名前が値に結びつくタイミングを表す概念。
- 束縛理論
- 言語学で名詞句が前方の語をどう参照(束縛)するかを扱う理論。
bindingの関連用語
- バインディング
- 要素やデータを結びつけ、同期を取る仕組みの総称。UIやデータソース、イベントなどと結びつけ、表示と状態を連携させます。
- データバインディング
- データとUIを結びつけ、データの変更を自動的に表示へ反映させる仕組み。基本はデータと表示の自動同期です。
- 双方向データバインディング
- データの変更がUIに、UIの変更がデータに同時に反映される、双方向の結びつき。
- 単方向データバインディング
- データから表示へ一方向のみ反映される結びつき。UIの更新はデータを参照するだけの場合が多い。
- UIバインディング
- UIの要素(テキスト、入力欄、属性など)をデータと結びつけ、表示を動的に変える手法。
- プロパティバインディング
- データのプロパティとUI要素のプロパティを結びつけ、値の同期を行います。
- イベントバインディング
- ユーザーの操作イベントと処理を結びつける仕組み。ボタンのクリックなどを対応づけます。
- 静的バインディング
- コンパイル時・設計時に結びつけを確定させる手法。実行時の変更は難しいことが多い。
- 動的バインディング
- 実行時に結びつきを決定・変更する手法。柔軟性が高いがパフォーマンスに影響することも。
- 関数バインディング
- 特定の関数を特定のオブジェクトや変数に紐づけること。JavaScriptのbindなどの例があります。
- 変数の束縛
- プログラミング言語で変数に値を結びつけ、参照可能にすること。別名「変数の割り当て」。
- パラメータバインディング
- SQLなどでプレースホルダに値を結びつけ、実行時に安全に値を挿入する手法。
- SQLパラメータバインディング
- データベースクエリのプレースホルダへ値を割り当てる安全な方法。SQLインジェクション対策にも有効。
- ソケットバインディング
- ネットワークでソケットを特定のアドレスとポートに結びつけ、通信を開始可能にする処理。
- アドレスバインディング
- 通信相手のアドレスを結びつけて宛先を決定すること(ネットワーク・ソフトウェアの設定で使われます)。
- 依存性注入のバインディング
- DIコンテナなどで、必要な依存関係を適切な実装へ結びつける設定。
- バインド式
- データバインディングを定義する式。データとUIの動的連携を表現します。
- バインディングライブラリ
- データバインディングを簡便に実現するライブラリ群。例えばVue、React、Angularの関連機能など。
- サーバーサイドバインディング
- サーバー側のデータとクライアント表示の結びつきを管理し、表示を更新します。



















