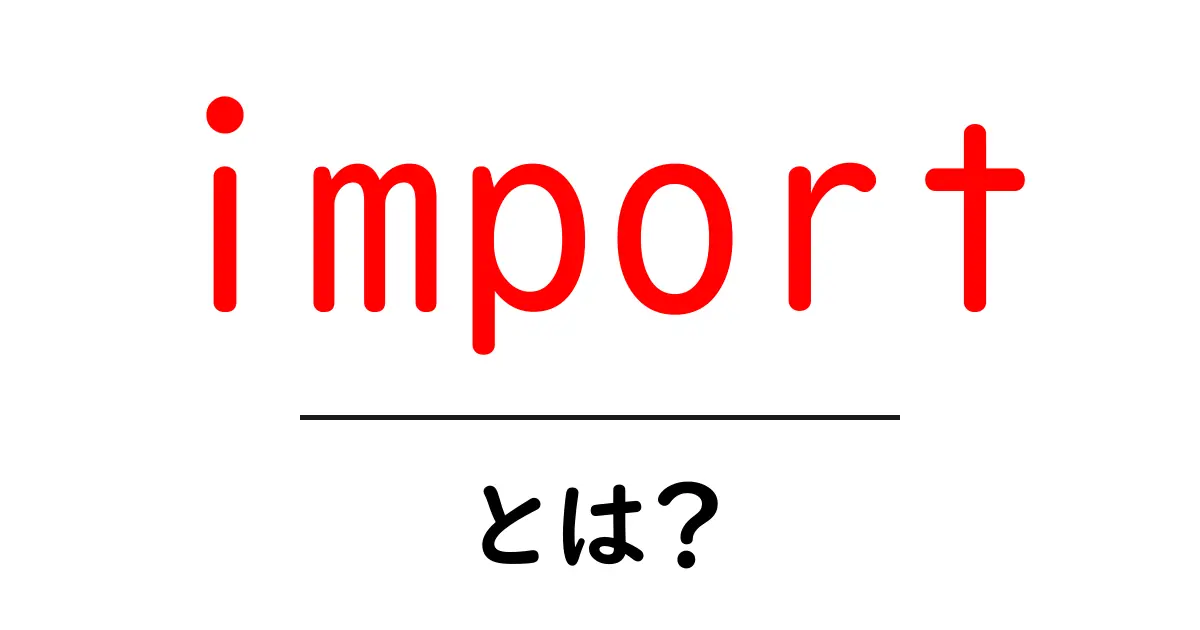

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
importとは?
プログラミングをするとき、別の人が作った部品を使いたいことがあります。そういうときに使うのが import です。import は「外部の機能を自分のプログラムに読み込む」命令のこと。日本語では「他のモジュールを取り込む」と表現されることが多いです。
ここでは代表的な使い方を中学生にもわかるように、Pythonを例にとって説明します。他の言語にも基本的な考え方は共通しているので、読み進めるとイメージがつかみやすくなります。
Pythonの基本的な使い方
Python では外部のモジュールを取り込むときに import を使います。例を見てみましょう。まずは数学の機能を持つモジュールを読み込みます。
import math
これで math という道具箱を使えるようになり、中の関数を使えます。例えば円周率は math.pi、平方根は math.sqrt です。実際の使い方は次のようになります。
print(math.pi)
print(math.sqrt(16))
ここでは math という名前のモジュールを読み込み、math.pi と math.sqrt を使っています。別の言語では書き方が少し違いますが「import で外部の機能を使えるようにする」という考え方は同じです。
特定の名前だけを取り込む
モジュール全体を読み込むのではなく、必要なものだけを取り込みたいときがあります。その場合は from を使います。例は以下の通りです。
from math import sqrt
このときは sqrt だけを直接使えます。つまり sqrt(16) のように書くだけで済みます。
よくある注意点
・import は通常、プログラムの最初に書きます。実行時に読み込まれ、使える状態になります。
・同じモジュールを何度も読み込んでも、実際には1回だけ読み込まれ、以降はキャッシュされます。これが効率の理由の一つです。
・読み込もうとしたモジュールが見つからない場合、ImportError などのエラーが出ます。正しい名前とパスを確認しましょう。
他の言語の“import”感
Java では import を使ってクラスを読み込み、JavaScript では ES6 モジュールとして import を使うことが多いです。言語によって書き方は違いますが、目的は「外部の機能を使えるようにすること」です。
要点を整理した表
importの関連サジェスト解説
- import とは python
- import とは python の世界で、他のファイルにある機能を今このプログラムで使えるようにする仕組みのことを言います。モジュールというのは、機能をまとめたファイルのことです。Python には標準で用意されたモジュールがたくさんあり、いちいち自分でゼロから作らなくても便利な機能を取り出して使えます。例えば math モジュールには数学の関数が集まっています。使い方はとてもシンプルです。まず import モジュール名 と書くと、そのモジュールを使えるようになります。実際にはダブルクォーテーションは使いません。次に モジュール名.関数名 などの形で中の機能を呼び出します。例を見てみましょう。import mathprint(math.sqrt(9)) # 3.0print(math.pi) # 3.14159...このときのポイントは、モジュールが別のファイルであること、インタプリタがどこを探すかを決めるパスという概念があることです。標準ライブラリは最初から使えますが、外部のパッケージを使うには pip でインストールします。from モジュール名 import 関数名 の形を使えば特定の機能だけを取り出して使うこともできます。さらに import … as … と書いて別名をつければ、長い名前を短く呼ぶこともできます。実際のコードを見ながら慣れていくことが大切で、最初は自分がよく使う機能だけを取り出して練習すると良いでしょう。
- import とは java
- Javaには、importという命令があり、別のパッケージにあるクラスを自分のプログラムで使えるようにするためのものです。importはパッケージ名とクラス名を宣言し、その後のコードでそれらを短い名前で使えるようにします。例えば import java.util.List; をファイルの先頭に書くと、List という名前だけで java.util.List を指すことになります。import が必要な理由として、コードを読みやすくし、長い名前を毎回書く手間を省くことが挙げられます。importはクラス単位でも、パッケージ内の複数のクラスを一度に取り込むワイルドカード import でも使えます。例: import java.util.*; これで java.util パッケージのすべてのクラス名を List キーとして使えますが、全てを一度に読み込むとコンパイルや読みやすさに影響が出ることもあるので注意してください。重要なポイントは、import文はファイルの最初の方に置くこと、そして java.lang は特別で自動的にインポートされるため、例えば String や System は import せずにそのまま使える点です。また、static import という少し高度な機能もあり、静的メンバーを名前なしで使えるようにすることができます。実際のコード例として、import java.util.List;import java.util.ArrayList;public class Sample { public static void main(String[] args) { List
names = new ArrayList<>(); names.add("太郎"); System.out.println(names.size()); }}このように、importを使うと長い名前を短く書け、コードの読みやすさと保守性が上がります。 - @import とは css
- @import とは css の文法の一つで、別のスタイルシートを現在の CSS ファイルに読み込むための指示です。これを使うと、複数のファイルを一つのまとまりとして管理しやすくなります。基本の書き方には、@import url("styles.css"); や @import "styles.css"; などがあり、読み込むファイルを指定します。さらに、読み込む際にどの環境で適用するかを指定することもできます。たとえば @import url("print.css") print; のように、印刷時だけ適用するファイルを用意することができます。別の例として、@import url("desktop.css") screen and (min-width: 800px); のように、画面サイズが特定の条件のときだけ読み込む設定も可能です。@import を使うと、層状に CSS を分割して整理できますが、使用にはいくつかのポイントがあります。まず、@import は基本的に他のルールよりも先に読み込まれるべきで、@charset の後に置くのが原則です。次に、読み込みは順序に依存するため、どのファイルを先に読み込むかで後のスタイルが上書きされることがあります。これが意図しないスタイルの崩れにつながることもあるので注意しましょう。もう一つの大事な点は、@import は新しいネットワークリクエストを作成するため、ページの表示が遅くなる可能性があることです。現代のウェブでは、パフォーマンスを重視する場面では HTML の タグを使って外部 CSS を読み込む方が適している場合が多いです。とはいえ、モジュール的な管理や、複数ファイルを一つのテーマとしてまとめたい場合には @import が有用です。初心者の方は、まず基本的な書き方と、読み込み順の関係、媒体条件の使い方を覚えることから始めると良いでしょう。また、Sass や PostCSS などのプリプロセッサを使うと、より効率的に CSS を分割・管理できるため、将来的にはそれらのツールと組み合わせて活用するのもおすすめです。ぜひ実際のサンプルを作って、@import の挙動を自分の目で確かめてみてください。
- inland haulage import とは
- inland haulage import とは、海外で生まれた商品が日本などの国へ入国した後、国内の陸上輸送で配送される一連の過程を指します。ここで大事なのは“陸上輸送”と“輸入”という二つの意味を同時に理解することです。陸上輸送とは、船や飛行機で海外へ運んだ貨物を、国内でトラックや鉄道などの陸上交通手段を使って目的地へ届ける動きを意味します。つまり、港での通関を経た貨物を内陸の倉庫や店舗まで運ぶ全体の作業を inland haulage import とはと呼びます。この流れにはいくつかの役割が関わります。貨物を取り扱う運送会社やフォワーダー、税関を手伝う通関士、荷物の追跡を管理する3PLなど、複数の専門家が関与します。実務では、出荷元と現地の輸入先の合意を示すインコタームズ(例: DAP、DDP)や、商業インボイス、梱包明細、船荷証券などの書類が必要です。これらを準備することで、遅延や追加費用を抑えることができます。具体的な例として、日本に衣料を輸入するケースを考えます。海上輸送で横浜港に到着し、税関の審査を経て国内の配送センターへトラックで運ばれます。これが inland haulage import の典型的な流れです。注意点として、コスト管理や貨物の安全性、遅延防止、追跡の重要性、混載便の活用、荷姿の適切な表示などを意識すると良いでしょう。
- terraform import とは
- terraform import とは、すでに存在するリソースを Terraform の管理下に取り込む機能です。これを使うと、クラウド上にある既存の仮想マシンやストレージ、ネットワークなどを新しく作るのではなく、Terraform の状態ファイルに登録して、今後の変更を Terraform で安全に適用できるようになります。要するに、“新規作成”ではなく“既存リソースの取り込み”です。\n\n使い方の流れは次のとおりです。まず、設定ファイルに取り込みたいリソースのブロックを用意します。例として AWS の場合、resource \"aws_instance\" \"web\" { } の形です。このブロックは後で値を埋めるための“骨組み”だけでOK。次に、取り込みたいリソースの ID を用意します。EC2 の場合はインスタンスID(例: i-0abcd...)などです。\n\nコマンドは次の形式です:terraform import
. 。具体例として、AWS の EC2 インスタンスを取り込むには、terraform import aws_instance.web i-0abcd1234def56789 となります。ここで aws_instance はリソースタイプ、web は設定ファイル内の名前、i-0abcd... が実在するリソースの ID です。\n\n重要な点は、import が行われるのは“状態ファイル”の更新だけで、設定ファイルの属性値を自動で埋めてくれるわけではないということです。取り込んだ後は、terraform plan を実行して現在の設定と実際のリソースの状態にズレがないか確認します。必要に応じて、設定ファイルの属性値を実際の値に合わせて追記・調整します。たとえば、ami や subnet_id などの値を config に正しく記述していく作業です。\n\nまた、取り込みたいリソースのブロックが設定ファイルに無い場合は import の前に追加しておく必要があります。ブロックが無いと Terraform は対象を見つけられず、エラーになります。さらに、モジュールの中のリソースを取り込む場合や複数のリソースをまとめて取り込む場合は、モジュールのアドレスを使うなど特別な書き方が必要になることがあります。\n\n最後に覚えておきたいのは、import は“既存資産を管理下に置く”第一歩であり、継続して Terraform のコードと状態を一致させる作業が大切だということです。 - javascript import とは
- javascript import とは、別のファイルにある機能を自分のファイルに取り込んで使えるようにする仕組みです。Web開発やアプリ開発でコードを整理する際にとても役立ちます。モジュールと呼ばれる部品を作り、それを他のファイルから利用するための命令が import です。使い方の基本は「import ... from ...」という形で、取り込みたい機能をカンマで区切って指定します。まず、取り出す側のファイルで export を使って機能を公開します。たとえば math.js に sum という関数と、デフォルトの計算機を作れば、次のように export します。export function sum(a, b) { return a + b; }export default { multiply(a,b){ return a*b; } }次に、別のファイルでその機能を使うには import 文を使います。例えば:import { sum } from './math.js';import calc from './math.js';// 複数の取り込みを同時に書くこともできますimport calcDefault, { sum } from './math.js';console.log(sum(2, 3));console.log(calcDefault.multiply(4, 5));ブラウザで使う場合は HTML に のように module を指定します。これによりモジュール機能が有効になり、import 文が動作します。Node.js で使う場合は、package.json に "type": "module" を追加するか、ファイル拡張子を .mjs にします。注意点として、import は静的な文なので、ファイルのトップレベルでしか書けません。関数の中や条件分岐の中で直接書くことはできません。動的に読み込みたい場合は import(...) という関数を使い、戻り値として Promise を返します。これを使えば必要なときだけ別ファイルを読み込むことができます。
- java static import とは
- java static import とは、Javaの静的メンバーをクラス名をつけずに使えるようにする仕組みです。『静的インポート』という言葉は英語の static import を日本語にしたものです。たとえば Math クラスの sin や PI をよく使う場面を想像してください。通常は Math.sin(...) や Math.PI と書きますが、static import を使うと import static java.lang.Math.*; のように宣言しておくと、sin(...) や PI をそのまま使えるようになります。これにより式が短く読みやすくなることがあります。以下に具体例を示します。通常の書き方は次の通りです:import java.lang.Math;public class Example { public static void main(String[] args) { double s = Math.sin(Math.PI / 2); }}静的インポートを使うと次のようになります:import static java.lang.Math.*;public class Example { public static void main(String[] args) { double s = sin(PI / 2); }}static import の形には二つの選択肢があります。すべての静的メンバーを取り込む場合は * を使う: import static java.lang.Math.*; これで sin, cos, tan, PI などを直接使えます。特定の静的メンバーだけを取り込みたい場合は、import static java.lang.Math.PI; など個別に指定します。使い方のコツと注意点も覚えておきましょう。良い場面は、特定のファイルで静的メンバーを頻繁に使い、クラス名を毎回書くと読みづらくなるときです。逆に大きなプロジェクトでは、どのクラスのどのメソッドか分かりにくくなる可能性があるため、過度な使用は避けるべきです。テストコードでは JUnit などの静的メソッドをよく使うので、import static org.junit.Assert.*; のように使うと便利です。要は、静的インポートは便利な道具ですが、読みやすさとのバランスを見て使うことが大事です。
- static import とは
- static import とは、Java の機能の一つで、クラスの静的メンバをクラス名をつけずに使えるようにする宣言です。通常は Math.PI や Math.sqrt のように静的メンバを使うとき、クラス名を前につけますが、import static を使うと PI や sqrt のような静的メンバをそのまま書くだけで利用できます。使い方の基本は次のとおりです。使いたい静的メンバを import static で取り込みます。例: import static java.lang.Math.PI; import static java.lang.Math.sqrt; その後はクラス名を省略して、PI や sqrt のように直接使えます。具体的なコード例は以下のとおりです。import static java.lang.Math.PI;import static java.lang.Math.sqrt;public class Example { public static void main(String[] args) { double r = 3; double area = PI * r * r; double root = sqrt(16); System.out.println(area); System.out.println(root); }}この機能を使うと、短く書けて読みやすくなる反面、どの静的メンバがどのクラスのものか分かりにくくなる場合があります。名前の衝突を避ける工夫も必要です。
- dynamic import とは
- dynamic import とは、JavaScript の機能のひとつで、必要になったときだけ別のモジュールを読み込む仕組みのことです。従来の static import はページの読み込み時にすべてのモジュールを読み込むのに対し、dynamic import は実行時にモジュールの読み込みを開始します。これを使うと「コード分割」と呼ばれる技術が実現され、初期の表示を速くしたり、使われる機能だけを後で読み込んだりできます。動作は非常にシンプルで、JavaScript で次のように書きます。// 基本的な使い方import('./math.js') .then(module => { console.log(module.add(2, 3)); }) .catch(err => { console.error('読み込みエラー', err); });// async/await を使う場合async function calc() { const mod = await import('./math.js'); console.log(mod.add(2, 3));}calc();
importの同意語
- 輸入
- 他国から品物を国内に持ち込むこと。貿易・商業の文脈で使われる正式な用語。
- 輸入する
- 外国から国内へ品物を持ち込む動作。動詞として使い、取引や取扱いの文脈で用いられる。
- インポート
- プログラミングやデータ処理で、外部のモジュールやデータを自分の環境に読み込む操作。英語の import のカタカナ表記。
- 導入
- 新しい制度・技術・ツールを自分の組織や環境へ取り入れること。ソフトウェアの文脈でも広く使われる語。
- 取り込み
- データや情報を自分のシステムに取り込むこと。データ処理・BI・ETLなどの場面で使われる名詞的表現。
- 取り込む
- データ・情報を外部から自分の環境へ取り込む動作。
- 取り入れる
- 他の要素を取り入れて自分のものとして使う・採用すること。
- 組み込み
- 部品や機能をシステムの内部に組み込むこと。ソフトウェア開発やハードウェア設計の文脈で使われる語。
- 読み込み
- ファイルやデータをプログラムに読み込む処理。データの取り込みと近い意味で使われることがある。
importの対義語・反対語
- 輸出
- 輸入の対義語。国内へ入れるのではなく、海外へ出すこと。例: 日本は製品を輸出して海外市場を開拓している。
- 出力
- データや情報を外部へ書き出す行為。データを取り込む import の対義語として使われる。例: 集計結果を出力してファイルに保存する。
- エクスポート
- プログラミングやデータ処理での対義語。モジュールやデータを外部へ書き出すこと。例: CSV をエクスポートして他のアプリで開く。
- 無意味
- import の意味の一つである『意味・重要性』に対する対義語。意味がなく、価値が薄いとされる状態。例: その説明は無意味だ。
- 重要性が低い
- import の意味としての重要性の対義語。重要性が低く、価値が薄いと感じられる状態。例: この点は重要性が低いと考えられる。
importの共起語
- export
- 輸出。国外へ物品やデータを送り出すこと。
- module
- モジュール。プログラムを構成する再利用可能な部品。
- library
- ライブラリ。再利用可能なコードの集まり。
- package
- パッケージ。複数のモジュールをまとめた配布単位。
- dependency
- 依存関係。ある機能を動かすために他の部品が必要な関係。
- from
- 前置詞。〜から。プログラミングでは特定のモジュールから要素を取り出すときに使われることが多い。
- as
- 〜として。別名を付けるときに使う語。
- import文
- インポート文。プログラミング言語でモジュールを取り込む命令の表現。
- path
- パス。ファイルやモジュールの場所を示す情報。
- sys
- Python の標準ライブラリの一つ。システム関連の機能を提供。
- pip
- Python のパッケージ管理ツール。
- virtualenv
- 仮想環境。プロジェクトごとに依存関係を分離する仕組み。
- venv
- 仮想環境の略称。
- importlib
- Python のモジュールを動的に読み込むための標準ライブラリ。
- csv
- CSV。カンマ区切り値のテキストデータ形式。
- json
- JSON。データを表現する軽量なデータ交換フォーマット。
- excel
- Excel。Microsoft の表計算ソフトおよびファイル形式。
- xml
- XML。データを階層的に記述するマークアップ言語。
- parquet
- Parquet。列指向のデータフォーマット。
- etl
- ETL。データの抽出・変換・取り込みの処理。
- api
- API。外部機能を呼び出すための窓口。
- data
- データ。情報の集合。
- integration
- 統合。別々の部品やシステムを結びつけること。
- bundler
- バンドラー。複数のファイルを一つにまとめるツール。
- loader
- ローダー。モジュールを読み込む役割を担う部品。
- runtime
- 実行時。プログラムが実際に動作する時点。
- interpreter
- インタプリタ。ソースコードを逐次実行するプログラム。
- compiler
- コンパイラ。高級言語を機械語に変換するプログラム。
- namespace
- 名前空間。識別子の衝突を避けるための識別子の集合。
- alias
- 別名。元の名前とは別の呼び方をすること。
- require
- 要求・必要という意味。特に Node.js などでモジュールを読み込む関数名として使われることもある。
- npm
- Node.js のパッケージ管理ツール。
- yarn
- Node.js の代替パッケージ管理ツール。
- environment
- 環境。実行条件や設定の総稱。
importの関連用語
- import
- 他のファイル・モジュールの機能を自分のコードで使えるように取り込む行為。依存関係を取り込む入口とも言えます。
- import文
- モジュールをどのように取り込むかを指定する、コード中の文法の構造です。
- ESモジュール
- JavaScript の公式なモジュールシステム。export/import を使い、ファイル間で機能を公開・利用します。
- CommonJS
- Node.js などで使われる従来のモジュール形式。require で読み込み、module.exports でエクスポートします。
- モジュール
- 再利用可能なコードのまとまり。関数・変数・クラスなどを1つのファイルやパッケージにまとめたものです。
- ライブラリ
- よく使われる機能を集めた再利用可能なコードの集合体。
- パッケージ
- ライブラリやモジュールのひとまとまり。依存関係を管理する単位として扱われます。
- 依存関係
- あるモジュールが動作するために、別のモジュールが必要になる関係。
- デフォルトエクスポート
- モジュールが主となる機能を1つ公開する形式。import x from 'mod' のように名前を自由に決められます。
- 名前付きエクスポート
- モジュールが複数の機能を個別に公開する形式。import { foo, bar } from 'mod' のように使います。
- エクスポート
- モジュールから他のファイルが使えるよう、機能を公開する行為。
- エイリアス(import alias)
- 取り込んだ名前を別名にして使えるようにすること。import { foo as f } from 'mod' のように書きます。
- 相対インポート
- ./
- ../
- 現在のファイルの位置から相対的に指定してモジュールを取り込む方法。
- 絶対インポート
- モジュール名や絶対パスでモジュールを指定する取り込み方。
- 動的インポート
- 実行時に必要になったときだけモジュールを読み込む手法。
- import()
- 動的インポートを実現する関数/構文。
- サイドエフェクトインポート
- 副作用だけを目的として、エクスポートを使わずにモジュールを読み込むこと。
- ワイルドカードインポート
- モジュールの全エクスポートをまとめて取り込む方法。例: import * as name from 'mod'。
- 名前空間インポート
- モジュール内の全エクスポートを1つの名前空間オブジェクトとして取り込む方法。
- モジュール解決
- モジュールの場所や名前をどう解決して見つけるかのルール。
- パスエイリアス
- 長いパスを短く置換する設定。
- バンドラー
- 複数のモジュールを1つのファイルにまとめ、配布・実行を容易にするツール。
- ローダー
- ファイルを別の形式に変換するプラグイン的機能。バンドル時に使われます。
- トリーシェイキング
- 使われていないエクスポートを自動で削除してコードを小さくする最適化。
- パッケージマネージャー
- 依存関係を管理・インストールする道具。
- npm
- Node.js の標準的なパッケージマネージャー。依存関係のインストールに使います。
- yarn
- npm の代替となるパッケージマネージャー。高速でキャッシュ重視。
- pnpm
- 重複を避けて高速に依存関係を管理するパッケージマネージャー。
- pip
- Python のパッケージマネージャー。
- Go modules
- Go のモジュール管理の仕組み。go.mod で依存関係を管理します。
- import in Java
- Java で他のクラスやパッケージを利用するための宣言。import java.util.List; のように書きます。
- require
- CommonJS でモジュールを読み込む関数。const m = require('mod') のように使います。
- from
- Python で特定の名前だけを取り込むときの構文。from mod import foo のように書きます。
importのおすすめ参考サイト
- importとは・意味・使い方・読み方・例文 - 英ナビ!辞書 英和辞典
- インポートとは?基本的な意味とエクスポートとの違い
- インポートとは? - フレッツ光
- インポート(取り込み)とは?意味を分かりやすく解説
- importとは・意味・使い方・読み方・例文 - 英ナビ!辞書 英和辞典
- IT用語『import』とは?意味や使い方を解説



















