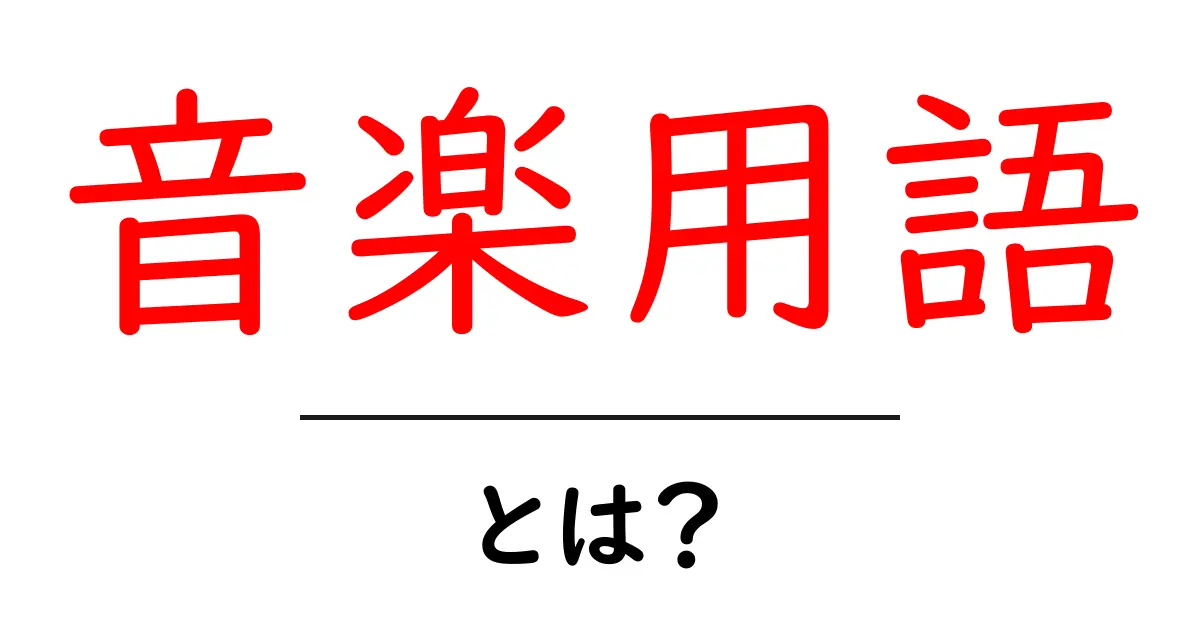

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
音楽用語とは何か
音楽用語とは、音楽を理解したり演奏したりするために使われる専門の言葉のことです。初心者が最初につまずくのは難しい言葉と思われがちですが、実は日常生活の言葉のように少しずつ覚えることができます。ここでは代表的な音楽用語をやさしく解説します。
よく使われる音楽用語の基本
以下の表は、実際の演奏でよく登場する基本的な用語と、その意味、例をまとめたものです。覚えると曲を聴くときや楽譜を読むときに役立ちます。
この表を基準に、曲を聴くときや楽譜を読むときの目安を作ると、音楽の理解が深まります。次に、実際の練習でどう活かすかを紹介します。
実践的な練習のコツ
まずは身近な曲を選び、楽譜に出てくる用語を1つずつ拾います。音階は鍵盤やギターの指板で確認し、和音は和音進行という連続を意識します。メロディを追いながら、リズムとテンポの関係を体で感じてください。ダイナミクスは曲の場面を想像しながら、弱いところを少しずつ大きく打鍵する練習をします。
聴くときのコツ
音楽を聴くときは、まず全体の雰囲気を感じ、その後に用語がどう使われているかを探ります。主旋律がはっきりしているか、和音が転調していないかなど、聞くポイントを決めると理解が深まります。
音楽用語は、始めは少し難しく感じますが、毎日の練習で少しずつ覚えていくと楽しくなります。難しい語の意味を一度に覚えるのではなく、曲ごとに出会うたびに新しい言葉を取り入れていくのがコツです。
よく使われる表現のまとめ
基本:音階、和音、メロディ、リズム、テンポ、ダイナミクス、アーティキュレーションを覚えることから始めましょう。
最後に、音楽用語を覚える段階的な学習計画の1つの例を示します。最初の週は音階と和音の基礎を固め、2週目はメロディとリズムに焦点を当て、3週目はダイナミクスとアーティキュレーションを練習します。4週目には実際の曲を聴きながら総合的な演習を行います。毎日15分程度の短い練習を続けると、語彙が自然と身につきます。
音楽用語の関連サジェスト解説
- 音楽用語 フェイク とは
- 音楽用語としてのフェイクは、正式な楽譜に書かれている音符をそのまま再現するのではなく、演奏者がその場の状況や表現したいニュアンスに合わせて別の音やリズムを当てる“代用的な演奏”を指すことが多いです。日本語の日常会話での“偽物”の意味とは異なり、音楽の場面では技術的・表現的な行為として使われることが多く、必ずしも悪い意味ではありません。特にジャズやボーカル・アカペラの現場では、オリジナルのメロディを完全には再現するのが目的ではなく、コード進行や歌詞の意味を伝えるために、即興的に音を足したり省いたりすることがあります。この場合、『フェイクをする』とは“その場で新しい音を当てて、メロディの形を少し変える”という意味に近いです。例を挙げると、ジャズのセッションでは、テーマのメロディを完全には再現せず、コードの響きを活かしてスケールの音を使いながらメインのラインを“フェイク”することがあります。演奏者は耳で相手の音を聴き、リズムを崩さずに違う音を入れる技術を磨きます。アカペラや合唱では、パート同士のハーモニーを保ちながら、歌い方を少し崩してニュアンスを表現するためにフェイク的な発声を使うことがあります。音の高さが難しい場面では、原曲の音を守ることよりも、感情や雰囲気を伝えることを優先する場合があるのです。とはいえ、フェイクは正式な楽語ではなく、学習教材や公式な曲の解説では“即興・代用音・表現の工夫”といった言い方で説明されることが多いです。そのため、初心者が学ぶときには“フェイク”という単語だけで意味を決めず、文脈を確認しましょう。代替語として“即興(improvisation)”や“代用音・代替音階”“ニュアンスを広げる表現”などを用いると伝わりやすいです。最後に、フェイクの技術を身につけるには、耳を鍛え、コードを理解し、メロディのどの音が崩せるのかを経験的に学ぶことが大切です。
- 音楽用語 div.とは
- 音楽用語 div.とは、楽譜に現れる 'div.' の略で、divisi(ディヴィジ)を指します。これは、セクションを2つ以上のパートに分けて同時に異なる音を演奏させる指示です。特に弦楽器のセクションや管楽器の大きなセクションでよく使われます。楽譜には 'Div. I'、'Div. II' などと表示され、音の分かれ方を示すことがあります。音符の並びが複数の声部になるため、同じ楽器でも別々の旋律を演奏します。Div. の指示が出ると、該当セクションのプレイヤーは二つ以上のグループに分かれ、上のグループと下のグループが別々の旋律を演奏します。全員で同じ音を出すユニゾンと違い、ハーモニーや複雑なリズムを作るのに役立ちます。例えば第1ヴァイオリンが高い旋律を Div. I が、低い旋律を Div. II が担当することがあります。時には、後半で再び一つの旋律に戻る unison に合流します。Div. の意味を理解するには、楽譜の指示だけでなく指揮者の合図にも耳を澄ませることが大切です。練習では、どの音が誰の担当かを確かめ、指揮者の指示に従って分割と合流を切り替える練習をします。音楽の厚みが増すこの技法は、オーケストラや合唱の勉強にも役立ちます。
- 音楽用語 トラック とは
- 音楽用語の中で「トラック」という言葉には、場面によって意味が少し違います。この記事では初心者にも分かるように、音楽制作とアルバムの二つの意味をやさしく解説します。まず、DAWという音楽制作ソフトの中での「トラック」は、音を録音したり再生したりするためのレーンのことです。1つのトラックには音声データ(歌や楽器の音)やMIDIデータ(音の指示情報)を入れることができます。複数のトラックを縦に重ねると、曲の音が立体的になります。トラックを使うと、録音したパートを別々に調整できます。ボーカルトラックの音量を上げたり、ギタートラックにはリバーブをかけたり、ドラムトラックにはパンニングを調整したりします。これをミックスと呼び、最終的にステレオの曲として完成させます。一方、アルバムの「トラック」は、アルバムに収録されている曲そのものを指します。CDや配信で並ぶ曲には番号が付き、トラック1、トラック2のように呼ばれます。つまり「トラック」は制作上の音の線と、アルバム内の曲の両方の意味を持つ、文脈で使い分ける言葉です。初心者が覚えるポイントはシンプルです。1つのトラックは1つの音源を表すことが多いです。録音した音を別のトラックに分けると、音作りや編集がしやすくなります。曲全体を指す場合はアルバムの各曲を指します。DAWを使い始めたら、まずはボーカル用のトラックと楽器用のトラックを用意して、音量バランスと基本的なエフェクトの扱いを練習してみましょう。
- 音楽用語 おかず とは
- この記事では、検索キーワード「音楽用語 おかず とは」について、初心者にも分かるように解説します。まず結論として、この語句は音楽の正式な用語としては一般的ではありません。普通は「音楽用語」という大きなカテゴリと、個々の用語が並びます。ところで「おかず」という語は日常語で、主にご飯のお供にする料理のことを指します。ネットの検索では、食べ物の話と混同して“おかず”という言葉が出てくることもあり、音楽の話題と一緒に表示されることがありますが、音楽の理論を説明する語としては使われません。次に、音楽用語の代表的なカテゴリーを紹介します:テンポ(速さ)、拍子(リズムの組み方)、音量の表現(フォルテ、ピアノなど)、ダイナミクス、音色、和音、転調、レジスター、アーティキュレーション(スタッカート、レガート)、音楽形式(ソナタ形式、リフレイン)など。これらは教科書や楽典で頻繁に出てくる言葉です。もし「とは」という語をネットで検索したいなら、「音楽用語とは何か」「音楽用語の基本的な意味」といった形で調べると理解が深まります。さらに、なぜ「音楽用語 おかず とは」という検索が現れるのかを考えると、次のようなケースが挙げられます。1) キーワードの打ち間違いや入力ミス。2) 面白く読ませる狙いで、SEO対策としてわざと変わった語を混ぜている場合。3) 「おかず」という語を使って、音楽の“サブ的な話題”を連想させようとしているケース。いずれにせよ、正式な音楽用語を覚えたいなら、まずは上記の基本用語を押さえるのがおすすめです。最後に、初心者向けの勉強のコツです。楽譜を読めるようになるには、まずはテンポと拍子を理解するのが最初の一歩。次にダイナミクスとアーティキュレーションを覚えます。音階やコードの名前を知ると、耳で聴いた音の正体がわかりやすくなります。音楽は言葉と同じく意味を持つ“表現の道具”ですから、少しずつ用語を増やしていくと、演奏にも文章にも深みが生まれます。
- 音楽用語 ds とは
- 音楽用語 ds とは、楽譜の指示のひとつです。DS は Dal Segno の略で、日本語にすると「記号から戻る」という意味になります。曲の途中でもう一度演奏したいときに使われ、楽譜には Segno(セグノ)と呼ばれる特別な記号が現れます。DS の指示を見つけたら、演奏者は Segno の場所へ戻り、そこから再び曲を進めます。D.S. のあとに続く文字列として、D.S. al Fine、D.S. al Coda などがあります。D.S. al Fine は「記号から戻って Fine まで演奏する」という意味です。Fine は楽譜の終わりの手前にある区切りです。D.S. al Coda は「Coda(終結部)へ飛ぶ」という指示で、Segno へ戻った後、Coda 記号の場所へ進み、曲を終えます。Coda とは別の終結部を指す特別なパートのことです。DS は長い曲の中でリフやテーマを繰り返して聴かせたいときに便利です。初めのうちは難しく感じるかもしれませんが、実際には戻る場所と進む場所を読むだけのシンプルなルールです。楽譜を読んで「この記号を見つけて、次はここへ戻る」ということを意識すると、練習のときにも混乱しにくくなります。
- 音楽用語 pa とは
- 音楽用語 pa とは、直感的には難しく感じる言葉ですが、実は必ずしも広く普及している標準用語ではありません。 pa は楽譜の中で現れることがありますが、それは作曲者や版元が独自に使う略語、あるいは特定のフレーズを短く指し示すものとして書かれている場合が多いです。そのため、 pa に出会ったときは周囲の文脈や楽譜の先頭にある凡例を確認することが大切です。まず考えられる意味は poco a poco の略語としての用法です。 poco a poco はイタリア語で『少しずつ』という意味で、演奏の勢いを急に変えずに徐々に調子を整えるときに使われます。楽譜の中で p.a. のように小さく書かれている場合、これを示している可能性があります。ただし、 pa が必ずしも poco a poco を指すとは限らないので、他の手掛かりを探しましょう。次に、 pa が特定の出版社・著者の独自略語であることもあります。大学の課題曲や学校の教材、または特定の地域の楽譜には pa が別の意味で使われていることがあります。例えば『piano a tempo』の省略と受け取れることもありますが、これは一般的な表記ではありません。実際には pa の意味を確定するには、楽譜の前書きの凡例を確認するのが一番確実です。音楽を学ぶうえでの対処法としては、以下の点を覚えておくとよいです。 pa を見つけたら周囲の動的記号や拍の進行と照らして意味を推測する。 可能なら版元の解説や原譜の注釈を読む。 不明な場合は指導者や同じ曲の他の版を参照する。 オンラインで検索する際は、曲名と『pa とは』『poco a poco』などの語を併せて調べる。 日常の演奏では pa の考え方を一つのヒントとして取り入れ、無理に確定的な意味にこだわらず、音楽全体の流れを意識して演奏するのが良いでしょう。 pa の用語が出てきても、全体の雰囲気・テンポ・曲の目的を踏まえれば、自然に解釈できるはずです。
- 音楽用語 レガート とは
- 音楽用語 レガート とは、音と音の間をはっきり切らずに、音をつないで演奏する表現のことです。鍵盤楽器や声楽、管楽器、弦楽器など、さまざまな楽器で使われます。楽譜上では、ノートの上にスラーと呼ばれる弧が引かれていることが多く、この記号は「このノートを滑らかにつなげて演奏して」という指示になります。実際には、弾き始めの力を一定に保ち、音の終わりを次の音へ自然に引き継ぐことが大切です。弦楽器では、一本の弓で連続して音を出し続けることでレガートを作りますが、音と音の間に力みが入ると途切れた感じになります。ピアノやサックス、ギターなどでは、指の運びと適切なペダル操作でつなぎを作ることが多いです。ポルタート(半分スタッカートのような軽い切り方)と組み合わせて使う場合もあり、曲の表現意図に合わせて変化させます。聴き方のポイントは、音の長さや音量を均一に保ち、呼吸のように自然な流れを意識することです。練習方法としては、スケールをゆっくりしたテンポで、各音を同じ間隔・同じ音色でつなぐ練習を繰り返します。初めはスラーを使わず、音を個別に出す練習をしてから、徐々にスラーをつけて滑らかさを増やしていくと良いでしょう。楽譜上のポイントは、スラーの他にも楽句の区切りを示すフレーズ記号があり、時には意味が異なる場合があるので、曲の指示をよく読み分けることが大切です。レガートを身につけると、曲全体の流れが美しくなり、聴いている人に音楽の意図を伝えやすくなります。初心者は焦らず、ゆっくりしたテンポで正確さを優先して練習するとよいでしょう。
- リフ 音楽用語 とは
- リフとは音楽で繰り返し登場する短いフレーズのことです。ギターやシンセサイザーで演奏され、曲の特徴や印象を決める重要な要素になります。リフはメロディの一部として登場することが多く、聴いた人が思わず口ずさんだり頭の中で覚えたりします。リフはジャンルを問わず使われ、ロックのギターリフ、ポップのリズミックなフレーズ、ファンクやジャズのリズム的なパターンなど、いろいろな形があります。音楽用語としてのリフは、繰り返される短いフレーズを指すことが多く、曲全体の雰囲気を作る核となる要素として機能します。作り方のコツとしては、3~4音程度の短い組み合わせから始め、それをリズムよく繰り返すと聴き心地がよくなります。コード進行がシンプルでも、リフのリズムや音の並べ方を工夫するだけで力強い印象を作れます。リフはボーカルラインと別に存在することが多く、曲の核として聴衆の記憶に残る役割を果たします。初心者はまず耳コピでリフ部分を再現する練習をすると良いでしょう。音を同じ音で長く出す練習から始め、徐々に指の位置を変えたりリズムを変化させたりすると、リフの表現力が広がります。リフは前奏やサビへつながる橋渡しとしても働くことが多いので、曲の構成を理解する手がかりにもなります。
- アウトロ とは 音楽用語
- アウトロ とは 音楽用語とは、曲の終わりに現れるセクションのことで、曲の締めくくりを作る役割を持ちます。英語の outro から来た外来語で、日本語では「終曲」や「終章」に近い意味ですが、ジャンルによって形はさまざまです。イントロが曲の入り口を作るのに対して、アウトロは聴き手に余韻を残し作品を一区切りつける役割を担います。ポップスやロック、ジャズ、映画音楽など、幅広いジャンルで使われ、終止感を強く出す方法や、穏やかにフェードアウトして曲を閉じる方法など、さまざまな表現が存在します。アウトロとコーダ(coda)の違いを知っておくと、曲全体の構成を理解しやすくなります。コーダは楽曲の正式な終結点を指す場合が多いのに対し、アウトロは自由度が高く、雰囲気作りを目的とした終わり方を指すことが多いのです。アウトロを作るときは、曲のテーマのモチーフを少しだけ再現したり、和声を変化させて終止へ導いたりします。具体的な手法としては、最後に主和音で締める、終盤のダイナミクスを抑えて穏やかに終える、同じフレーズを繰り返して聴衆の印象を引き継ぐ、あるいはフェードアウトで音量を徐々に下げるなどがあります。中学生にもわかるポイントとして、アウトロは「終わり」を強く意識させる部分だと覚えると良いでしょう。日常の音楽づくりでも、最後の一音で聴き手の心に余韻を残すよう心がけると、作品全体の完成度が高まります。
音楽用語の同意語
- 楽語
- 音楽で使われる専門的な語彙の総称。特に演奏指示や表現を示す語で、イタリア語由来の用語が多いです。
- 音楽語彙
- 音楽で用いられる語彙や語句の総称。音楽用語とほぼ同義ですが、語彙としての広い意味を含むこともあります。
- 音楽用語集
- 音楽に関する用語を整理した辞典・リスト・教材のこと。初心者が用語を調べる際に役立つ資料です。
- 楽譜用語
- 楽譜に記される指示・表現を指す語彙。テンポ・強弱・演奏指示・記号などを含みます。
- 音楽専門用語
- 音楽分野で使われる専門的な語彙の総称。音楽理論・演奏・作曲などの用語を含みます。
- 音楽表現用語
- 音楽の表現やニュアンスを示す語彙。色彩・ニュアンス・感情の指示を含みます。
- 音楽理論用語
- 和声・旋律・リズム・拍子など、音楽理論を説明するための語彙です。
- テンポ用語
- 楽曲の速さを指示する語。例: allegro、andante、adagio など、速度を示す用語の総称です。
- ダイナミクス用語
- 音量の変化を表す語。p、f、crescendo、diminuendo などが含まれます。
- 演奏記号
- 演奏時の技法・表現を指示する符号・語。スタッカート、アタック、ブレスなどを含みます。
- 記譜用語
- 楽譜上の指示に使われる語彙。テンポ・拍子・演奏指示などを含みます。
- 音楽語彙集
- 音楽用語をまとめた語彙集・辞典のこと。初心者向けの学習資料として活用できます。
音楽用語の対義語・反対語
- 日常語
- 音楽の専門用語ではなく、日常生活で普通に使われる言葉。楽譜の記号や演奏指示の意味を持たない、一般的な語彙です。
- 非音楽用語
- 音楽以外の分野で使われる語彙。例えば科学・技術・文学など、音楽に直接関係しない用語の総称。
- 一般語彙
- 特定の分野に偏らず、広く使われる基本的な語彙。音楽用語の専門性とは対照的です。
- 専門用語(音楽以外の分野)
- 音楽以外の分野で用いられる専門的な語彙。医療・物理・経済など、音楽の用語とは別の領域の用語。
- 科学・技術用語
- 科学・技術の分野で使われる専門語。音楽用語とは異なる学術・技術的語彙。
- 文学・文章用語
- 文学・文章表現に用いられる語彙・表現。音楽用語とは別の語彙体系。
- 方言・俗語
- 地域の方言や日常的な俗語・スラング。公式な音楽用語とは異なる言葉遣い。
- 非専門的表現
- 専門性を抑えた、日常的・平易な表現。音楽用語の専門性の対極となる語彙です。
音楽用語の共起語
- テンポ
- 楽曲の速さを示す概念。速いほどテンポが速く、遅いほど遅く感じます。
- 速度記号
- 楽曲の速さを具体的に指示する表現。LargoやAllegroなどの言葉や、楽譜上の記号で示されます。
- アレグロ
- 快活でやや速いテンポを意味する代表的なテンポ指示。
- アダージョ
- ゆっくりと落ち着いたテンポを指す表現。情感豊かな場面で使われます。
- アンダンテ
- 「歩く速さ」で、穏やかで中くらいのテンポを意味します。
- モデラート
- 中庸な速さのテンポを示す指示。
- ラルゴ
- とてもゆっくりとしたテンポを表す語。
- ヴィヴァーチェ
- やや速く活発なテンポを示す表現。
- プレスト
- 非常に速いテンポを意味します。
- プレストissimo
- 極めて速いテンポを表す強調形。
- リタルダンド
- 徐々に遅くなる指示。
- リタルタンド
- 徐々に遅くなる表現の別表記。
- アチェレランド
- 徐々に速くなる指示(Accelerandoの表記ゆれ)。
- アクセラレンド
- 徐々に速くなる指示。上昇感を作る効果があります。
- クレシェンド
- 音量を徐々に大きくしていく動的指示。
- ディミヌエンド
- 音量を徐々に小さくしていく動的指示。
- デクレシェンド
- 徐々に音量を下げる表現。弱く終わる場面で使われます。
- フォルテ
- 大きな音量、力強い演奏を指す表現。
- フォルテッシモ
- 極めて大きな音量で演奏する指示。
- フォルティッシモ
- 強く・大きく演奏する強めの指示。
- メゾフォルテ
- 中くらいの強さで演奏する表現。
- ピアノ
- 小さな音量で静かに演奏する指示。
- メゾピアノ
- 中くらいの音量で演奏する指示。
- ピアニッシモ
- 非常に弱く、かすかな音量で演奏する指示。
- スタッカート
- 音を短くはっきり切って演奏するアーティキュレーション。
- レガート
- 音と音を滑らかにつなげて演奏するアーティキュレーション。
- スラー
- 複数の音を滑らかにつなぐ連結の表記。
- アーティキュレーション
- 音の出し方の指示全般。スタッカートやレガートなどを含みます。
- アクセント
- 強く打つ・際立たせる演奏表現。
- -tenuto
- 音を十分な長さで、ほぼ均等に保って演奏する指示。
- トレモロ
- 弦楽器などで急速な指の振動や連続した音を作る技法。
- トリル
- 短音と長音を素早く交互に奏でる装飾音の一種。
- グリッサンド
- 音を滑らせて連続的に移動する技法。
- モルデント
- 音を一瞬だけ下げて戻す短い装飾音。
- グリーチョ
- 装飾音の一種。高低を素早く変化させる演奏表現。
- アルペジオ
- 和音を1音ずつ順番に奏でる技法。
- arco
- 弓楽器で弓を弦に当てて演奏する指示(弓で演奏)。
- pizzicato
- 弦楽器を弦を弾くように奏でる演奏法。
- col legno
- 木部(楽器の木部)で弦を打つ演奏法。
- glissando
- 音を滑らせて連続的に移動する技法。
- mordent
- 装飾音として短く挟む音の反復。
- turn
- 短い装飾音のパターンの一つ。
- 音符
- 楽譜上の音の記号。音の高さと長さを表します。
- 休符
- 音を出さず休む時間の記号。
- 全音符
- 長さが4拍分の音符。
- 二分音符
- 2拍分の音符。
- 四分音符
- 1拍分の基本的な音符。
- 八分音符
- 0.5拍分の音符。
- 十六分音符
- 0.25拍分の音符。
- 臨時記号
- 楽譜上で臨時に音を変える記号。シャープ、フラット、ナチュラルなど。
- シャープ
- 半音高くする臨時記号。
- フラット
- 半音低くする臨時記号。
- ナチュラル
- シャープとフラットを打ち消して元の音高に戻す記号。
- ダブルシャープ
- 半音よりさらに高くする記号。
- ダブルフラット
- 半音よりさらに低くする記号。
- 調号
- 楽譜の冒頭に書かれたキーを示す記号群(#や♭の集合)。
- 長調
- 明るく安定した調性を持つ音階・和声の性質。
- 短調
- 哀愁や暗さを感じさせる調性の性質。
- 転調
- 別の調に移ること。
- 和聲
- 音と和音の組み合わせによる音楽理論の分野。
- コード
- 和音の組み合わせを示す記号や響き。
- 和音
- 同時に鳴る複数の音の組み合わせ。
- トニック
- 楽曲の基礎となる主音・主和音。
- ドミナント
- 和声的に強い響きを作る第5音系の和音。
- サブドミナント
- ドミナントの前に来る和音群の機能を果たす和音。
- 転調進行
- ある調から別の調へ移る和声の進行。
- 終止
- 音楽の一区切りを作る和声的な結び。
- カデンツ
- 終止形の総称。完全終止、半終止など。
- 対位法
- 複数の独立した旋律が重なる作曲法。
- モチーフ
- 楽曲の最小単位となる旋律の断片。
- テーマ
- 楽曲の主題となる旋律・動機。
- 動機
- テーマの短い断片、発展していく細部。
- 旋律
- 音の連なりによるメロディ。
- 音階
- 一定の音の並び方(スケール)。
- 長音階
- 長調に使われる音階。
- 短音階
- 短調に使われる音階。
- 全音階
- 全音だけで構成される音階。
- 半音階
- 半音ずつ連なる音階。
- 階名
- ソ・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シのような音の名。
- ソルフェージュ
- 音階を歌って音感を鍛える訓練法。
- ドレミファソラシ
- 日本語での音名表記(ドレミファソラシ)。
- solfege
- ソルフェージュの別表記・英語圏での表現。
- 楽譜
- 音楽を記した紙やデータ。演奏の指針となる。
- 五線譜
- 音楽記譜の基本となる五つの横線の楽譜。
- 譜表
- 楽譜で音高を示す記号。ト書きや記譜要素。
- 拍子
- 楽曲の拍の組み方。4/4、3/4などが代表的。
- 4/4
- 4拍子の代表的な拍子。
- 3/4
- 3拍子の代表的な拍子。
- 2/4
- 2拍子の代表的な拍子。
- 変拍子
- 小節ごとの拍子が変化するリズム構造。
- 拍感
- 拍の感じ方や体感。リズム感の表現。
- 楽器編成
- 演奏に使われる楽器の組み合わせ。
- 弦楽器
- バイオリン・ビオラ・チェロ・コントラバスなどの弦楽器。
- 管楽器
- フルート・オーボエ・クラリネット・ホルンなどの管楽器。
- 打楽器
- ドラムやティンパニなど打楽器全般。
- 鍵盤楽器
- ピアノ、オルガンなどの鍵盤楽器。
- 音色
- 楽器や演奏の音の特徴(色・色彩)を指す語。
- 音質
- 音の品質や色の違いを表現する語。
- 編成
- 楽曲全体の楽器構成・人数。
- オーケストレーション
- 楽曲を楽器ごとにどう配置するかという技法・設計。
- アンサンブル
- 複数の楽器・声が合奏する演奏形態。
音楽用語の関連用語
- 音階
- 音の高さが階段状に並んだ音の集合。長音階(メジャースケール)・短音階(マイナースケール)などがある。
- 調号
- 楽曲の調を示す記号。シャープやフラットの数で決まり、どの音を半音上げ下げするかを決定する。
- 長音階(メジャースケール)
- 基本的な明るい響きの音階。全-全-半-全-全-全-半の音ステップ配列。
- 短音階(マイナースケール)
- 暗い響きを持つ音階。自然短音階は全-半-全-全-半-全-全の配列。
- 自然短音階
- 短音階の基本形。第7音を下げた構成で、暗い響きを生む。
- 和声的短音階
- 自然短音階に第7音を半音高くして和声音を取りやすくした音階。
- 音名
- 音の名前。英語名のA,B,C,D,E,F,Gや、日本語のドレミファソラシなどがある。
- ドレミファソラシ(ソルフェージュ)
- 音名を階名で呼ぶ方法。歌唱訓練にも使われる。
- 半音
- 隣接する二音の高さ差の最小単位。西洋音楽の最小距離。
- 全音
- 二つの半音分の距離。音階でWと表されることが多い。
- オクターブ
- 同じ名前の音が高さを1オクターブ上か下に離れた音域。
- 音符
- 音の長さと高さを表す記号。拍の長さを決める。
- 全音符
- 4拍分の長さの音符。
- 二分音符
- 2拍分の長さの音符。
- 四分音符
- 1拍分の長さの音符。
- 八分音符
- 0.5拍分の音符。
- 十六分音符
- 0.25拍分の音符。
- 付点音符
- 音の長さを点の分だけ伸ばす記号。
- 休符
- 音を出さない時間を示す記号。
- 全休符
- その小節の全声部が休みになる長さ。
- 拍子
- 拍の数と区切り方を示す。4/4・3/4などが一般的。
- 四分の四拍子(4/4)
- 最も一般的な拍子。1小節に4拍、強弱のリズムパターンがある。
- 三拍子(3/4)
- 3拍で1小節を構成する拍子。
- 変拍子
- 通常とは異なる、複雑な拍子。例: 5/4、7/8など。
- テンポ
- 曲の速さの指示。速さは演奏の雰囲気を決める。
- アンダンテ
- 歩くくらいの速さで演奏するテンポの表記。
- アレグロ
- 快活で速いテンポ。
- アダージョ
- 遅めの落ち着いたテンポ。
- プレスト
- 非常に速いテンポ。
- ラルゴ
- 非常にゆっくりとしたテンポ。
- リタルダンド
- 徐々に遅くする指示。
- アッチェレランド
- 徐々に速くする指示。
- ア・テンポ
- 元の速さに戻す指示。
- ダイナミクス
- 音の強弱の表現。ダイナミクス記号で示す。
- ピアノ(p)
- 弱く演奏する指示。
- フォルティッシモ(ff)
- とても強く演奏する指示。
- ピアニッシモ(pp)
- とても弱く演奏する指示。
- メゾフォルテ(mf)
- 中くらいの強さで演奏。
- メゾピアノ(mp)
- 中くらいの弱さで演奏。
- クレシェンド
- 徐々に音量を上げる。
- ディミヌエンド
- 徐々に音量を下げる。
- スフォルツァンド
- 特定の音を強く瞬間的に強調する。
- アクセント
- 特定の音を強く打つ、強い強勢。
- レガート
- 音と音を滑らかにつなぐ演奏法。
- スタッカート
- 音を短くはっきり切る演奏法。
- テヌート
- 音の長さをわずかに保つ(長めに持つ)。
- スラー
- 隣接する音を滑らかに結ぶ曲線記号。
- 連符
- 同じ音を連結させて演奏する記号/装飾。
- アーティキュレーション
- 音の出し方の指示。キレのある、滑らかなどの表現を決める。
- 音色
- 音の色、楽器特有の響き。ティンバーとも呼ばれる。
- アルペジオ
- 和音の構成音を順番に鳴らして演奏する方法。
- コード
- 和音の組み合わせ。音を同時に鳴らして和声を作る。
- メジャーコード
- 明るい響きの和音。
- マイナーコード
- 暗い響きの和音。
- セブンスコード
- 七度の音を含む和音で、和声音楽でよく使われる。
- 増三和音
- 三和音の中で三度間隔を増やした和音。
- 減三和音
- 三度間隔が狭くなる不安定な和音。
- コード進行
- 和音の並び順や変化の流れ。曲の骨格を作る。
- 和声
- 同時に鳴らす音との関係、和音の進行。
- 対位法
- 複数の旋律を独立して同時に進行させる作曲技法。
- モード
- 伝統的な音階体系。イオニアン、ドリアンなどがある。
- 音楽形式
- 楽曲の構造・形式(例: ソナタ形式、変奏曲、カノンなど)。
- 編成
- 楽曲に含まれる楽器編成の組み合わせ。室内楽・オーケストラなど。
- 楽器編成
- 使用する楽器の組み合わせ。
- 調律
- 音を正確な高さに合わせる作業。
- 音域
- 楽器や声が出せる音の高さの範囲。
- トリル
- 短い高低音の速い連続装飾音。
- グリッサンド
- 音と音の間を滑らかに滑らせて移動する装飾。
- フェルマータ
- 音符の長さを延長する記号。演奏者の自由度が生まれる。
- 装飾音
- 主旋律に付く短い音符や装飾の音。
- 反復記号
- 同じ部分を繰り返す譜面の記号。
- D.C. al Fine
- 頭へ戻ってFineまで演奏する指示。
- D.S. al Coda
- D.S.の指示の後、Codaへ進んで演奏する指示。
- 主題と変奏
- 一つの主題をさまざまに変化させて展開する形式。



















