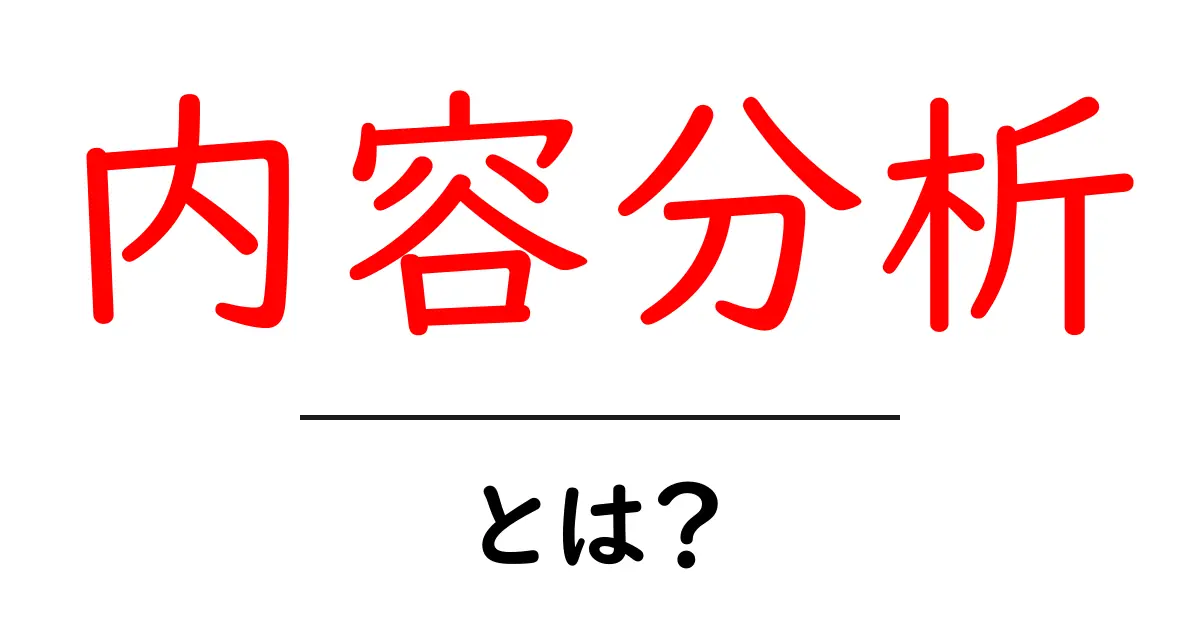

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに 内容分析とは?
内容分析とは、言葉や文章、画像など、私たちが情報として受け取る「内容」を整理して意味を読み解く方法のことです。目的を決めてデータを分析することで、どんな傾向があるのか、どんな意図があるのか、そして人々が何を伝えたいのかを明確にします。内容分析は研究やマーケティング、教育など幅広い場面で使われます。
内容分析の基本的な考え方
内容分析は「観察と分類」を基本にします。大量のテキストや映像をそのまま見るのではなく、共通のテーマやカテゴリーを作って、それに沿ってデータを分類します。すると、数字で表しにくい表現の意味や傾向を、整理されたデータとして見ることができます。
どんな場面で使われるのか
学校の課題では、つけられた評価の理由を探すとき、インターネットのコメントを分析して世間の意見を把握するとき、広告の反応を調べるときなどに使われます。例えば、ある商品についての口コミを集めて、良い点と悪い点を分けて整理することで、今後の改善点が見つかります。
内容分析の5つのステップ
以下の表は、初心者が押さえるべき基本的な流れです。
重要なポイントは、分析の過程で「偏りを減らす工夫」をすることです。たとえば、同じデータを複数の人が別々にコード化してみると、見落としや主観的な判断を減らせます。
具体例で学ぼう
例として、ある商品へのオンラインコメントを対象にします。まず目的として「使いやすさと満足度を知る」ことを設定します。データとして、100件のコメントを収集します。次にコードを作成します。「使いやすさ」「デザイン」「価格」「サポート」のようなカテゴリを設定します。それぞれのコメントを対応するカテゴリに分類します。最後に、各カテゴリの頻度を数え、どの点が高く評価され、どの点が改善の余地が大きいかを報告します。
ツールと注意点
初めは手作業でも大丈夫です。Excelやメモ帳を使ってデータを整理しましょう。分析が進んできたら、NVivoやAtlas.tiといった専門ソフトを使うと効率が上がります。ただし、ツールに頼りすぎず、データの意味を読み解く力を忘れないことが大切です。
よくある誤解と正しい理解
「内容分析は数字だけの作業だ」という誤解があります。しかし実際には、観察力と解釈力が重要です。また、分析は一度で完結するものではなく、反復して改善していくものです。
小さな練習問題
自分で簡単なデータを用意し、5つ程度の短い文章を分析してみましょう。まず目的を決め、データを読み取り、コードを作成し、結果を解釈します。練習を重ねるほど、内容分析のコツがつかめていきます。
まとめ
内容分析・とは?という問いに対して、データを整理し、意味を読み解くための基本的な方法だと理解すると良いでしょう。学問だけでなく、日常の情報判断にも役立つ強力な手法です。コツを覚え、練習を積めば、誰でも信頼できる分析ができるようになります。
内容分析の同意語
- コンテンツ分析
- ウェブサイトや文書の中身(コンテンツ)を対象に、質・量・構成・読みやすさなどを評価・整理する手法。
- コンテンツ解析
- コンテンツ分析の別表現。内容を分解して意味・特徴・影響を把握する作業。
- コンテンツ中身分析
- コンテンツの中身そのものを分析し、情報の網羅性や要点の伝わりやすさを評価する作業。
- 内容の分析
- 含まれる情報や要素を分解して、意味・構造・適切さを検討する分析活動。
- 記事分析
- 記事全体の構成や文体、要点の伝わりやすさを系統的に評価する分析作業。
- 記事内容分析
- 記事の中身(情報の正確さ・網羅性・読者への伝達力)を分析する手法。
- 本文分析
- 本文の文章構造や用語、読みやすさ、説得力などを評価する分析。
- テキスト分析
- テキストデータを対象に語彙・文体・情報の配置などを分析する手法。
- 文章分析
- 文章全体の表現・構造・意味伝達を検討する分析活動。
- テキストマイニング
- 大量の本文テキストから重要語句やパターンを抽出して情報を整理する手法。
- テキストデータ分析
- テキストとして扱えるデータを分析し、特徴や傾向を把握する作業。
- 情報分析
- 情報の性質や構造、伝達効果を評価・理解するための分析活動(内容分析の広義の一つとして適用可能)。
内容分析の対義語・反対語
- 表面的な分析
- 内容の核となる意味や構成を深掘りせず、表面的な特徴だけを見て評価する分析のこと。
- 形式的な分析
- 内容そのものの意味を分析するのではなく、文体・構成・表現形式に焦点を当てる分析。
- 直感的な分析
- データに基づく検証よりも直感や感覚で判断する分析。
- 推測的な分析
- 十分な根拠がないまま推測で結論を出す分析。
- 抽象的な分析
- 具体的な内容より概念や理論的枠組みを優先して解釈する分析。
- 外部要因分析
- 内容そのものではなく、外部の市場・文脈・トレンドなど外因に着目する分析。
- 全体像・俯瞰的分析
- 個々の要素の意味を詳しくコード化せず、全体の印象や総括に依る分析。
- 非定量的・非構造化分析
- 数値化・体系化されたコード化を避け、自由回答や個人の解釈に頼る分析。
- 感情・価値判断重視の解釈
- データの根拠より、感情や価値判断を中心に解釈する分析。
- 結論優先の分析
- 結論を先に出してしまい、根拠の検証や反証を後回しにする分析。
- テキスト以外の素材分析を重視
- 映像・音声などテキスト以外の素材を優先して分析する傾向がある内容分析の対極。
- 理論的・哲学的分析
- 実務的な内容の読み解きより、理論や哲学的枠組みに基づく解釈を重視する分析。
内容分析の共起語
- コンテンツ分析
- 内容分析の同義・別称として用いられる。ウェブ・紙媒体を問わず、コンテンツのテーマや構成、品質を評価・整理する分析手法です。
- テキスト分析
- 文章データを対象に、語の出現頻度や意味関係を整理する分析。
- テキストマイニング
- 大量のテキストデータから頻度・共起・トピックなど有用な情報を機械的に抽出する手法。
- 形態素解析
- 日本語のテキストを語(形態素)に分割し、基本形・品詞を割り当てる処理。
- 品詞分析
- 形態素解析の結果を品詞ごとに整理・分析する作業。
- コード化
- テキストをカテゴリ・テーマ・コードに分類し、定量的・定性的に整理する作業。
- コードブック
- コード化の基準を整理した辞書のような表。分析の再現性を高める。
- カテゴリ化
- テキストをあらかじめ定義したカテゴリに振り分ける作業。
- カテゴリ分類
- カテゴリ化と同義、項目ごとに分類するプロセス。
- テーマ抽出
- 文章の中から主要な話題・主題を抽出する手法。
- トピック抽出
- 潜在的な話題を特定・抽出する手法(例:LDAなどのトピックモデル)。
- 出現頻度分析
- 語や語形の出現回数を集計し、重要語を特定する分析。
- 単語頻度
- 特定語の出現頻度を指標として分析する基本項目。
- 連語分析
- 語が結びつくパターン(連語・コロケーション)を分析する。
- 共起語分析
- 特定の語と共に出現する語の関係性を調べる分析。
- 定性分析
- 意味・解釈に重きを置く質的な分析手法。
- 定量分析
- 数値化できる指標で結果を評価・比較する分析手法。
- 情報設計
- 読者に伝わりやすい情報の構成・階層を設計する作業。
- コンテンツ品質評価
- 正確さ・網羅性・読みやすさ・信頼性などの品質を評価する。
- コンテンツ最適化
- SEOとユーザー体験の両方を考慮してコンテンツを改善する作業。
- ユーザー意図分析
- ユーザーが何を知りたいのか、何を達成したいのかを読み解く分析。
- 検索意図分析
- 検索クエリの背後にある意図を理解する分析。
- キーワード分析
- 関連キーワードの需要・競合度・類義語を調べる作業。
- SEO分析
- 検索エンジン最適化の観点からコンテンツを評価・改善する分析。
- 競合分析
- 競合他社のコンテンツと自社の差別化ポイントを比較する分析。
- メタデータ分析
- 著者・日付・タグ・カテゴリなどのメタデータを分析する。
- 内部リンク分析
- サイト内リンクの配置・構造を分析してSEOと回遊性を改善する。
- 可視化
- 分析結果をグラフ・図表で表現して理解を促進する。
- 文章構造分析
- 見出し・段落・論旨の構成を評価・改善する。
- 語彙豊富さ分析
- 使用語彙の多様性を評価して表現力を確認する。
- 読みやすさ分析
- 文章の難易度・読みやすさを測定して改善点を探る。
内容分析の関連用語
- 内容分析
- テキストやデータの中身を、意味・テーマ・傾向・構成などの観点から読み解く分析手法。SEOでは、コンテンツの品質・関連性・読者満足度を把握するために用いる。
- テキスト分析
- 文章データを定量的・定性的に分析する手法。語彙頻度・共起語・トピック・文体などを抽出する。
- コンテンツ分析
- 作成したコンテンツそのものを評価・改善する分析。網羅性・正確さ・読みやすさ・検索意図の適合性をチェックする。
- テーマ分析
- 文章の中心となる話題(テーマ)を特定し、構成や見出しの設計に活かす作業。
- キーワード分析
- コンテンツ内で使われている語句や検索語の出現頻度・関連性を調べ、最適化のヒントを得る。
- SEO分析
- サイトの検索エンジン最適化の状況を点検する作業。技術要素・オンページ・オフページの各観点をチェック。
- コンテンツ最適化
- 読者と検索エンジンの両方にとって有用になるよう、見出し・本文・画像・メタデータなどを改善すること。
- 文章構造分析
- 見出し階層・段落構成・要点の整理など、文章の組み立て方を評価・改善する。
- 読みやすさ分析
- 文の長さ・難易度・改行・見出しの使い方などから読みやすさを数値化・改善する。
- 文体分析
- 文のトーン・語調・統一感を評価して、ブランドに適した文体へ整える。
- 要約
- 長文を要点だけにまとめる作業。内容を短くわかりやすく伝える練習にも使う。
- 情報抽出
- テキストの中から名前・日付・場所・数値など特定の情報を取り出す技術。
- 自然言語処理
- 人間が使う言語を機械が理解・処理できるようにする学問・技術。
- セマンティック分析
- 意味・関係性を抽出して、語の意味を理解する分析。
- 感情分析
- テキストの肯定/否定・感情の強さを判定する手法。
- ユーザー意図分析
- ユーザーが検索や閲覧で何を求めているかを推測する分析。
- 検索意図分析
- 検索クエリが示す目的を特定して、適切なコンテンツ設計に活かす。
- タイトル分析
- タイトルの分かりやすさ・キーワードの適切さ・クリック率向上の観点を評価。
- メタデータ分析
- ページのタイトル・説明・OGタグなどの情報が適切かを検証。
- 内部リンク分析
- サイト内のリンク構造を見直し、巡回性とページ評価の伝わり方を改善。
- 外部リンク分析
- 他サイトからの被リンクの質・量を調べ、SEO効果を把握する。
- コンテンツギャップ分析
- 競合と比べて不足しているトピックを洗い出し、追加すべきテーマを特定。
- コンテンツ品質評価
- 正確さ・網羅性・新鮮さ・信頼性・読みやすさなど、総合的な品質を評価。
- アクセス解析
- 訪問者数・滞在時間・直帰率など、サイトのパフォーマンスをデータで把握する。
- コンテンツ戦略
- 目的・ターゲット・トピックの方針・公開スケジュールなど、長期的な計画を立てること。
- コンテンツデータ分析
- 各コンテンツのパフォーマンス指標(順位・CTR・滞在時間など)を分析。
- 競合分析
- 競合サイトの強み・弱み・戦略を比較して、自サイトの立て直しに活かす。
- ボリューム分析
- 検索ボリュームやトピックの量を調べ、狙うキーワードの規模を判断。
- 可読性指標
- Flesch等の指標を使い、文章の難易度を数値化して読みやすく改善。
- 文章の一貫性
- 論旨の整合性・情報の連携・論点のつながりを確認する。
内容分析のおすすめ参考サイト
- 内容分析:質的研究における内容分析とは? - QuestionPro
- 内容分析とは何か : 内容分析の歴史と方法について
- 内容分析:質的研究における内容分析とは? - QuestionPro
- 内容分析とは何か : 内容分析の歴史と方法について
- 内容分析(ないようぶんせき)とは? 意味や使い方 - コトバンク



















