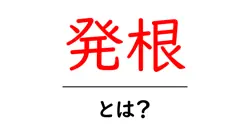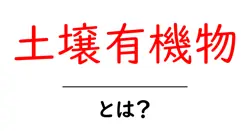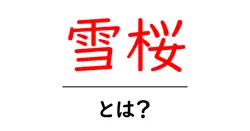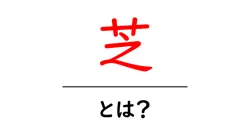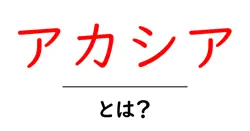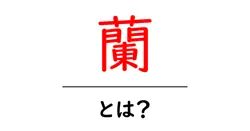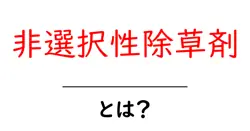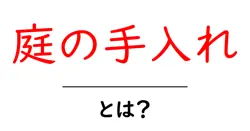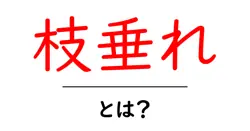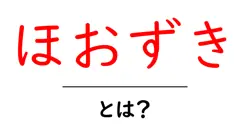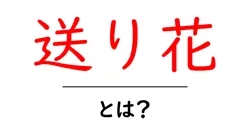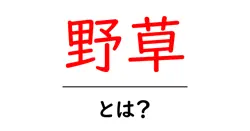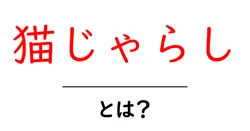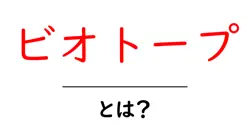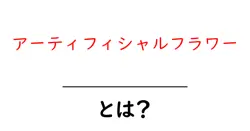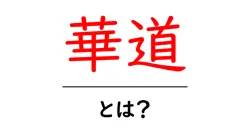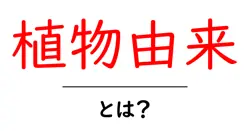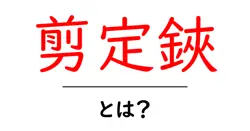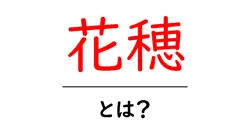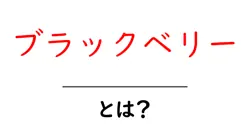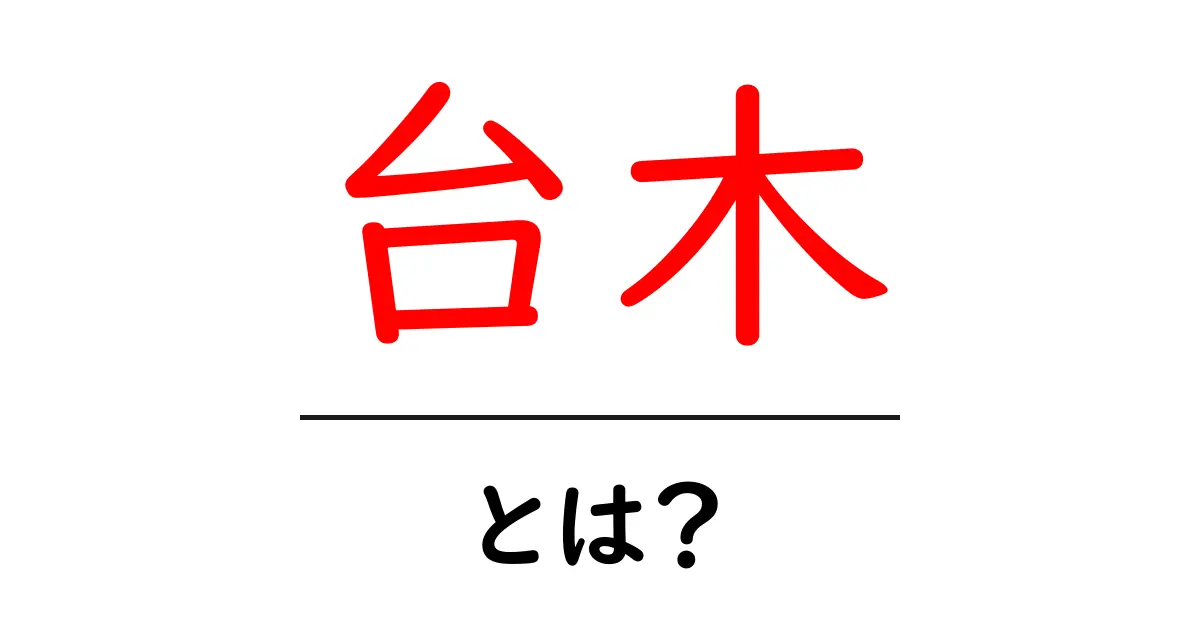

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
台木とは何か
台木(だいぎ)とは、接ぎ木で用いられる 根の部分を担う木 のことを指します。植物の苗木を育てるとき、上の部分に接ぎ穂と呼ばれる新しい枝をつけて一本の木にしますが、その接ぎ穂を支える土台となるのが台木です。台木は地中の根を通じて水分や養分を取り込み、地上部の成長を支える役割を果たします。
台木の役割は大きく分けて三つあります。まず第一に「根の力で苗全体の安定を作る」こと。次に「地上部の成長をコントロールする」こと、すなわち木の大きさや形を決める役割です。最後に「病害耐性や環境耐性を向上させる」機能を持つこと。これらの役割が組み合わさることで、病気に強く、育てやすい植物に育てることが可能になります。
接ぎ木との関係。接ぎ木とは、上の部分(接ぎ穂)と下の部分(台木)を一つの苗木に接合する技術です。台木は根の力と地上部の成長を支え、接ぎ穂は花や実をつける部分を提供します。二つの部分がうまく適合すると、病気に強く、地域の気候に適した植物を育てることができます。
台木の選び方のポイント
相性を最優先に。接ぎ穂と台木は品種ごとに相性があり、うまく組み合わせないとうまく根付かなかったり、成長が不安定になったりします。購入前に品種同士の適合情報を確認しましょう。
地域と気候を考慮。寒さや暑さ、風の強さ、雨量などの気候条件に強い台木を選ぶと、長い目でみて育てやすくなります。
土壌条件を重視。土壌のpHや栄養分の状態によって適した台木が変わります。例えば酸性土壌では根の活着が難しくなることがあるため、事前に土壌診断をすると良いでしょう。
病害耐性と管理のしやすさ。病害耐性が高い台木は栽培リスクを減らします。また、樹の大きさや剪定の手間、樹勢の安定性も初期投資として重要です。
地域の実績と信頼性。地域の園芸店や生産者の実績情報を参考にすると、地元の気候に合った台木を選びやすくなります。
代表的な台木の例
果樹の世界では、品種ごとに適した台木がさまざまです。リンゴの台木としてよく使われる系統にはM9系、M26系、M27系などがあり、樹の成長速度や耐寒性、病害耐性のバランスを考えて選ばれます。ナシやモモ、サクランボなど他の果樹でも地域や品種に応じた台木が選ばれます。柑橘類では耐病性や適応性の高い台木が複数存在し、地域の園芸家が長年の経験をもとに選択しています。
以下の表は、台木と接ぎ穂の相性や特徴の一部をざっくり比較した例です。実際には目的の品種や地域の条件に合わせて選ぶ必要があります。
植え付けと日常の管理の基本
台木と接ぎ穂を接合した苗を植え付ける際は、苗の根元がしっかり安定するように深さと水はけを確保します。根鉢を崩さず植え、初期の水やりを控えめにして根の活着を促します。成長期には適度な剪定と施肥を行い、過繁茂を防ぎます。
また、接ぎ目の周りを清潔に保ち、病気の予防を徹底することが長期的な成功には欠かせません。特に新しく接ぎ木を行った苗は、最初の1〜2年間が重要な時期です。病害の兆候が出たら早めに対処しましょう。
まとめ
台木は接ぎ木苗の根底を支える重要な要素です。適切な台木を選ぶことで、苗の安定性・成長のコントロール・病害耐性を同時に得られます。初心者の方は地域の実績情報を参考に、品種ごとの相性や土壌・気候条件を確認してから選ぶと安心です。
台木の同意語
- 台株
- 接ぎ木で用いられる下部の木。台木と同義で、接ぎ木の基部を支える役割を果たします。
- 根株
- 台木とほぼ同義で、接ぎ木の下部に位置する木。根の部分を支え、品種の性質を受け継ぐ土台となる木を指します。
- 接木用根株
- 接ぎ木に使用する根株のこと。品種の適合性や耐病性を考慮して選定されており、接ぎ木の成功を左右します。
台木の対義語・反対語
- 自根苗
- 台木を使わず、自分の根だけで育つ苗木。根系の提供を受けない点が、台木を用いた苗木と対照的です。
- 接木苗
- 根は台木の根と上部の苗が接合して育つ苗木。台木を中心とした構造の概念と対になるものです。
- 実生苗
- 種子から発芽して育てた苗木。台木を介さず育つケースが多く、遺伝的背景が多様になる点が特徴です。
- 挿木苗
- 枝や芽を挿して育てる苗木。接ぎ木とは別の繁殖法で、台木を用いないことが多い点が対比になります。
- 非接ぎ木苗
- 接ぎ木をしていない苗木。台木を使う苗木の対極として挙げられる表現です。
- 種子繁殖苗
- 種子を用いて育てた苗木。台木を介在させず、種子から育てる繁殖法の一例として捉えられます。
台木の共起語
- 接ぎ木
- 台木と穂木を結合して一本の木を作る技術。健全な接ぎ木は安定した生育と長期の成長を支えます。
- 穂木
- 接ぎ木に用いる枝や芽の部分。台木と組み合わせて新しい樹形や品種を育てる材料です。
- 接ぎ口
- 台木と穂木が接合する箇所。強固で漏れのない接ぎ口を作ることが根の結合と発育の要になります。
- 根域
- 台木の根が広がる領域。水分と養分の吸収を左右するため、適切な根域管理が重要です。
- 根系
- 木の根の集合体。太く丈夫な根系は水分と栄養の安定供給に寄与します。
- 根張り
- 根が地中にしっかり張る状態。根張りが弱いと倒伏や病害への抵抗力が低下します。
- 耐病性
- 病害に対する抵抗力。耐病性の高い台木を選ぶと病害リスクを減らせます。
- 品種適合性
- 穂木と台木の組み合わせが相性良く育つ適合性。適合性が高いほど成長・収量が安定します。
- 土壌適性
- 台木が適応する土壌条件(pH、水はけ、養分など)。適切な土壌適性を選ぶことで健全な生育を促します。
- 樹勢
- 木全体の成長の勢い。過度な樹勢は管理の難易度を上げるため、適切な調整が必要です。
- 発根力
- 切断面から新しい根を出す能力。発根力が高いと接ぎ後の回復と成長が早くなります。
- 苗木
- 接ぎ木の材料となる若木・苗木の総称。初期の健全さが将来の生育に影響します。
- 果樹
- 台木は主に果樹栽培で用いられることが多い。果樹の種類に応じた台木選びが重要です。
- 収量安定性
- 台木選定が収量の安定性に寄与する度合い。病害耐性や環境適応性が影響します。
- 選定
- 目的に合わせて台木や穂木を選ぶ作業。適切な選定は生育・収量に直結します。
台木の関連用語
- 台木
- 接ぎ木の下側に位置する植物体。根と幹を提供し、樹勢・耐病性・耐寒性などの性質を決定する重要な部位。
- 穂木
- 接ぎ木の上側に接合される部分。元の品種の特性を受け継ぐ部分。
- 接ぎ木
- 二つの異なる植物体を結合して一つの植物として育てる繁殖・育成技術。
- 苗木
- 若木・苗木のことで、台木・穂木として使われることがある。
- 台木選抜
- 樹勢・耐病性・適応地域などの条件に合う台木を選ぶ作業。
- 穂木選抜
- 接ぎ木に使う穂木を選ぶ作業。品種の適性と健康を確認する。
- 品種相性
- 台木と穂木の組み合わせが安定して成長・結合できるかの適合性。
- 樹勢
- 木の成長の勢いのこと。台木は樹勢を調整して過繁茂や過小成長を防ぐ。
- 樹勢抑制
- 台木の特性で樹勢を抑制すること。主に矮化効果などを指す。
- 矮化
- 樹高を低く抑える性質の台木を用いること。栽培スペースの節約や管理のしやすさにつながる。
- 耐病性
- 病害に対する抵抗力。台木の選択で重要な要素。
- 耐寒性
- 寒さに対する耐久性。地域に合わせて適切な台木を選ぶ目安。
- 寄木
- 一つの根株に複数の穂木を接ぎて、同じ木に複数の品種を育てる技法。
- 芽接ぎ
- 穂木の芽を台木に接ぐ方法。比較的早く結合が形成される。
- 切り接ぎ
- 穂木と台木を切り合わせて接合する基本的な接ぎ方。
- 割り接ぎ
- 台木を割って穂木を挿し込む接ぎ方。