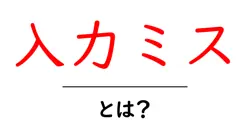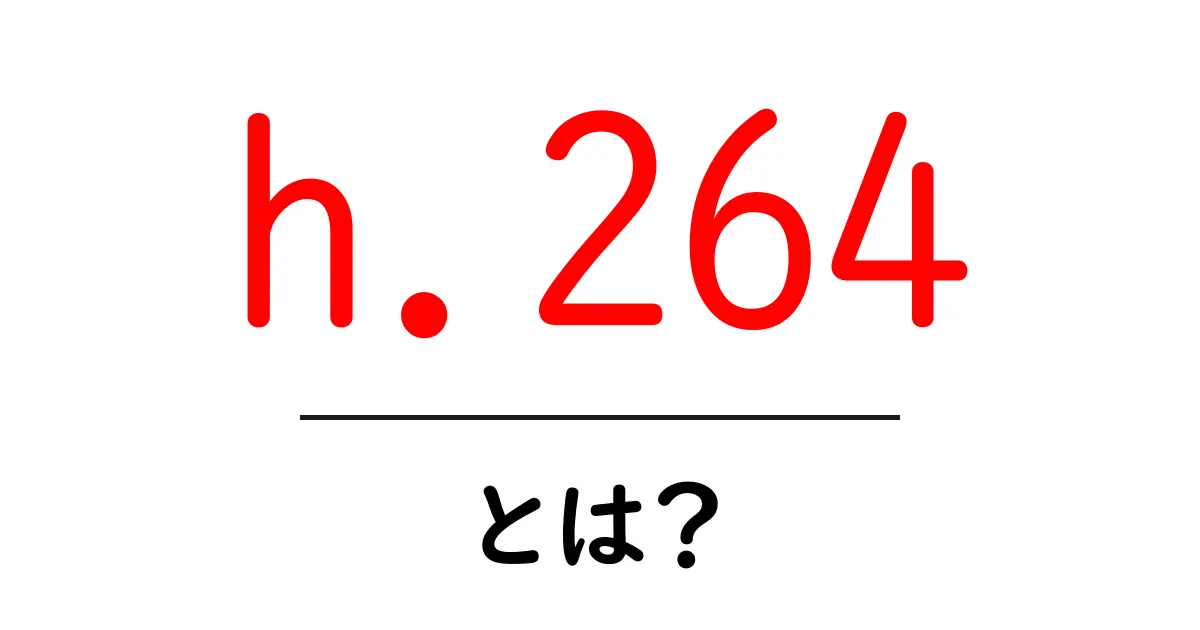

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
h.264とは何かをやさしく解説
動画ファイルを保存するとき、データ量が大きすぎると再生が遅くなったり通信に時間がかかったりします。そこでデータを圧縮して小さくする仕組みが必要になります。h.264はその代表的な規格のひとつです。正式には H.264 と呼ばれ、ITU-T と ISO/IEC が共同で定義した動画の圧縮規格です。読み方は「エイチ・ドット・二・六四」です。元々は新しい映像を高い画質のまま小さくすることを目標に作られました。
この規格が生まれた背景には、インターネットの普及とスマートフォンの登場があります。みんなが動画をスマホやパソコンで見るようになったため、通信量を減らしつつ画質を保つ技術が求められました。H.264はそれに応えるべく、従来の規格と比べて「同じデータ量でも画質が良い」または「同じ画質ならデータ量を少なくできる」といった利点を持っています。
どうやってデータを小さくするのか
圧縮の基本は「似ているものをまとめて記録する」ことです。H.264は動画を「画面の静止した部分と動く部分」に分けて扱います。まず連続する画像(フレーム)間の違いを予測して記録する方法を使います。これを動き予測と呼び、実際には前のフレームを参考にして次のフレームを作るようにします。その結果、同じ場面でも全てのピクセルを一から記録する必要がなくなります。
さらに画面の細かな変化を扱うときには変換と量子化という技術を使います。複雑な映像の情報を、視覚的に重要な部分だけを残す形で数値に変換します。これを行うとデータ量を大きく減らすことができます。最後にエントロピー符号化という「短い記号で意味を伝える」方法で、さらにデータを詰め込みます。すべての段階で品質とデータ量のバランスをとるのがH.264の特徴です。
主な特徴と使われ方
特徴としては高い圧縮効率と広い互換性が挙げられます。高画質を保ちながらファイルサイズを小さくできるため、動画サイトの配信、スマホの撮影、テレビ放送、Blu-ray などさまざまな場面で使われています。
使われ方としては、動画をオンラインで視聴する際の「動画のフォーマット」として選ばれることが多いです。代表的な用途には YouTube やストリーミングサービス、デジタルカメラの録画ファイル、Blu-ray の一部規格などがあります。
デメリットと限界
データを過度に圧縮すると画質が劣化することがあります。H.264にも限界があり、非常に低いビットレートでは細部が崩れることがあります。最新の規格である H.265(HEVC)や AV1 などは、同じ画質でさらに小さなファイルを作れる場合がありますが、対応機器やデコードの計算量が増えるため、すべての環境で使えるわけではありません。
簡単な比較表
まとめ
要するに h.264 は「動画を軽くて扱いやすくするための技術」です。使い方次第で、通信をそんなに増やさずに高画質な動画を楽しむことができます。初心者の方でも、動画を作ったり観たりするときに H.264 のことを知っていると、用途や設定の選び方がわかりやすくなるでしょう。
h.264の関連サジェスト解説
- h.264/avc とは
- h.264/avc とは、動画を圧縮して容量を小さくするための標準規格です。正式名称はH.264/AVCで、ITU-TがH.264、ISO/IECがAVCとして規格化しています。私たちが普段見る動画やオンライン配信の多くは、この規格の圧縮技術を使って、画質を保ちながらデータ量を抑えています。仕組みのポイントは3つです。1つはブロック単位の処理。動画の画面を小さなブロックに分けて、それぞれを処理します。2つ目は予測と差分の考え方。前のフレームを見てこの場面はこれくらい動くだろうと予測し、実際との差分だけを小さく伝えます。3つ目は全体の情報をどう効率よく並べるかというエンコードの工夫。Iフレーム、Pフレーム、Bフレームといった種類のフレームを組み合わせ、画質とデータ量のバランスをとります。さらにデータを圧縮して伝えるための符号化CABACやCAVLCも使われます。この規格が優れている理由は、同じ画質でも以前よりファイルサイズを大幅に減らせる点です。スマホやパソコン、テレビのハードウェアにも対応しており、YouTubeやNetflix、LINEのビデオ通話など日常的な場面で活躍しています。一方で特許料がかかるため、特許料に関する話題が時々出ます。最近は新しい規格としてH.265/HEVCやAV1が登場していますが、H.264/AVCは今なお広く使われており、学習の入り口としてもおすすめです。覚えておくべきことは、h.264/avc とは動画を質を保ちながらデータ量を抑えるための標準的な圧縮技術であるということです。
- h.264 master とは
- h.264 master とは公式な定義としては存在しません。実務の現場でよく耳にする表現ですが、多くの場合は「H.264 で圧縮した元データ(マスター)」を指す言い方として使われることが多いです。つまり最終的な配信や編集の元になる高品質な動画ファイルを、H.264 という圧縮技術を用いて作成したもの、という意味合いです。H.264 は動画を圧縮するための標準技術の一つで、画質を保ちながらデータ量を減らす仕組みを持っています。 使われ方は幅広く、ネット配信やスマホ・パソコンでの視聴、テレビ放送の補助ファイルなど、さまざまな場面で用いられます。 ここで覚えておきたいポイントは三つです。 第一に、H.264 はブロックごとに映像を処理してデータ量を減らします。 第二に、プロファイルと呼ばれる設定段階があり Baseline、Main、High など、再生機器の性能や用途に合わせて選ぶことができます。 Baseline は低スペック機器向け、High は高画質を狙う場面に適しています。 第三に、H.264 は他の圧縮技術と比べて互換性が高く、現在でも多くの機器やプラットフォームで広くサポートされています。 ただし、最新の圧縮技術と比べると圧縮効率はやや劣る場合があり、ファイルサイズと画質のバランスを取る際にはビットレートの設定が重要になります。 まとめとして、h.264 master とは公式な用語ではなく、H.264 で圧縮した元データを指す慣用表現であると理解しておけば良いです。動画を作るときは、用途に合わせて適切なプロファイルと適正なビットレートを選ぶことが、再生時の安定性と画質のバランスを取るコツです。
- h.264 mp4 とは
- この記事では h.264 mp4 とは 何かを、難しくなく解説します。まず h.264 は動画を圧縮する技術の名前で、動画のデータ量を小さくして再生しやすくする役割があります。mp4 は動画や音声を1つのファイルにまとめる容器の名前で、テキストや字幕を入れることもできます。つまり h.264 mp4 とは、h.264 という圧縮技術で作られた動画を mp4 という容器に入れたファイルのことを指します。実際には h.264 は多くのデバイスやアプリで広く使われており、スマホやパソコンで動画を再生する際の標準的な形式の一つです。なぜ mp4 が人気なのかというと、再生の互換性が高く、ファイルサイズと画質のバランスが良いからです。さらにこの組み合わせはネットで動画を見たりSNSにアップしたりする時にもよく使われます。注意点としては mp4 が容器の名前であり中身の圧縮方式が h.264 以外にも存在する点です。例えば新しい規格の h.265 などもあり、ファイルの大きさや再生環境で選択肢が変わります。初心者の方はまず h.264 mp4 の組み合わせを覚えると動画に関する話がわかりやすくなります。
- quicksync h.264 とは
- quicksync h.264 とは、Intelが自社のCPUに内蔵するQuick Sync Videoというハードウェア機能を使って、H.264形式の映像をエンコード・デコードする方法です。H.264は今も世界で最も普及している動画コーデックで、画質とデータ量のバランスが良く、動画の容量を抑えつつ見やすさを保てます。従来はPCのCPUを使ってエンコードしていたため、高いCPU負荷と長い時間がかかることがありました。これに対してQuick Syncを使うと、CPUの一部ではなく、統合GPU(iGPU)を使って処理するため、動画のエンコードが速くなり、同時に省電力にもなります。特にノートパソコン(関連記事:ノートパソコンの激安セール情報まとめ)や長時間作業で効果が大きいです。対応しているのは、Sandy Bridge以降のIntelのCPUで、内部GPUを搭載しているモデルです。世代や搭載状況により、対応するH.264のプロファイルや設定項目が異なることがあります。実際の使い方としては、OBS Studio、Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve、HandBrake、FFmpegなど、H.264エンコードを選べるソフトでエンコーダをquicksync h.264やQSVに設定します。設定例としては、出力のビットレートを適切に設定し、GOP長やプリセットを中程度から速めに選ぶと、速度と画質のバランスが取りやすいです。短時間の配信や動画のダイジェスト作成、画面キャプチャの録画など、CPUを休ませたい場面で特に有効です。ただし、ソフトウェアエンコードと比べて微妙な画質差が出ることもあるので、目的に合わせて設定を調整しましょう。
- jpeg/h.264 とは
- jpeg/h.264 とは、日常のスマホやパソコンでよく耳にする言葉です。まず覚えてほしいのは、jpeg/h.264 は二つの別々の技術の名前という点です。jpeg は Joint Photographic Experts Group の略で、静止画、つまり一枚の写真を圧縮してファイルを小さくする仕組みです。写真を保存するときには、画質とファイルの大きさのバランスを考えます。jpeg は色の情報を少し失っても、人の目にはそれほど違和感が出にくいという特徴があります。次に h.264 についてです。h.264 は動画を圧縮する規格で、動画は静止画が連続して動いている状態なのでデータ量がとても大きくなります。そこで、h.264 は前の画と次の画を比べて、動きの少ない部分をうまく表現してデータ量を減らします。これにより、高い画質を保ちながらもファイルサイズを小さくし、通信や保存が楽になります。実際には jpeg や h.264 がそのままファイル形式の名前になるわけではなく、動画には mp4 や mkv のような容器(データを入れる箱)に、h.264 の映像データと音声データをまとめて保存します。一方、静止画は jpg や jpeg の拡張子を持つファイルとして単体で保存されることが多いです。また、昔は動画でも jpg の連続フレームを使う「M-JPEG」という方式もありましたが、現在は主に h.264 が広く使われています。要するに、jpeg は写真用、h.264 は動画用の圧縮技術で、それぞれの用途と仕組みを理解すると、ネット上の画像・動画データの扱い方がよく分かります。日常生活の中で、写真を軽く保存したいときには jpeg、動画を軽く再生したいときには h.264 を頭に入れておくと便利です。
- nvidia nvenc h.264 とは
- nvidia nvenc h.264 とは、NVIDIAのGPUに搭載されたハードウェアエンコーダ「NVENC」を使って、H.264形式の動画を圧縮する仕組みのことです。H.264は長い間使われている動画圧縮規格で、画質とファイルサイズのバランスが良く、インターネット配信にも適しています。NVENCを使うと、動画を作るときにCPUを使わずGPU側で圧縮処理を行えるため、ゲームを遊ぶパソコンやノートパソコンで配信したり録画したりするときにCPUの負担を大幅に減らせます。どういう場面で役立つかというと、ゲーム実況、ライブ配信、スクリーン録画などです。特に配信では画面遷移や動きが多い場面でも滑らかな映像を保ちやすくなります。設定方法は、OBS Studioなどの配信ソフトでエンコーダを「NVIDIA NVENC H.264」に選び、ビットレートやレート制御(CBRやVBR)、プリセット、キー情報などを調整します。ビットレートは配信の画質と回線速度に影響します。通常はCBRで一定の画質を保つ設定が推奨されます。ただし生放送の回線が不安定な場合はVBRにすることもあります。プリセットは処理の重さと画質のバランスを表します。NVENCの世代によって名称が違うことがありますが、一般的にはQualityやPerformanceのような選択肢があり、画質を優先するか処理を軽くするかを選べます。注意点としては、 NVENCはGPUの性能に依存する点です。古いGPUでは画質がソフトウェアエンコードより劣ることがあります。設定を適切に選ぶことが重要です。録画と配信を同時に行う場合は、カクつきを避けるためにビットレートを抑えるか解像度を下げると良いです。最新のGPUではHEVC(H.265)にも対応していますが、互換性の点ではH.264がまだ広く使われています。まとめとして、nvidia nvenc h.264 はCPU負荷を減らしつつ高画質な配信・録画を実現する有力な選択肢です。正しい設定で使えば初心者でも比較的簡単に導入でき、OBSなどのツールと組み合わせて手軽に高品質な動画を作れます。
- 動画 h.264 とは
- 動画 h.264 とは、動画を小さくしてインターネットで送ったりスマホで再生したりするための“圧縮のしくみ”の代表格です。正確には AVC(Advanced Video Coding)と呼ばれるコーデックの名前で、映像データを効率よく圧縮して品質を保ちながらデータ量を減らします。H.264 がどうやってデータを減らすかというと、前のフレームと現在のフレームの違いを上手に見つけ、動きの少ない部分は多く、動きの速い部分は少しだけ情報を残して表示します。これを可能にするのが予測符号化と呼ばれる技術と、Iフレーム、Pフレーム、Bフレームといった種類のフレームです。 この規格はファイル形式ではなく、動画の“圧縮の仕組み”です。実際には MP4、MOV、MKV などの容器(コンテナ)に H.264 の映像データが入って再生されます。つまり、拡張子が .mp4 の動画でも中身は H.264 で圧縮されたデータかもしれませんし、別のコーデックが使われている場合もあります。 なぜ H.264 が広く使われるのかというと、画質を保ちながらデータ量を抑えるバランスが良いこと、そして多くの機器やソフトで再生できる互換性が高いことです。スマホの動画、YouTube での動画、テレビの放送など、日常のあらゆる場面で見かけます。 初心者向けの使い方のコツをいくつか紹介します。まずエンコードの際にはプリセットやプロファイルを選べることが多く、目的に合わせて Baseline、Main、High などを使い分けます。Baseline は互換性重視、High は品質重視です。次にビットレートを適切に設定します。低すぎると画質が荒れ、高すぎるとデータ量が増えすぎます。解像度とフレームレートも用途に合わせて選びましょう。 また、H.264 は新しい規格と比べると同じ画質でファイルサイズが大きくなることがあります。一方で H.265/HEVC や AV1 はより小さくできる場合が多いですが、対応機器の差があるため用途を見極めて選ぶのが大切です。 総括として、動画 h.264 とは映像を効率よく圧縮する代表的なコーデックの一つで、ファイル形式を指すものではなく圧縮方法のことです。広い互換性と安定した画質を両立させやすく、動画制作や配信の入り口として覚えておくと役立ちます。
- amd hw h.264 とは
- amd hw h.264 とは AMDのGPUが持つH.264のハードウェアエンコーディング機能のことです。H.264は動画を圧縮して小さくする規格で、配信や録画の画質を保ちつつデータ量を減らす役割があります。CPUを使わずGPU側でエンコードを行うため、パソコンの負荷を軽くしてゲームや作業の動作を妨げにくくなるのが大きなメリットです。AMDのGPUは世代ごとにVCE(Video Coding Engine)からVCN(Video Core Next)へと呼ばれ方が変わり、現在はVCN系のH.264ハードウェアエンコードが主流です。ソフトウェア側のエンコーダと比べると、エンコードの処理をGPUにオフロードする分、CPUは別の作業に使え、録画や配信の安定性が向上します。ただしハードウェアエンコードには品質や設定の違いが生じることがあります。実際の使用では、OBS Studioなどの配信ソフトでエンコード設定を「AMF H.264」や「AMD VCE/H.264」といったハードウェアエンコーダに切り替え、ビットレートやプリセットを現場のネット環境や必要な画質に合わせて調整します。新しい機能やデベロッパーの更新によって画質が改善されることが多く、fpsを高く保ちつつ遅延を減らしたい配信・編集用途に向いています。ウェブカメラ含めた配信環境やソフトウェアの設定次第で、ハードウェアエンコートのメリットを最大化できるので、まずは試してみて、パソコンの動作感や画質の変化を比べてみるとよいでしょう。
h.264の同意語
- H.264
- ITU-Tが標準化した動画圧縮規格の呼称。正式にはH.264/AVCとして知られ、広くAVCやMPEG-4 Part 10と同義で使われます。
- AVC
- Advanced Video Coding の略。H.264の正式名で、同じ規格を指します。
- MPEG-4 Part 10
- ISO/IEC 14496-10として規格化された呼称。H.264/AVCと同義の正式名称の一つです。
- MPEG-4 AVC
- MPEG-4の第10部として定義される動画圧縮規格。H.264/AVCと同義です。
- AVC/H.264
- AVCとH.264を併記した表記。意味は同じ規格を指します。
- H.264/AVC
- H.264とAVCを併記した表記。意味は同じ規格を指します。
- ITU-T H.264
- ITU-Tが正式に規格化した名称。一般にはH.264と同義として使われます。
- ISO/IEC 14496-10
- H.264の国際規格番号。MPEG-4 Part 10に対応する正式名称です。
- Advanced Video Coding
- 規格の英語名称。H.264の長い正式名です。
h.264の対義語・反対語
- 非圧縮映像
- H.264が行う圧縮を行わない映像データの状態。ファイルサイズは非常に大きくなりますが、画質は元データに近く、圧縮アーティファクトが発生しません。
- 生データ映像
- 圧縮・加工されていない生の映像データ。「原始映像」と同義で、編集前の未処理データです。
- 原始映像データ
- 未処理・未圧縮の映像データ。後で圧縮処理を受ける前の元データ。
- アナログ映像
- デジタル圧縮を前提とする H.264 とは対照的な、デジタル化されていない映像源のこと。
- ロスレス圧縮
- データを失わずに圧縮する方式。H.264 が主に採用する lossy 圧縮とは対極に位置します。
- 可逆圧縮
- 圧縮してもデコード後に元データを完全に復元できる圧縮方式。失われない圧縮の概念です。
- 低圧縮動画
- 圧縮率が低く、ファイルサイズが大きい動画。H.264 の高い圫縮効率の対極的な例として挙げられます。
- 非圧縮データ
- データが圧縮されていない状態そのもの。映像以外のデータにも適用される概念です。
h.264の共起語
- AVC
- Advanced Video Coding の略。H.264の正式名として使われることが多いです。
- H.264/AVC
- H.264 の別称で、最も一般的なビデオ圧縮規格の総称です。
- MPEG-4 Part 10
- 正式名称で、国際標準化機構(ITU)とISO/IECが定義した規格。
- CABAC
- Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding の略。H.264の高効率な符号化方式のひとつです。
- CAVLC
- Context-Adaptive Variable Length Coding の略。低遅延・低複雑度の符号化方式です。
- Baseline
- Baselineプロファイルは基本的な機能だけを持つ低遅延向けのプロファイルです。
- Main
- Mainプロファイルは中程度の機能と互換性を提供します。
- High
- Highプロファイルは高画質・高機能向けのプロファイルです。
- High 10
- High 10は10-bitカラー深度をサポートする拡張プロファイルです。
- High 4:2:0
- 4:2:0の色差サブサンプリングと高画質を組み合わせたプロファイルです。
- I-フレーム
- Intra予測だけで符号化されるフレーム。動画の基本となる参照フレームです。
- P-フレーム
- 予測符号化を用い、Iフレームを参照して圧縮します。
- B-フレーム
- 複数の参照フレームを使う高効率の予測フレームです。
- GOP
- Group of Pictures の略。連続するI/P/Bフレームの集合で、圧縮効率と遅延を決めます。
- マクロブロック
- H.264では画素を16×16のマクロブロック単位で処理します。
- 4x4 変換
- DCTの代わりに4×4整数変換を使って信号を変換します。
- 整数DCT
- DCT風の変換を整数演算で実現する変換方式です。
- 量子化パラメータ (QP)
- 量子化の強さを決めるパラメータ。画質とサイズのバランスに影響します。
- エンコーダ
- 映像をH.264で圧縮するソフトウェアまたはハードウェア。
- デコーダ
- 圧縮された映像を復元する機器・ソフトウェア。
- 容器フォーマット MP4
- 動画データを格納するファイル形式。H.264はMP4でよく使われます。
- 容器フォーマット MKV
- Matroska形式。柔軟な格納が可能で、H.264を格納することが多いです。
- x264
- ソフトウェアベースのH.264エンコーダの代表格。多数の設定が可能。
- FFmpeg
- 映像処理ツール。H.264のエンコード/デコードにも広く使われます。
- CRF
- 定量的品質設定。x264で広く使われる画質指標としての可変ビットレート設定値。
- VBR
- 可変ビットレート。映像の複雑さに応じてビットレートを変える方式。
- CBR
- 一定ビットレート。配信などで安定したデータ量が必要なときに使用します。
- 色空間 YUV 4:2:0
- 色成分のサブサンプリング仕様。H.264で最も一般的に使われる組み合わせです。
- 色差信号
- 色の違いを示す信号(U、V成分)を扱います。
- ストリーミング HLS
- HTTP Live Streaming など、H.264を使った配信手法。
- 4K/1080p 対応
- 高解像度の映像(例:1080p・4K)にも広く対応します。
- ハードウェアエンコード NVENC
- NVIDIA製のGPUでH.264を高速にエンコードする機能。
h.264の関連用語
- h.264
- 動画圧縮規格の総称。ITU-TとISO/IECが共同で標準化し、従来の規格より高い圧縮効率と柔軟性を持つ映像規格です。
- AVC
- Advanced Video Coding の略。H.264の別称として使われます。
- MPEG-4 Part 10
- H.264の正式名称の一つ。MPEG-4ファミリーの10番目の規格として規定されています。
- ITU-T H.264
- ITU-T が標準化した動画圧縮規格。正式名の一つです。
- ISO/IEC 14496-10
- ISO/IEC が定めるH.264の国際規格番号。MPEG-4 Part 10としても参照されます。
- MPEG-4 AVC
- MPEG-4 Advanced Video Coding の略称。H.264と同等の規格を指します。
- Baseline Profile
- 負荷が低く、低スペック機器向けの基本的な機能群を提供するプロファイル。
- Constrained Baseline Profile
- Baseline の一種で、Webやモバイル用途で使われる制約付きプロファイル。CABACが使えないことが多いです。
- Main Profile
- 中程度の機能を提供するプロファイル。一般的な用途で広く利用されます。
- Extended Profile
- 追加機能を提供するプロファイル。特定用途向けに用いられます。
- High Profile
- 最高機能を提供するプロファイル。高品質・高解像度の映像向けに適しています。
- High 10 Profile
- High Profile の拡張で、10ビットカラー深度対応など高度な機能を追加します。
- High 4:2:2 Profile
- 4:2:2 色空間を前提とする高機能プロファイル。放送用途などに用いられます。
- High 4:4:4 Predictive Profile
- 4:4:4 色サブサンプリングと予測機能を強化した高機能プロファイル。
- Level
- 規格内で定義される、解像度・フレームレート・ビットレートの組み合わせを示す指標。レベルが上がるほど処理能力の限界が広がります。
- SPS
- Sequence Parameter Set の略。映像全体の基本情報(解像度、フレームレートなど)を格納します。
- PPS
- Picture Parameter Set の略。個々のフレームやシーンで使われる補助情報を格納します。
- NAL Unit
- Network Abstraction Layer の略。映像データを運ぶ基本的な単位です。
- IDR frame
- IDR(Instantaneous Decoding Refresh)フレーム。新しい参照を再開する基準となる特別な I フレームです。
- I-frame
- Intra-frame。ブロック内の情報だけで復号可能なフレーム。
- P-frame
- Predicted frame。前方のフレームから動き補償で予測されるフレーム。
- B-frame
- Bidirectional predicted frame。前後のフレームを用いて予測するフレーム。
- GOP
- Group of Pictures の略。1つの映像シーケンス内の I/P/B フレームの集合。
- Motion estimation
- 動き推定。ブロック単位で映像の動きを推定する処理。
- Motion compensation
- 動き補償。推定した動きを用いて予測フレームを再構成します。
- Intra prediction
- I-フレーム内の予測。周囲の画素情報から現在のブロックを予測します。
- Inter prediction
- P/Bフレームの予測。前後のフレームを利用して予測します。
- CAVLC
- Context-Adaptive Variable Length Coding。可変長符号化の一種、主に Baseline 系で使用。
- CABAC
- Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding。より高い圧縮率を実現しますが計算量が多いです。
- Deblocking filter
- デブロッキングフィルタ。ブロック境界のジャギーを滑らかにする後処理。
- SAO
- Sample Adaptive Offset。画素値の誤差を補正する後処理の一種。
- Transform
- 4x4 および 8x8 の整数変換。量子化前のデータを変換して符号化効率を高めます。
- Quantization Parameter (QP)
- 量子化パラメータ。数値が大きいほど圧縮率が高く、画質が低下します。
- Chroma subsampling 4:2:0
- 色成分のサブサンプリング。データ量を減らす一般的な手法。
- YUV
- 輝度成分Yと色差成分U/Vからなる色空間。H.264 の内部表現として広く使われます。
- Macroblock
- マクロブロック。輝度成分は16x16、色成分はそれに対応する小ブロックで構成されます。
- Annex B
- NAL ユニットを区切るためのバイトストリーム規約。主にシーケンスの切り替えに用いられます。
- Container formats (例: MP4)
- H.264 で圧縮された映像を格納する容器フォーマット(例: MP4、MKV など)です。
h.264のおすすめ参考サイト
- H.264とは?| Advanced Video Coding(AVC) - Cloudflare
- H.264とMP4の違いとは?相互変換する方法 - MiniTool Video Converter
- ビデオコーデック「HEVC」とは?その特長と活用方法を知る
- H264プロファイルとは - Bandicamの使い方(上級編)
- H.264とH.265とは?知っておきたい動画コーデックの違い
- H.264 ビデオ圧縮とは|Black Box 用語事典 - ブラックボックス