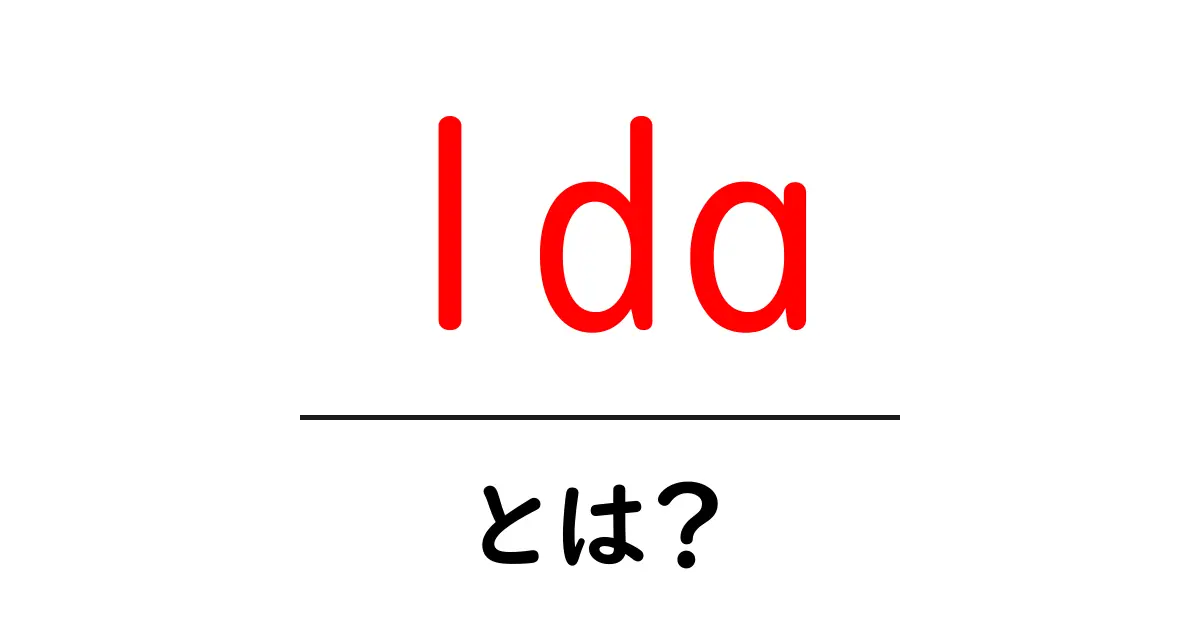

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
lda・とは?
この記事では「lda・とは?」というキーワードを分かりやすく解説します。初心者にも理解しやすい言葉で、難しい専門用語を避け、身近な例を使って説明します。
ldaとは何か
ldaは略語で、英語の Latent Dirichlet Allocation の頭文字をとったものです。日本語では「潜在ディリクレ配分を用いたトピックモデル」と呼ばれることもあります。ここでの“トピック”は文章全体の中に隠れている話題のことを指します。
どういう仕組みか
ldaは「大量の文章を読み込み、文章の中に出てくる単語のつながりから“話題”を見つけ出す方法」です。複数の話題を仮定し、それぞれの話題が特定の語彙(単語の集まり)をどれくらい含むかを推定します。最終的に、文書は複数の話題の混ざり物として表現され、それぞれの話題には代表的な語が紐づけられます。
ざっくりした例
学校の作文が3つの話題に分かれると仮定します。1つ目は「スポーツ」、2つ目は「学校生活」、3つ目は「動物」です。ldaは各作文を読み込み、各話題がどの程度出てくるかを推定します。例えば「試合」「ボール」「走る」といった語が多い作文はスポーツの話題が多い、などの判断をします。
使い方の流れ
表で見ると分かりやすい
| トピック | 代表的な語 |
|---|---|
| スポーツ | サッカー、野球、走る、試合 |
| 学校生活 | 宿題、授業、友達、先生 |
| 動物 | 犬、猫、飼い主、ペット |
注意点
ldaは「話題が何であるか」を自動で推定するツールですが、正解が必ずしも一つとは限りません。データの量や前処理の仕方、話題の数の設定によって結果が変わります。分析する目的をはっきりさせ、複数の設定を比べて解釈することが大切です。
身近なイメージ
例えば、学校の掲示板に貼られた多くの文章を読み、どんな話題がよく出てくるかを機械に教えるとします。機械は「この文はスポーツの話題が強い」「この文は学校生活の話題が強い」と段階的に判断します。人間がすぐには分からない“潜在的な話題”を、機械が見つけてくれるイメージです。
まとめ
lda・とは?の基本は「大量の文章から話題を見つけ出す方法」です。自然言語処理(NLP)の分野で広く使われ、検索エンジンの改善や研究、データ分析の現場で役立ちます。中学生でも、話題を分解して考える練習として捉えると理解が進みます。
ldaの関連サジェスト解説
- lda とは 医療
- この記事では、lda とは 医療 というキーワードをきっかけに、Latent Dirichlet Allocation(潜在ディリクレ配分)という統計的手法が、医療の世界でどう使われているかを、初心者にも分かりやすく解説します。LDAは大量の文書から“トピック”を見つけ出す仕組みです。医療分野では、論文や電子カルテの記述が日々増えているため、研究のテーマを整理したり、文献の傾向を把握したりするのに役立ちます。使い方の流れは、データの準備、前処理、モデル作成、トピックの解釈、評価の順です。データ準備では医療論文の要約や臨床ノートを集めます。前処理では日本語の分かち書き、ストップワードの除去、語幹化などを行います。次に文書-語彙の行列を作り、トピック数Kを決めてLDAを走らせます。得られた各トピックは、頻出語の組み合わせで意味づけをします。解釈には医療専門知識が役立ち、コヒーレンスと呼ばれる評価指標を用いて品質を確認します。実際の活用例として、研究テーマの自動抽出、論文の分類、臨床現場のメモから重要な情報を拾い出す試みなどがあります。ただし、LDAは確率的手法であり、同じデータでも出力が変わること、短い文章には弱いこと、適切な前処理と解釈が重要であることを覚えておきましょう。なお、医療の場でLDAという略語を使うときは、コンテキストによりLatent Dirichlet AllocationだけでなくLongitudinal Data Analysisの意味にもなるため、文脈を確認することが大切です。
- lda とは 車
- この記事は『lda とは 車』というキーワードで検索してくる初心者のための解説です。LDAとは Latent Dirichlet Allocation の略で、日本語では「潜在ディリクレ配分」と呼ばれる、長い文章の中からトピック(話題)を見つけ出す統計的な手法です。車の話題に置き換えると、車の口コミ・レビュー・記事を大量に集めて、どんな話題がよく出てくるのかを自動で整理するイメージになります。LDA自体は車の機能や部品を指す言葉ではなく、車についての情報を整理・分析するための道具だと理解すると良いでしょう。具体的なイメージとして、車ブログを1000件以上の投稿からLDAで分析すると、主に『燃費・エコ性能』『価格・コストパフォーマンス』『安全機能』『デザイン・快適性』といったトピックが浮かび上がることが分かります。これによって、読者がどんな話題を求めているのか、どの記事を増やせばいいのかを把握できます。LDAの進め方(ざっくり): 1) 車関連のテキストデータを集める 2) 余分な文字や記号を整える前処理をする 3) LDAを実行して複数のトピックを抽出する 4) 各トピックをキーワードと代表的な文で解釈する 5) その結果を元に記事のテーマを選んだり、SEOの対策を練る。注意点として、LDAは確率的なモデルなので同じデータでも結果がわずかに変わることがあります。前処理の質が結果に大きく影響するため、データを清潔に保ち、トピックを無理に解釈しすぎないことが大切です。初心者はまず小さなデータセットで試して、トピックごとの代表例を見つける練習をすると良いでしょう。結論として、lda とは 車というキーワードは、車の情報を整理・理解する道具としてのLDAを紹介するSEO向けのテーマです。車に関する文章を分析して、読者が興味を持つ話題を見つけ出す手法として覚えておくと、車ブログの企画や記事作成に役立ちます。
- lda とは 医療 肝臓
- lda とは 医療 肝臓というキーワードを前提に、LDA(Latent Dirichlet Allocation、潜在ディリクレ配分)について、医療の現場でどのように使われるかを中学生にも分かる言葉で解説します。まず、LDAは“文章の中の話題を見つける道具”であり、肝臓に関する論文や診療ノート、患者の記録など大量の文章データを分析して、記事ごとにどんな話題が含まれているかを推定します。医療分野では、肝臓病に関する研究を整理するためにLDAを使い、例えば“肝炎”“脂肪肝”“肝硬変”“肝がん”といった話題がどの文脈で現れるかを地図のように示すことができます。データの集め方は、論文の要約や診療ノートのテキストを集め、前処理として記号の削除や用語のそろえを行います。次に話題の数を決め、LDAを実行すると、各話題には重要な語の組み合わせが現れます。たとえばある話題には“ウイルス性肝炎”“B型”“C型”といった語が多く現れることがあります。結果の解釈では、各論文がどの話題にどの程度関連しているかを示す確率が出ます。研究者はこれを使って過去の研究の方向性を把握したり、新しい研究テーマを見つけたりします。臨床の現場では、最新のエビデンスを要約して把握する助けにもなります。ただしLDAには限界があります。データの質や前処理の方法、話題の数の設定次第で結果が大きく変わり、専門家の判断が必要です。このように、 lda とは 医療 肝臓の話題は、データ分析の道具として肝臓病研究をサポートするものです。
- lda とは 脳
- lda とは 脳 — このキーワードは、LDAという機械学習の考え方と脳の情報整理のイメージをつなぐものです。LDAはLatent Dirichlet Allocationの略で、たくさんの文書から話題を見つけ出す仕組みです。人は文章の中にいくつもの話題が混ざっていると感じます。LDAも同じように、文書ごとにどの話題がどれくらい入っているかを確率で表します。例えばニュース記事を読んだとき、スポーツや科学、映画といった話題が混ざっていることがあります。LDAはその混ざり方を数値で表し、後でこの文書はスポーツの話題が多いこの話題は科学用語が多いなどを教えてくれます。脳の働きに例えると、私たちの脳は新しい情報を過去の知識と結びつけて意味をつくります。LDAもデータの中のパターンを見つけて意味を整理する道具です。使い方は難しく見えますが、基本は二つのことです。1 文書の中の語の出現パターンを分析してトピックを作る。2 各トピックがどんな語をよく使うかを決める。これをうまく組み合わせると、たくさんの文書をテーマごとに整理できます。実務では検索の候補を絞る、記事を分類する、商品レビューを要約するなどに使われます。初心者向けにはまずPythonのgensimや scikit-learn などのライブラリで小さなデータセットを試すのが良いでしょう。難しい用語が出てきても大丈夫。要点は文書をトピックの集合として表すこととトピックは語の集まりという二点です。脳のように情報を整理する道具としてLDAを知ると、テキストの理解が深まります。
- lda とは 化学
- 使われ方のイメージを簡単に説明します。例えば、ケトンという種類のカルボニル化合物があり、そのα位の水素を LDA によって取り去るとエノレートができます。次に別の試薬を加えると、そのエノレートが新しい炭素-炭素結合を作る方向へ進み、元の分子に新しい置換基がついた別の化合物になります。こうした操作は、有機合成という分野で新しい薬や材料を作るときにとても役立ちます。実際の実験では、LDA を使う際に温度を低く保つことが多く、溶媒としては THF(テトラヒドロフラン)などの乾燥した溶媒が用いられます。安全面では、LDA は強い塩基で反応性が高いため、手袋や保護具を着用し、換気の良い場所で扱う必要があります。なお、LDA は実験室で専門的に取り扱う物質であり、家庭での扱いは推奨できません。日常の用語に直すと、LDAは「化学の道具箱にある強くて扱いにくい塩基の一つ」であり、α位の化学反応をうまく誘導するための手段だと覚えておくと理解が進みます。
- lda とは トヨタ
- lda とは トヨタ というキーワードから連想されるように、ここでは LDA という機械学習の考え方を、初心者にもわかるように解説します。LDAは Latent Dirichlet Allocation の略で、日本語では潜在ディリクレ配分と呼ばれる、文章の中で「どんな話題が出てくるか」を推定する統計モデルです。専門用語が多く見えるかもしれませんが、要点はとてもシンプルです。たくさんの文書を集め、その中に現れる単語の出現パターンから、いくつかの共通の話題(トピック)を作ります。各文書は、そのトピックの組み合わせとして表現され、単語は各トピックに対して出現する確率を持ちます。教科書的な説明だけでなく、実際の感覚としては「文書集団の会話の主題を分類する道具」と考えると分かりやすいでしょう。トヨタの実務に落とすと、顧客の声や製品説明・販売資料を対象に LDA を用いて「燃費・走行性能」「安全性と快適さ」「価格とコストパフォーマンス」「デザイン」などのトピックを抽出します。こうして各トピックがどの程度文書に現れているかを見れば、ユーザーが重視しているポイントが分かり、車種ごとの課題や改善点を具体的に拾い上げる手助けになります。実務では大量データを前提に分析を行うため、前処理(不要な語の除去、統一表記、語幹化など)と、トピック数の設定が重要です。トヨタのケースでは、顧客の声と製品情報を結びつけ、マーケティング戦略や製品開発の意思決定に活用することが可能です。ただしLDAは確率モデルなので「正解」は一つではなく、出力結果の解釈には人の判断も必要です。。
- lda とは 飛行機
- lda とは 飛行機?と聞くと驚く人もいるかもしれません。実はLDAという略語は、飛行機そのものとは別の分野で使われる言葉です。LDAとはLatent Dirichlet Allocationの略で、たくさんの文章の中から“話題”を自動的に見つけ出すアルゴリズムのことです。飛行機に関する記事を例にとると、機材、エンジン、燃費、安全対策、サービスなど、記事の共通した話題をいくつかのグループ(トピック)に分け、そのトピックごとに現れる単語の出現確率を求めます。そうして各トピックを上位語で解釈することができます。LDAは完全に機械任せの分析なので、最初は意味が取りづらいこともありますが、トピックの“何の話題か”を読むコツをつかむと、ブログの企画や読者の関心を把握するのに役立ちます。分析を進める上で知っておきたい点は、トピック数を決めるときの判断材料と、結果をどう解釈するかという点です。使い方の流れはおおむね次のとおりです。1) 飛行機の記事やレビューなど、分析対象となる本文データを集めます。2) 前処理として、記号を揃え、不要な語(ストップワード)を取り除き、単語を分かち書きします。3) トピックの数をいくつに設定するか決めます。4) LDAを実行して、各トピックの特徴語を確認します。5) 出てきた話題をもとに、記事のシリーズ名や記事タイトル、内部リンクの方向性を考えます。
- lda とは 電球
- このキーワードを検索すると、頭の中で ‘lda’ と ‘電球’ の関係を想像してしまうかもしれません。しかし、現実にはこの二つは別の話題です。この記事では、lda とは 電球という検索語が指す可能性を解きほぐし、初心者にも分かるように「lda とは 電球」がどういう意味なのか、そしてなぜ電球と混同されることがあるのかを説明します。首先、LDA とは Latent Dirichlet Allocation の略で、機械学習や自然言語処理で使われる「トピックモデル」という考え方です。大量の文章を読み込んで、その文章がどんな話題(トピック)で構成されているのかを見つける手法です。具体的には、1つの文書はいくつものトピックの混ぜ合わせと考えます。各トピックは特定の単語の出現傾向(確率分布)を持ち、文章の中でどの単語がどのトピックに属するかを割り当てます。モデルはデータから「この文章はこのトピックが主に含まれている」と判断し、全体のトピックを推定します。使い方の流れはこんな感じです。データを集める、前処理として形態素解析やストップワードの除去を行う、モデルのパラメータ(トピック数など)を決めて学習させる、出力として各トピックの代表語(トップワード)と各文書のトピック分布を得る、結果を解釈して文書の分類や要約、検索の改善などに活かします。電球の説明文を大量に集めると、LDA は『タイプ別の語彙』というトピックをいくつか見つけるかもしれません。例えば『LED/蛍光灯/白熱灯』といった単語群を含むトピック、次に『取り付け方/安全/交換時期』などの別のトピックが現れます。こうして各文書の背景にある話題がわかるのです。一方で、'電球' という語は家庭の照明の話題であり、LDA の話とは別カテゴリです。検索意図が混同している場合は、質問を分けて考えるとよいです。例えば『lda とは』だけでなく『電球の種類』や『LED電球 って何?』など、別のキーワードで調べると検索結果が整理されやすくなります。SEOの観点からは、検索ユーザーの意図を意識して、キーワードを自然な形で含めることが大切です。例: 'lda とは 電球' をメインの見出しにした上で、本文では LDA の説明と、電球の話題を混ぜる場合の注意点を分けて書くと読みやすいです。初心者にも理解できるよう、LDA の基本と、混同しやすい点を抑えることが重要です。
- lda とは ct
- この記事では、検索キーワード「lda とは ct」に答える形で、LDA について分かりやすく解説します。まず、LDA とは Latent Dirichlet Allocation の略で、文書を自動的にトピック(話題)に分解する統計モデルです。つまり、大量の文章データの中から、どの文書がどの話題にどれくらい関係しているかを推定します。具体的には、各文書は複数のトピックの混ざり物として表現され、各トピックは単語の出現確率を持ちます。推定には反復的な計算(Gibbsサンプリングなど)が使われ、全体として「この文書はどんな話題の組み合わせでできているか」を出力します。LDA の使い道はたくさんあります。ニュース記事の分類、ブログや論文のテーマ分析、検索エンジンのトピックフィルタ、要約の補助などです。初心者が始めやすいのは、公開データを使ってトピックを抽出し、各トピックの代表語を確認することです。このキーワードの後半「ct」については、文脈により意味が変わります。CT は計算機断層撮影(Computed Tomography)などを指す略語で、LDA の文脈とは直接関係が薄いことが多いです。つまり「lda とは ct」という検索語は、LDA の基本を知りつつ、CT という別分野の話を同時に知りたい人が混在している可能性があります。もし CT が医用画像の話で、画像データに対してトピックモデルを適用する研究を探しているなら、画像を「単語」に分けて扱う拡張的な手法や、Deep Learning との併用など別の話題になります。要は、LDA はテキストデータのトピック抽出の基礎を学ぶ入口で、ct は文脈次第で別の意味を取る用語ということです。
ldaの同意語
- 潜在ディリクレ配分法
- Latent Dirichlet Allocationの日本語表記。大量の文書コーパスからトピックを自動的に抽出する確率的トピックモデル。
- 潜在ディリクレ配分モデル
- Latent Dirichlet Allocationの別表現。文書中のトピック分布と単語分布を推定するモデル。
- Latent Dirichlet Allocation
- 英語名。文書集合の潜在的トピックを見つけ出す代表的なトピックモデル。
- 線形判別分析
- Linear Discriminant Analysisの日本語表記。教師あり学習でクラス間の分離を最大化する手法(次元削減にも用いられる)。
- Linear Discriminant Analysis
- 英語名。特徴量をクラス間の分離を最大化するように変換して、分類や次元削減を行う手法。
- 線形判別法
- Linear Discriminant Analysisの別称として使われることがある表現。
- 地方開発庁
- Local Development Authorityの日本語訳。地方の開発・インフラ整備を推進する政府機関。
- 地方開発機構
- Local Development Authorityの別表現。地域の発展を支援する組織を指す場合がある。
ldaの対義語・反対語
- LSA(潜在意味分析)
- SVD(特異値分解)を用いた行列分解ベースの手法。文書-語彙の共起行列を低次元空間に投影して潜在的意味を表現するが、確率的トピックモデルではないためトピックを確率分布として解釈しない。
- NMF(非負値行列分解)
- 語彙-文書行列を非負の要素で分解する手法。トピックは語の重みの組み合わせとして現れ、解釈性が高いが確率モデルではない。
- PLSA(確率的潜在意味分析)
- LDAの前身となる確率的トピックモデル。文書-トピック・トピック-語彙の分布を推定するが、LDAより階層構造が簡素で扱いがやや難しい点がある。
- TF-IDF+クラスタリング
- 文書をTF-IDFで表現してから、K-meansなどで文書クラスタを作る方法。トピック分布の概念を使わず、文書の類似性に基づくクラスタリングが主体。
- Word2Vec/GloVe などの分散表現
- 単語をベクトル空間に埋め込む分散表現モデル。語彙間の意味的関係を捉えるが、文書全体のトピック分布を直接学習するLDAとは別のアプローチ。
ldaの共起語
- Latent Dirichlet Allocation
- 潜在ディリクレ配分法。文書集合からトピックを抽出する代表的なトピックモデルです。
- トピックモデル
- 文書集合を話題(トピック)に基づいて表現・分類する統計的手法です。
- トピック
- 文章群の共通の話題・テーマ。各トピックは語彙の分布で特徴づけられます。
- 文書
- テキストの単位。ニュース、記事、ブログ投稿などの集合です。
- 語彙
- 文書に含まれる語の集合。
- 文書-語彙分布
- 各トピックが語彙をどの程度使うかを表す確率分布。通常 φ(ファイ)と表記されることが多いです。
- ディリクレ分布
- 多変量ディリクレ分布。LDAで θ や φ の先行分布として用いられます。
- Dirichlet分布
- ディリクレ分布の正式名称。
- α
- 文書のトピック分布 θ の事前分布のパラメータ。小さいと特定のトピックへ偏りやすくなります。
- β
- 各トピックの語彙分布 φ のパラメータ。語の出現確率を平滑に調整します。
- ハイパーパラメータ
- モデルの事前分布を決めるパラメータの総称。αやβが代表例です。
- 推論
- 観測データから θ、φ を推定する処理。推定方法として推論アルゴリズムを使います。
- Gibbsサンプリング
- Gibbsサンプリングによる推論アルゴリズムの代表例です。
- 変分推論
- 別の推論アプローチで、近似的に θ、φ を推定します。
- コーパス
- 学習対象となる大量のテキスト集合のことです。
- 文書集合
- 複数の文書の集合、データセットとして使われます。
- 学習済みモデル
- 学習が完了した LDA の状態。新しい文書へ適用可能です。
- 新規文書の推論
- 未知の文書に対して θ を推定する処理です。
- Gensim
- Python の自然言語処理ライブラリで、LDA の実装が含まれています。
- Mallet
- Java で実装された高速な LDA 推論ツールです。
- scikit-learn
- Python の機械学習ライブラリで、LDA の実装を提供します。
- LDAvis
- LDA のトピックを可視化するツールです。
- コヒーレンス
- トピックの意味的な一貫性を測る指標。高いほど解釈しやすいです。
- UMassコヒーレンス
- 文脈非依存のコヒーレンス指標の一種です。
- C_vコヒーレンス
- 外部データを用いたコヒーレンス指標の一種です。
- トピック数
- モデルに含めるトピックの数。設定または推定されます。
- num_topics
- LDA のトピック数の設定値。英語表記です。
- 文書-語の行列
- 文書-語の行列(DTM)として表現されるデータ構造です。
- document-term matrix
- 文書-語の行列の英語表記。データ前処理の出発点です。
- 前処理
- テキストを LDA に適した形に整える処理。分かち書き・ストップワード除去などを含みます。
- ストップワード除去
- 頻出で意味が薄い語を除去する前処理です。
- 分かち書き
- 日本語テキストの語を分かつ処理。形態素解析の前段階です。
- 形態素解析
- 日本語の語を形態素(品詞など)に分解する処理です。
- 解釈性
- トピックの意味を人が理解しやすいかどうかの指標です。
- 可視化
- トピック分布や語彙分布を視覚的に表示することです。
- 推定速度
- 推論に要する計算コスト・時間の指標です。
- 文書内トピック割り当て
- 文書内の語に対して割り当てられるトピックのことです(z の割り当て)。
- θ(Theta)
- 文書ごとのトピック分布の表記。各トピックの出現確率を示します。
- φ(Phi)
- 各トピックの語彙分布の表記。語がどれだけ使われるかを示します。
- 語彙分布 φ
- 各トピックが語彙をどの程度使うかを表す確率分布。
ldaの関連用語
- 潜在ディリクレ配分法
- トピックモデルの代表的手法。文書集合から文書ごとのトピック分布と、各トピックの語彙分布を推定するベイズ的モデル。
- トピックモデリング
- 大量の文書データから“トピック”と各文書のトピック分布を自動的に抽出する手法の総称。
- 文書-トピック分布
- ある文書が各トピックをどれだけ含むかを表す確率分布(θ)。
- トピック-語彙分布
- 各トピックがどの語をどの程度使うかを表す確率分布(φ)。
- ディリクレ分布
- Dirichlet分布。多項分布の事前分布として使われる、確率の和が1になる共役分布。
- αハイパーパラメータ
- 文書-トピック分布 θ の Dirichlet 事前分布のパラメータ。
- βハイパーパラメータ
- トピック-語彙分布 φ の Dirichlet 事前分布のパラメータ。
- コーパス
- 分析対象となる文書の集合。
- Bag-of-Words
- 文書を語の出現頻度だけで表す基本的な表現方法。
- 文書-トピック分布 θ
- 各文書がどのトピックをどの程度含むかを示す分布。
- トピック-語彙分布 φ
- 各トピックがどの語をどの程度用いるかを示す分布。
- ギブスサンプリング
- 潜在変数の後方分布をサンプリングして推定するマルコフ連鎖法の手法の一種。
- 変分推定
- 事後分布を近似的に求める推定法。大規模データでよく使われる。
- Online LDA
- 大規模データに対応するオンライン(逐次)推定版のLDA。
- 動的トピックモデル
- 時間とともにトピック分布が変化するモデル。
- 階層LDA
- トピック構造を階層的に表現する拡張版。
- 相関トピックモデル
- トピック間の共起関係を捉える拡張モデル。
- テーマ数 K
- 推定するトピックの総数。
- コヒーレンス
- トピック内の語の意味的一貫性を評価する指標。
- パープレキシティ
- モデルの予測困難性を測る評価指標。低いほど良いとされる。
- LDAvis
- LDAのトピックを対話的に可視化するツール。
- Gensim
- Pythonの自然言語処理ライブラリ。LDAを含むトピックモデルを実装。
- scikit-learn LatentDirichletAllocation
- scikit-learn の LDA 実装クラス。実装が手軽。
- トピック名づけ/解釈
- 抽出したトピックに意味のある名前を付けて解釈する作業。
- 前処理: トークン化
- 文書を語の単位に分割する基礎処理。
- 前処理: ストップワード除去
- 意味の薄い高頻度語を除去する処理。
- 前処理: Lemmatization/Stemming
- 語の原形に揃える処理。語の統一性を高める。
- 文書のトピック推定
- 新しい文書に対して θ を推定する作業。
- 推論収束
- 推定アルゴリズムが安定した状態に到達することを確認する指標。
- アプリケーション例: ニュース記事分析
- ニュースの話題構造を把握する用途。
- アプリケーション例: 商品レビュー分析
- レビューの話題・感情のテーマを抽出する用途。
- アプリケーション例: ソーシャルメディア分析
- 投稿の話題傾向を追う用途。
- テーマ名づけのコツ
- 抽出されたトピックに実世界の意味を持たせる工夫。
- データ規模と稀な語の扱い
- 大規模データや希少語の影響をどう扱うかの工夫。
- 線形判別分析
- 別名 LDA のもう一つの意味。線形判別分析は次元削減と分類を同時に行う教師あり学習手法。
- フ ィッシャー判別
- Fisherの線形判別基準に基づく最適判別軸の推定。
- クラス間分散
- クラス間データの散らばりを表す指標。
- クラス内分散
- 各クラス内のデータ点のばらつきを表す指標。
- 共分散行列
- 特徴量同士の分散と共分散を表す行列。
- 正規分布仮定
- 各クラスの特徴量が正規分布に従うとする仮定。
- 同質性(ホモセダスティ)
- 全クラスで共通の共分散を仮定すること。
- 固有値問題 / 固有ベクトル
- 判別軸を決める際に解く数値問題。
- 判別軸
- データを分離する最適な方向。
- 次元削減
- 重要な情報を保ちつつデータの次元を減らす操作。
- 教師あり学習
- ラベル付きデータを用いて学習する学習形態。
- 線形決定境界
- 分類境界が直線で表される境界。
- 事後確率 / 予測確率
- 新規データが各クラスに属する確率の推定値。
- 多クラス対応
- 2クラスだけでなく複数クラスにも対応。
- scikit-learn: LinearDiscriminantAnalysis
- scikit-learn の LDA 実装クラス。
- QDA (Quadratic Discriminant Analysis)
- クラスごとに共分散が異なる場合の判別分析。
- PCAとの違い
- LDAは教師ありで分類/次元削減を同時に狙い、PCAは無監督で分散最大化を目指す。



















