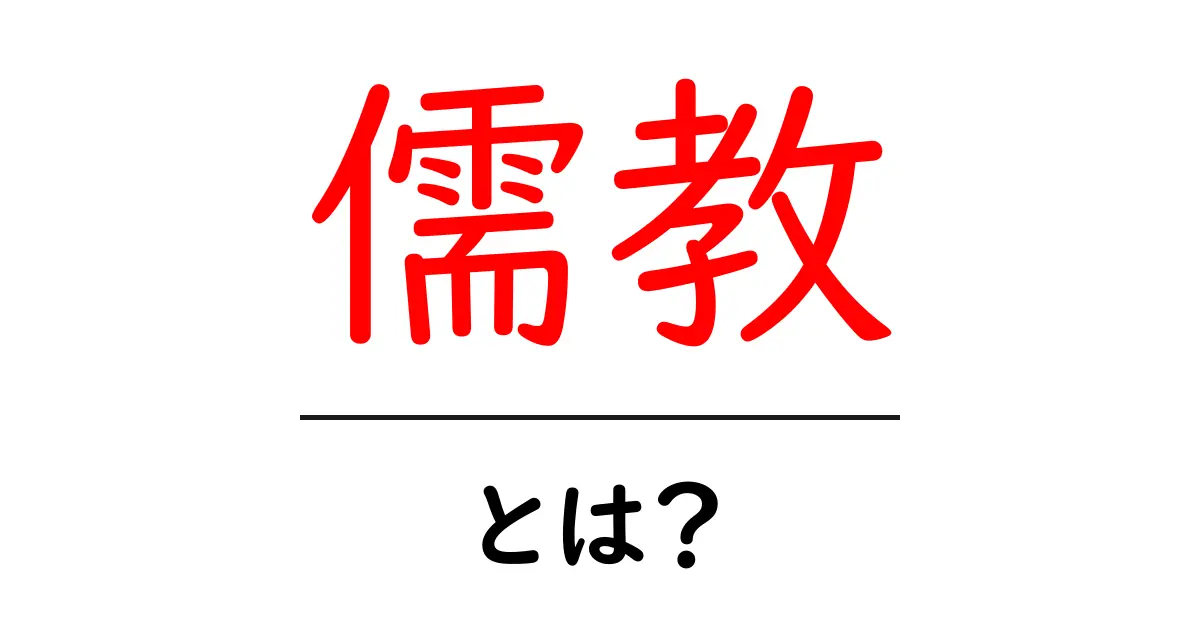

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
儒教・とは?
儒教は、人と人との関係を大切にする倫理哲学です。中国の思想家・孔子を中心に広まり、現在の東アジアの家庭や学校、社会に長く影響を与えています。儒教は宗教のように神を礼拝する体系ではなく、「どう生きるべきか」を考える道しるべのような教えです。
初心者にも分かりやすいポイントとして、儒教の基本は「仁(じん)」という人を思いやる心、「礼(れい)」という礼儀・礼節、「義(ぎ)」という正義感と責任、「智(ち)」という知恵・判断力、そして「孝(こう)」という家族を敬う心です。これらは個人の性格だけでなく、家庭・学校・社会の在り方にも結びつきます。
孔子と儒教の歴史
儒教の中心人物とされるのが孔子です。彼は紀元前6世紀ごろの中国の時代背景の中で、人と人の関係を整える道を探しました。孔子自身は貧しい家庭に生まれましたが、学問を学び、多くの対話を通じて人間関係を改善する知恵を伝えようとしました。
孔子が説いた「仁」は、ただ感情としての思いやりではなく、相手の立場を理解し、具体的な行動につなぐ力を指します。儒教の体系は、彼の弟子たちによって整理され、『論語』などの対話録として現在まで伝えられています。
儒教の基本思想
儒教の基本的な価値観は次の五つにまとめられることが多いです。仁は他者を思いやる心、礼は社会の中で適切な振る舞いを守る礼儀、義は正しいことを選び、責任を果たす勇気、智は学び続ける心と判断力、孝は親や先祖を敬い家族を大切にする倫理観です。
これらの価値は、個人の行動だけでなく、社会の制度や教育にも影響を与えました。
日常生活と儒教の関係
家庭では親を敬うこと、年長者を尊重すること、礼儀正しく振る舞うことが重視されました。学校教育や官僚制度にも儒教の思想が反映され、科挙(かきょ)という試験制度を通して人材を選ぶ仕組みが整えられました。
日本と儒教の受容
日本にも長い歴史の中で儒教が入り込み、武士の倫理観や教育制度、礼節の文化にも影響を与えました。江戸時代には「朱子学」と呼ばれる儒学の一派が広く学ばれ、幕府や藩の制度運営にも影響を及ぼしました。
現代の儒教
現在でも儒教の考え方は、アジアの家族観や教育観、社会的な責任感の形成に影響を与えています。一方で、世代間の親密さが変化する現代では、儒教の教えを現代の生活にどう取り入れるかが課題となることがあります。
誤解と正しい理解
儒教を「古い宗教」や「儀式ばかりの教え」と勘違いする人もいます。しかし本質は「人間関係を良くする倫理哲学」であり、それを現代の生活に活かす方法を探すことが大切です。
用語解説
- 仁 (じん)
- 他者を思いやる心。相手の立場を理解する力。
- 礼 (れい)
- 社会の中で適切な振る舞いを守ること。礼儀・作法を大切にする考え。
- 孝 (こう)
- 親や祖先を敬い、家族を大切にする倫理。
- 孔子
- 儒教の創始とされる思想家。人間関係の理想像を語りました。
学習のポイントと現代への活用
儒教は学問として「論語」「孟子」などの典籍にまとめられ、対話形式で教えを伝えます。現代では学校教育や企業・家庭での人間関係づくり、倫理的判断のヒントとして活用されます。現代社会における儒教の価値は、伝統と新しい生き方をつなぐ橋渡し役になる点です。
まとめ
儒教は人と人をつなぐ倫理哲学です。 日常生活の中で実践できる教えを通じて、家庭・学校・職場の人間関係をより良くするヒントを提供します。現代社会では、伝統的な価値観と新しい生き方をどう両立させるかが大きなテーマとなっています。
儒教の関連サジェスト解説
- 儒教 とは 簡単に
- 儒教 とは 簡単に、古代中国で生まれた倫理・思考の伝統です。孔子という思想家を中心に、人と人とのつながりを大切にする考え方が体系化されました。儒教の基本となる言葉には、仁(じん)=思いやり・他者を大切にする心、礼(れい)=礼儀や社会の決まりごと、孝(こう)=親を敬い家族を大切にする心、義(ぎ)=正しい行いをすること、などがあります。これらは「人を正しく導く教え」という意味で、家族や学校、地域社会の中で調和を保つのを助けます。儒教は宗教というよりも、道徳・倫理・教育の体系として理解されることが多いです。創始者の孔子が教えを弟子に伝え、『論語』などの経典にまとめられました。『論語』には日常の言葉やエピソードが多く、今でも学校の授業や倫理の話題で取り上げられることがあります。孟子や荀子といった後の学派も、仁や礼をより深く考え、政治や社会のあり方を論じました。儒教は中国だけでなく、日本・韓国・ベトナムにも伝わりました。長い間、官僚の教育や科挙制度、家庭のしつけ、祭祀の風習にも影響を与えました。現代でも、親子の関係、年長者を敬う姿勢、学校での学習姿勢など、日常生活の倫理観の基盤として役立つ考え方として残っています。ただし、宗教的な儀式を中心とする信仰とは異なり、信仰心よりも倫理・社会のあり方を重視する側面が強いと理解するとよいでしょう。儒教 とは 簡単にというキーワードを覚えておくと、難しく感じるかもしれない倫理観を、身近な人間関係や学校生活の具体例に結びつけられます。たとえば、挨拶をきちんとする、ありがとうと言う、年上を敬う、約束を守る、家族を大事にする、といった行動が儒教の考え方と結びつきます。
- 儒教 礼 とは
- 儒教における礼とは何かを知ると、日常の行動に新しい意味が生まれます。礼は単なる作法ではなく、人と人がうまく関係を保つための道徳的な規範です。儀式的な行事だけでなく、日常の挨拶、敬語、礼儀正しい振る舞い、年長者を敬う態度など、幅広い場面を含みます。儒教では仁と礼が大切な二つの柱です。仁は相手を思いやる心で、礼はその心を表す外の形と考えられます。つまり、心が仁なら礼は自然と形になり、人間関係が円滑になります。礼の働きには大きく分けて三つの役割があります。第一は儀式を通じて社会の秩序を保つこと。冠婚葬祭や国の儀式などで、人と人とが適切な関係を守る手本になります。第二は日常生活での人間関係を円滑にすること。挨拶の仕方、座り方、言葉遣いなど、場の空気を乱さず、他人を不快にさせない振る舞いを身につけられます。第三は自己修養の道具としての役割です。礼を守る練習を続けると、思いやりや謙虚さが育ちます。儒教の五倫や孝、君臣、父子、兄弟、朋友といった関係性の中で、礼は役割に応じた振る舞いを示します。例えば、年長者を敬い、上位の人には敬意を示す、でも感謝を忘れず相手を思いやる気持ちを持つ、という現代の学校生活にも通じる考え方です。現代の生活では、礼は宗教的な儀式というより、相手への配慮と社会の和を作る習慣として解釈されることが多いです。無理なく実践できるポイントとしては、挨拶を丁寧にする、約束を守る、感謝を言葉にする、話すときは相手の立場を考える、場の雰囲気を乱さないように言葉遣いを選ぶ、などがあります。このように儒教の礼とは、心の仁を形にする道具であり、日々の生活の中で人と社会をより良くするための考え方です。
- 儒教 孝 とは
- 儒教とは中国古代の思想体系で、倫理と社会秩序の基盤を作る教えです。中でも「孝(こう)」は儒教で最も重要な徳のひとつとされ、親を敬い、感謝し、親を支える義務を日常生活の行動で示すことを意味します。古典には「百善孝为先」という語があり、家族の和と社会の安定は孝から始まると考えられてきました。孝には親を養う責任だけでなく、親の意見を尊重し、困難なときには寄り添って助ける姿勢、年長者を敬う礼儀、そして先祖供養と伝統を大切にする心も含まれます。現代の日本を含む多くの社会では、孝の意味が少しずつ変化しています。盲目的な従属ではなく、対話を通じた理解と相互尊重が重視され、子どもの自立を妨げずに親の支えを行うことが理想とされます。親子間の意見の相違を話し合い、双方の幸福を探る努力が孝の現代的解釈です。家庭だけでなく学校や地域社会でも、思いやりや協力の態度として孝の精神が生かされます。さらに孝は日本の家族観や介護の価値観にも影響を与え、長寿社会の課題に対する考え方にもつながります。要点は、孝とは親をただ従わせることではなく、尊敬・感謝・責任をもって親子の関係を健全に保ち、時代に合わせて自分と親の幸福を両立させる努力をすることです。
- 儒教 五倫 とは
- 儒教 五倫 とは、儒教の教えの中で特に重要とされる5つの人間関係のことです。以下にそれぞれの関係をわかりやすく説明します。・君臣: 君主と臣下の関係では、君主は国を治め民を守る役割を果たし、臣下は忠誠と職務を果たす義務があります。現代のリーダーシップと部下の協力の考え方と重なる部分があります。・父子: 親は慈しみと教育を与え、子は親を敬い孝行することが求められます。家族の絆を大切にする考え方の根幹です。・夫妻: 夫と妻の関係では、互いを尊重し協力して家庭を築くという意味があります。現代の夫婦の協力や配慮の考え方につながります。・兄弟: 兄が年上としての責任を持ち、弟は敬意と協力を示します。年齢差に応じた役割分担を学ぶ場になります。・朋友: 友人同士の信頼と義理の関係です。互いに助け合い正直であることが大切です。以上の5つの関係は、古代の中国社会で人と人との絆を保つ道義として語られてきました。現代社会では、これらをそのままの形で実践するのは難しい面もありますが、「相手を尊重すること」「約束を守ること」「責任を果たすこと」といった教えは、今でも大切な人間関係のヒントになります。学校生活や家庭、地域の人間関係を考えるときの指針として、五倫の考え方をやさしく取り入れることができます。
- 儒教 大学 とは
- 儒教 大学 とは、現代の“大学”とは意味が違うことが多く、語感が混ざりやすい言葉です。ここでは、儒教の文献としての“大學”(ダイガク・だいがく)と、現代の教育機関としての大学の違いを分かりやすく解説します。儒教 大学 とは主に『大學』という古典的な文献のことを指す場合が多く、四書の一つとして知られています。大學は孔子の時代より後に誰が書いたかが議論されますが、一般には孔子とその弟子たちの教えを集めたものと考えられ、宋代の朱子によって四書の一冊としてまとめられました。内容は「格物致知」「修身」「齊家」「治国」「平天下」といった成長の道筋を示しており、自分を高めることが家族を整え、国を治め、世界を平和にするという連結した道として説明されます。まずは自分の心を整えることから始まり、物事を深く調べて知識を広げ、そこから正しい行いを選び取ることを学びます。その上で家庭をきちんと整え、次第に社会・国家へと良い影響を及ぼしていく、という発想です。なお「格物致知」は、物事の仕組みを調べ、知識を深めることを意味します。これらの教えは、現代の教育にも影響を与えています。現代の大学は学問の場であり、知識を得る進路を提供しますが、儒教 大学 とは違い、倫理や人格形成を中心的な目的に置く伝統的な教育思想が強く残る点が特徴です。現代生活では、正直さや責任感、他者を思いやる心といった倫理観を育てることが大切だという点で、儒教の影響を感じる場面は多いです。もし学習の入口として「儒教 大学 とは」というキーワードを調べる場合は、古典の原文だけでなく、現代の解説本や授業の入門書を合わせて読むと理解が深まります。
- 儒教 論語 とは
- 儒教とは、人と人とのつながりを大切にし、社会を良くするための道を説く思想です。論語とは、その儒教の教えをまとめた書物の名前で、孔子と弟子たちの会話や言葉が集められています。論語は孔子の死後に弟子たちが編集したもので、古代中国の春秋戦国時代の人間関係や政治の理想を分かりやすく伝えようとしています。主要な考え方には「仁(じん)」と呼ばれる人を思いやる心、「礼(れい)」と呼ばれる儀式や礼儀の意味、そして「孝(こう)」といわれる親を敬い大切にする気持ちがあります。仁は他者の幸せを自分の幸せと感じる心、礼は挨拶や約束を守るなど社会の約束ごとを大切にする行動、孝は家族に対する尽くしと感謝の気持ちを育てます。論語はこれらの教えを、物語のような対話形式で伝えるため、教室での道徳の話や、将来の指導者の在り方を考えるときの参考になります。現代の日常生活にもつながるポイントとして、思いやりの心、家族への感謝、約束を守る責任感などをどう培うかを考えるきっかけになります。儒教 論語 とはを理解するには、読み方を工夫して短い一節を噛みしめるのがコツです。論語は難解に見えますが、日常の場面に置き換えると理解が進みます。
- 儒教 聖人 とは
- 儒教は、中国を中心に伝わる道徳と社会のしくみを説明する思想です。人と人との関係を大切にし、仁(思いやり)や礼(礼儀・作法)を実践することを目標にします。そんな儒教の中で「聖人」という言葉は、ただ賢い人という意味を超え、道(この世の正しい生き方)を深く理解し、行いに表せる最高レベルの人を指します。聖人は社会の道しるべとなり、みんなが正しく生きるための“模範”を示す存在です。儒教における聖人は、孔子をはじめとする教えを実践し、後の世代に影響を与えた人物として称えられます。孔子は特に重要視され、日本でもしばしば聖人と呼ばれることが多いです。孔子は仁と礼を人々に教え、親切・誠実・勤勉といった徳を広く伝えました。聖人という語が指すのは、単に学問ができる人ではなく、心の底から他者の幸せを願い、社会の秩序と和を大切にできる人です。孔子だけでなく孟子(もう一人の偉大な思想家)も、聖人として語られることがあります。聖人と君子という概念の違いも覚えておくとよいでしょう。君子は“道徳を身につけた人”という意味で、日々の修養を通じて近づくべき理想像です。一方で聖人はその修養を極限まで進め、理論と実践の両方で社会を導く存在として描かれます。現代では「聖人」という言葉が比喩的に使われることもあり、「聖人ぶる人」への皮肉として使われる場面もあります。儒教の聖人とは、正義と善を体現する特別な人物のことであり、孔子をはじめとする偉大な教師たちの生き方を学ぶための鍵となる概念です。
- 韓国 儒教 とは
- 儒教とは人と人との関係を大切にする考え方で、どう生きるべきかを学ぶ教えです。韓国では中国から伝わり、長い間生活の支えになりました。朝鮮半島では特に朝鮮王朝の時代に性理学という新しい流派が広まり、政治や教育、家庭のしつけの基盤になりました。政府は儒教の倫理を重視し、官僚を選ぶ制度や学校の教育にもその考えが反映されました。孝行や礼儀、祖先の祭祀といった儀式は日常生活の中で自然に守られ、年長者を敬う気持ちや学問を重んじる精神が育ちました。現代の韓国では儒教は宗教というより文化的な伝統としての位置づけが強く、教育や家庭でのマナーとして影響を残しています。歴史の授業で学ぶと、昔の人々がどう社会をつくってきたのか理解しやすくなるでしょう。
- 五徳 とは 儒教
- 五德とは、儒教の教えの中で、人がよりよく生きるために大切にする五つの徳のことです。仁・義・禮・智・信の五つを指します。仁は、よく人を思いやる気持ちです。他の人を大切にし、困っている人を助ける心です。義は、正しいことを判断して、必要なときには公平に行動することです。禮は、挨拶や礼儀、約束を守るなど、社会の作法を大切にすることです。智は、物事をよく見て、賢く判断する力です。信は、約束を守り、相手を信頼できる人になることです。これらの徳は、互いに支え合い、家族・学校・地域の和をつくります。孔子の教えをまとめた『論語』には、日常でどう実践するかが多く書かれています。例えば、困っている人を助けること、嘘をつかないこと、友だちや家族を大切にすること、学び続けて知恵を深めること、約束を守って信頼を作ることなどが挙げられます。五徳は理想だけでなく、私たちが毎日に生かす行動の道しるべです。
儒教の同意語
- 儒学
- 儒教の学問・研究領域。儒教の思想を体系的に学ぶ学問分野のこと。
- 儒家思想
- 儒教が提唱する倫理・価値観・社会秩序の総称。
- 孔教
- 孔子を祖とする教えを指す語。広く儒教を指す場合もあり、教育・倫理の伝統を意味します。
- 孔子思想
- 孔子の教えを核とする思想。仁・礼・忠恕などの核となる価値観を含みます。
- 儒教倫理
- 仁・礼・義など、儒教が重視する倫理規範のこと。
- 儒家哲学
- 儒教の哲学的側面を表す言い方。倫理と知性の両方を重視する思想傾向。
- 儒学思想
- 儒学が提示する思想の総称。教育・倫理・社会秩序に関する考え方を含みます。
- 儒教思想
- 儒教が持つ世界観・倫理観・教育観の総称。
儒教の対義語・反対語
- 道教
- 儒教の倫理・階層重視の社会観に対して、自然と無為を重んじる哲学・宗教。人間関係の秩序より自然との調和や道(タオ)を重視する点で対照。
- 法家
- 倫理より法と国家機構の強制力を重視する思想。儒教の仁義礼智の徳治と異なり、法規と罰による統治を中心とする点で対照。
- 佛教
- 苦しみの原因と解脱を中心に据える宗教思想。儒教の社会倫理・家族重視の実践と対比し、現世の倫理より超世的な救済を重視する点で対照。
- 反儒教
- 儒教に批判的・反対的な立場を示す考え方。儒教の価値観や制度を見直す動きとして捉えられる総称。
- 個人主義
- 個人の自由・権利を重視し、集団・家族・社会の規範より自立を優先する倫理観。儒教の集団・秩序重視と対照。
- 現代西洋思想
- 科学・合理主義・民主主義・人権志向などを含む近現代の西洋思想群。伝統的な儒教倫理とは前提や方法論が異なる点で対照。
儒教の共起語
- 孔子
- 儒教の創始者とされる古代中国の思想家。倫理・政治の基盤を築いたとされる。
- 孟子
- 儒教の主要思想家。孟子の著作と教えは性善説などを提唱。
- 儒学
- 儒教の学問体系。倫理・政治・教育の理論と実践を扱う分野。
- 儒家
- 儒教思想を信奉・継承する学派・思想家の総称。
- 孔孟思想
- 孔子と孟子の教えを総称した倫理・政治思想。
- 論語
- 孔子と弟子の対話を収録した儒教の基本経典の一つ。
- 礼
- 社会秩序を保つ儀礼・礼儀の概念。
- 仁
- 人に対する思いやり・慈愛。仁愛の心を重視。
- 義
- 正義・道義・公正さ。社会の倫理規範となる徳。
- 礼節
- 礼儀と節度を守る態度。人間関係の円滑さを生む規範。
- 四端
- 仁・義・礼・智の四つの徳の萌芽。
- 中庸
- 過不足なく調和を保つ徳。偏らない生き方の基準。
- 君子
- 道徳的に優れた人格者。仁義礼智を身につけた理想像。
- 士大夫
- 儒教思想を背景とする知識人・官僚層。
- 孝道
- 親への孝行と敬愛を重視する倫理。
- 孝
- 親孝行の行為・敬意を表す概念。
- 忠信
- 忠実さと信義を重んじる徳。人間関係の基盤。
- 科挙
- 儒教教育を受けた官僚を選抜する制度。
- 官僚制度
- 儒教倫理を前提に形成された古代中国の官僚組織と仕組み。
- 朱子学
- 宋代に確立された儒学の一派。理と事の関係を重視。
- 儒教倫理
- 儒教に基づく倫理観・道徳規範。
- 儒教思想
- 儒教の思想全般。倫理・政治・教育を含む。
- 孔子廟
- 孔子を祀る廟。儒教文化の象徴。
- 孔子像
- 孔子を象徴する像・肖像。
- 孔孟之道
- 孔子と孟子の教え・道を指す表現。
- 教育倫理
- 教育現場で重視される倫理原則。儒教の影響がある。
- 学問
- 学問・学術の領域。儒教思想の中心テーマの一つ。
- 東アジア倫理
- 東アジア地域の共通倫理観。儒教由来の要素が多い。
- 中国思想
- 中国の思想体系の総称。儒教は中核的な潮流。
- 礼楽思想
- 礼と音楽を尊ぶ儀礼文化。儒教の儀礼観の一部。
- 家庭倫理
- 家庭内の道徳規範。親子・兄弟・夫婦間の倫理。
- 孟子の思想
- 孟子の教え・性善説・民本思想などを指す。
- 儒学者
- 儒教を学び教えを広めた学者・教育者。
儒教の関連用語
- 孔子
- 儒教の創始者とされる思想家。仁と礼を中心に道徳・政治の理想を説いた。
- 孟子
- 四書の一つ。孟子自身の著作で、仁政・性善の論を展開。
- 荀子
- 性悪説を唱えつつ、教育と礼によって人を善へと導く儒学者。
- 儒家
- 孔子を祖とする思想家の集団。倫理・社会秩序・政治理論の基盤。
- 儒学
- 儒教の教えを研究・解釈する学問。四書・五経を中心に学ぶ伝統。
- 四書
- 儒教の基本テキストの総称。論語・孟子・大学・中庸の4冊から成る。
- 大學
- 四書の一つ。自身を修養し、家庭・国家・天下の秩序を整える道を説く。
- 中庸
- 四書の一つ。過度と不足の中庸を保つことを重視する倫理思想。
- 論語
- 孔子の言行を弟子が記録した対話集。倫理・政治の基本テキスト。
- 五経
- 儒教の五経典。詩経・尚書・礼記・易経・春秋の総称。
- 詩経
- 五経の一つ。古代中国の詩を収録した文学・歴史テキスト。
- 尚書
- 五経の一つ。古代の政事・史書的記録を集めた経典。
- 礼記
- 五経の一つ。礼儀・制度・社会秩序の解説書。
- 易経
- 五経の一つ。変化と占いを通じた宇宙の理を解く思想書。
- 春秋
- 五経の一つ。中国古代の年表・史実を記述する歴史書。
- 仁
- 他者への思いやり・慈悲。倫理の中心となる徳。
- 義
- 正義・道義。道理にかなった行いを重視する徳。
- 礼
- 礼節・儀礼。社会秩序と人間関係の基盤となる徳。
- 智
- 知恵・理解。道理を見抜く力。
- 信
- 約束を守る誠実さ。人間関係の基盤となる徳。
- 五常
- 仁・義・礼・智・信の五つの基本倫理。
- 五倫
- 重複を避けるため省略。実際には五倫は君臣・父子・夫妻・兄弟・朋友の倫理関係を指す。
- 君子
- 道徳修養に努める高潔な人の理想像。
- 小人
- 欲望や私利私欲が強いとされる人の対語。
- 孝道
- 親への孝行を重視する倫理。家族の基盤となる。
- 修身齊家治國平天下
- 自身を磨き、家庭を整え、国を治め、天下を平和にする儒教の理想。
- 仁政
- 君主が民に仁愛をもって統治する政治思想。
- 三纲
- 君臣・父子・夫妻の三つの基本的支配関係。
- 科举制度
- 官吏を選ぶ科挙制度。儒教の教養を中心に試験が行われた。
- 程朱理学
- 宋代において程頤・朱子が理と格物致知を重視して形成した儒学の派。
- 朱子学
- 程朱理学の中心的流派。道徳と政治を理と一体で考える。
- 董仲舒
- 漢代の儒学者。天人感応説を取り入れ、儒教を国家思想として完成。
- 国学
- 日本で伝統的な中国思想・文学・歴史を総称する概念。儒教思想と深く関連。
- 家父長制
- 家族を父系中心に統治する伝統的制度。儒教倫理と結びつく。
- 礼教
- 礼を軸とした倫理・教育・社会統制の思想。



















