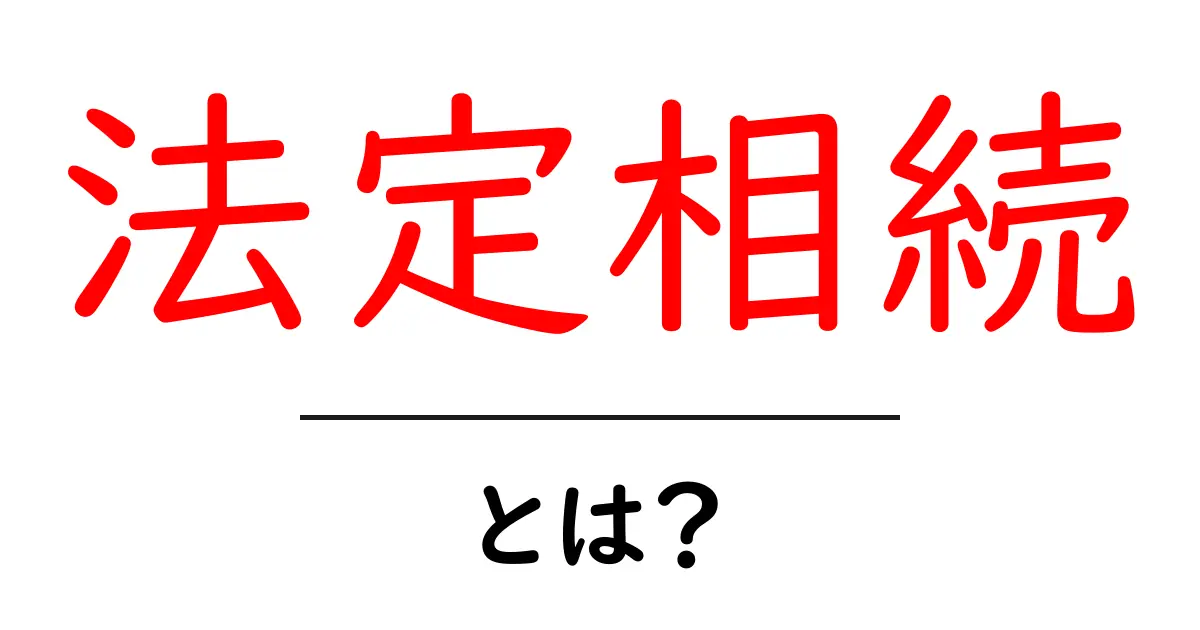

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
法定相続とは、遺言がない場合や遺言の内容が一部しか効かない場合に適用される、国が定めた「相続の分け方」のことです。誰が相続人になるのか、相続分はどう決まるのかを決める基本ルールです。
法定相続の基本となる相続人
法定相続では、まず「誰が相続人か」を決めます。中心となるのは配偶者と子ですが、場合によっては両親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。最も大切なのは、血縁関係と婚姻関係です。
法定相続分の考え方(ケース別の考え方)
以下は代表的なケースの説明です。数値は制度改正や個別事情で変わることがあります。正確な割合は専門家へ確認しましょう。
法定相続と遺言の関係
遺言があると、原則として遺言の内容が優先されます。ただし、遺言の内容が法定相続分を超える場合には、遺産の一部だけが遺言に従います。法定相続は「最低限の取り分」を確保する制度としても重要です。
手続きの流れ
まずは相続人を確定します。配偶者や子どもの有無、親や兄弟の存在などを確認し、戸籍謄本で証明します。
次に、遺産の総額と負債の有無を把握します。負債が多い場合は現在の財産の扱いも変わってきます。
その後、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。合意できない場合には家庭裁判所の調停・審判を利用します。
実務のポイント
現実の手続きでは、相続開始を知ったらすぐに動くことが大切です。金融機関や公的機関にはそれぞれ相続手続きの窓口があります。必要書類としては、戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産の一覧、財産の評価書などを揃えるとスムーズです。
遺産分割協議書を作成する場合には、誰が何を受け取るのかを具体的に記し、全員が署名・押印します。後でトラブルにならないよう、内容はできるだけ明確にしましょう。
税金のことにも注意が必要です。相続税の課税対象になる財産がある場合には、税務署や税理士に相談するとよいです。準備を早めに進めておくと、相続手続き全体がスムーズになります。
ケーススタディ
例1: 配偶者と子が1人いる家庭では、遺産の分け方を話し合い、配偶者が生活に必要な財産を確保しつつ、子へ財産を渡す形をとるケースが多いです。
例2: 配偶者と子が2人以上いる場合、子の数に応じて子どもたちへの分配が増える方向で協議が進むことが一般的です。
例3: 配偶者がいない場合には、子どもや両親・兄弟姉妹などが相続人となり、比率はケースごとに異なります。専門家のアドバイスを受けながら進めると安全です。
よくある質問
Q: 法定相続と遺言の違いは?
A: 法定相続は法で定められた基本の分け方で、遺言は故人が希望する分け方を反映します。遺言がある場合には原則として遺言の内容が優先されます。
Q: 相続税はいつかかるの?
A: 財産の総額が一定額を超えると相続税の対象になります。詳細な金額や計算方法は専門家に確認しましょう。
相続は専門的な事項が多く、個別の事情で結論が変わります。まずは家族で話し合い、必要に応じて専門家に相談しましょう。
法定相続の同意語
- 法定相続人
- 民法で定められた、遺産を法的に相続する権利を持つ人のこと。配偶者・子・親・兄弟姉妹など、相続権の順位に従って遺産を受け取る権利を有します。
- 法定相続分
- 法定相続人が法定の割合で遺産を受け取るべき割合のこと。配偶者・子などの状況により割合が決まります。
- 法定相続制度
- 民法に定められた、誰がどの割合で遺産を相続するかを決める制度のこと。遺言がない場合の基本ルールとして機能します。
- 民法上の相続
- 民法に基づく相続全般のこと。法定相続人と法定相続分を含む、法的な枠組みで遺産を引き継ぐことを指します。
- 法定相続権
- 法定相続人が遺産を相続する権利そのものを指す表現です。遺産を受け取る法律上の権利です。
- 法定相続による遺産継承
- 法定相続制度に従って遺産を相続人へ引き継ぐことを指します。遺言がない場合の標準的な手続きです。
法定相続の対義語・反対語
- 遺言による相続
- 遺言で定められた相続分・分割方法に従うこと。法定相続分を超えたり変更したりすることが可能で、法定相続の原則とは異なる分配を指します。
- 協議分割
- 相続人同士の話し合いで遺産を分割する方法。法定相続分に縛られず、合意内容を優先して決定します。
- 任意分割
- 相続人の合意のもと、法定相続分を変更して分配すること。遺言がなくても成立しますが、全員の同意が必要です。
- 私的分割
- 公的な法定分割に対して、私的な合意によって分割を決めること。一般には協議分割の一形態として使われます。
- 法定外分割
- 法定相続分の枠外で、遺言や協議で決まった分割のこと。法定分割以外の配分を指す概念として使われます。
- 遺言優先分割
- 遺言の内容が優先され、法定相続分より遺言で指定された分配を実現する考え方。
法定相続の共起語
- 被相続人
- 相続の対象となる人。死亡した個人を指します。
- 法定相続人
- 民法で定められた正式な相続人。配偶者と血縁者の一定の組み合わせが含まれます。
- 配偶者
- 被相続人の夫または妻。法定相続分で大きな割合を占めることが多い相続人。
- 子
- 被相続人の子ども。法定相続人の一つ。
- 第1順位相続人
- 第1順位の法定相続人。配偶者と子などが該当します。
- 第2順位相続人
- 第2順位の法定相続人。直系尊属(親・祖父母など)。
- 第3順位相続人
- 第3順位の法定相続人。兄弟姉妹など。
- 直系尊属
- 血統の直系上の先祖(親・祖父母など)。
- 直系卑属
- 血統の直系下の子孫(子・孫など)。
- 遺産
- 被相続人が遺した財産・権利・義務の総称。
- 遺産分割
- 遺産の分配を相続人同士で決める手続き。
- 遺産分割協議
- 相続人が遺産の分け方を話し合って決める合意のこと。
- 遺産分割調停
- 家庭裁判所での遺産分割の話し合いを行う手続き。
- 現物分割
- 遺産を現物のまま分割する方法。
- 換価分割
- 遺産を換価して現金に変え、現金で分割する方法。
- 遺言
- 故人が遺す意思表示。遺産分割の指示となることがある。
- 自筆証書遺言
- 自分で書いて作成した遺言。
- 公正証書遺言
- 公証人が作成する遺言。公証役場で作成します。
- 遺言執行
- 遺言の内容を実現する手続き。遺言執行者が務めることが多い。
- 検認
- 自筆証書遺言などの遺言の形式を裁判所が確認する手続き(公正証書遺言は不要)。
- 相続開始
- 被相続人の死亡により相続手続きが正式に始まること。
- 相続人確定
- 誰が相続人であるかを確定する手続き・作業。
- 相続手続き
- 相続登記、名義変更、財産の調整など一連の手続き。
- 相続登記
- 不動産の所有権を相続人名義へ移す登記手続き。
- 不動産名義変更
- 不動産の所有権を相続人に移す手続き。
- 戸籍謄本
- 相続人を特定するために取得する公的戸籍の写し(謄本)。
- 戸籍抄本
- 戸籍の写し(要件に応じて使われる)。
- 除籍謄本
- 死亡等を含む戸籍の改正前の戸籍謄本。
- 相続税
- 遺産に課される税金。資産の評価額に応じて算出。
- 相続税申告
- 相続税を申告・納付する法的手続き。
- 相続税の基礎控除
- 相続税計算の基礎となる控除額。
- 遺留分
- 法定相続人が最低限確保できる遺産の取り分。
- 遺留分減殺請求
- 遺留分を侵害する遺言・贈与に対し請求する権利。
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分を侵害された場合の金額請求。
- 代襲相続
- 相続人が死亡・廃除などで代わって相続すること。
- 相続欠格
- 一定の欠格事由がある場合、相続権を失うこと。
- 廃除
- 相続欠格の一部として、相続権を排除する手続き。
- 特別代理人
- 未成年の相続人などの代理人として裁判所が選任する人。
- 遺産管理人
- 相続人がいない場合など裁判所が遺産を管理する人。
- 相続人調査
- 相続人を特定するための戸籍調査などの作業。
- 公証役場
- 遺言作成や公証手続きを行う公証人の事務所・場所。
法定相続の関連用語
- 法定相続
- 遺産が法定のルールに従って分配される基本的な考え方。遺言がない場合はこの法定相続に従って相続人が遺産を分けます。
- 法定相続人
- 遺産を受け継ぐ権利が法律で決められている人。配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹などが該当します。
- 第一順位相続人
- 第一順位は子・孫などの直系卑属。子がいれば子が優先して遺産を受け取ります。
- 第二順位相続人
- 第二順位は直系尊属(父母・祖父母など)。子がいない場合に相続します。
- 第三順位相続人
- 第三順位は兄弟姉妹。子・親がいない場合に相続します。
- 配偶者
- 生存している配偶者。法定相続分を他の相続人の組み合わせで決定します。
- 子
- 法定相続人の一つ。第一順位相続人として遺産を受け取ることがあります。
- 直系卑属
- 子・孫など、血縁関係の下位の相続人の総称。
- 直系尊属
- 父母・祖父母など、血縁関係の上位の相続人の総称。
- 第一順位相続分
- 第一順位相続人が受け取る遺産の割合。配偶者の有無で割合は変わります。
- 第二順位相続分
- 第二順位相続人が受け取る遺産の割合。子がいない場合の中心となります。
- 第三順位相続分
- 第三順位相続人が受け取る遺産の割合。子・親がいない場合の選択肢です。
- 遺産
- 故人が遺した財産の総称。現金・不動産・預貯金などが含まれます。
- 遺言
- 自分の死後の財産の処遇を生前に指定する文書。法定相続分に優先することがあります。
- 遺産分割
- 相続人が誰にどれだけ分けるかを決める作業。協議・調停・審判で進めます。
- 遺産分割協議
- 相続人同士で分割方法を話し合うこと。
- 遺産分割調停
- 話し合いがつかないと家庭裁判所で調停を行います。
- 遺産分割審判
- 調停が成立しない場合、裁判所が分割を決定します。
- 現物分割
- 具体的な財産そのものを分ける分割方法。
- 代金分割
- 現物を分ける代わりに現金で等価に分割する方法。
- 換価分割
- 財産を換価して現金化して分ける方法。
- 遺留分
- 法定相続人が最低限受け取れる遺産の割合。長年の権利です。
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分が侵害された場合に請求する権利のこと。
- 遺留分減殺請求
- 遺留分を確保するための正当な請求。
- 相続放棄
- 相続を一切受け取らないと決める手続き。
- 限定承認
- 相続財産の範囲を限定して相続し、マイナス財産がある場合は負わない選択肢。
- 相続人
- 法定相続人や推定相続人など、遺産を受け取る人の総称。
- 推定相続人
- 死亡時点で相続権を持つ可能性のある人。実際の相続は後に決まります。
- 相続欠格事由
- 相続権を放棄される原因(重大な犯罪、遺産の横領など)
- 廃除
- 相続人としての権利を一定の事由で廃止する制度。
- 代襲相続
- 相続人が死亡・廃除等となった場合、その子などが代わりに相続します。
- 相続登記
- 不動産などの財産を法定相続人名義に移す登記手続き。
- 配偶者居住権
- 配偶者が遺された自宅に一定期間住み続けられる権利。
- 相続税
- 相続で取得した財産にかかる税金。控除や税率が法で定められています。
- 公正証書遺言
- 公証人が作成する正式な遺言の形式。法的に強い効力を持ちます。
- 自筆証書遺言
- 自分で作成する遺言。偽造防止の工夫が必要です。
- 相続開始日
- 相続が開始する日。通常は被相続人の死亡日。
- 家庭裁判所
- 遺産分割の調停・審判、相続関連の手続きが行われる裁判所。
法定相続のおすすめ参考サイト
- 法定相続人とは?財産を残す3つの方法について解説 | 資産管理・承継
- 法定相続・指定相続とは - 東京の遺産相続問題なら山下江法律事務所
- 遺産分割と相続の違いとは?遺産分割の方法もそれぞれ解説
- 法定相続人とは?確認方法や相続分について事例を交えて解説
- 法定相続人とは?その範囲・順位・割合をわかりやすく解説
- 法定相続人とは?範囲と相続順位、相続割合を詳しく解説 - 相続会議
- 法定相続人とは?範囲や相続順位・割合、確認方法などを徹底解説!
- 法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!



















