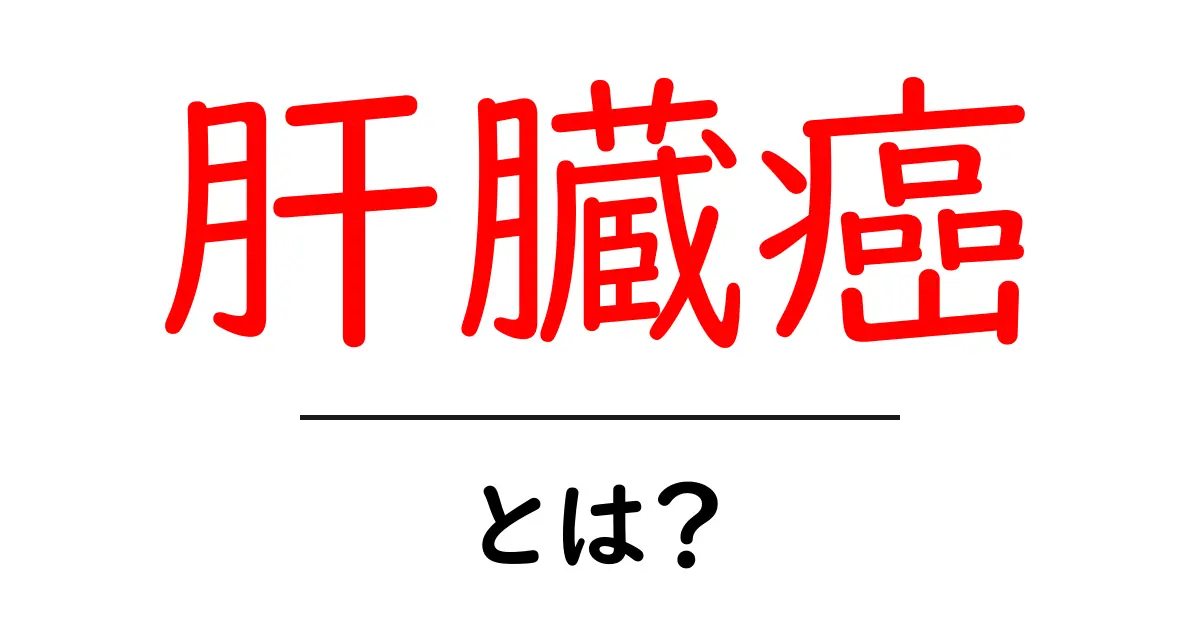

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
肝臓癌とは
肝臓癌とは肝臓に発生する悪性の腫瘍の総称です。代表的なものとして肝細胞癌があり、世界中で肝癌はがんの中でもかなり多くの人に影響を与えています。
肝臓は体の中で大きな臓器であり、血液を濾過し解毒し栄養の代謝などを行っています。そのため肝臓にはがんが発生しやすい環境が整っています。肝臓癌は原発性肝癌と転移性肝癌に分けられます。原発性肝癌は肝臓自体から発生するがんなのに対し、転移性肝癌は他の臓器から肝臓へがん細胞が飛んできてできた腫瘍です。
原因となるリスク要因としては慢性B型肝炎やC型肝炎ウイルス感染、肝硬変、長期間のアルコール摂取、非アルコール性脂肪肝疾患などがあります。これらの状態があると肝臓の細胞が長くダメージを受け、がんに変わりやすくなります。
症状については初期には目立たないことが多いですが倦怠感腹部の不快感黄疸腹水体重減少などが現れることがあります。早期発見のためには定期的な検査と医師の診断が重要です。
診断には画像検査と血液検査が中心となります。超音波検査やCT MRIで腫瘍を確認し、腫瘍マーカーのAFPなどを測定します。必要に応じて組織検査を行い病理診断を確定します。
治療は病期と肝機能によって異なります。手術で腫瘍を取り除く切除や肝移植が適用される場合があります。腫瘍が小さく周囲の組織に広がっていない場合は局所治療のラジオ波焼灼療法やラジオ波治療などを選択することがあります。血管塞栓療法を含むTACEも一般的です。
最近では分子標的療法や免疫療法といった新しい治療も進歩しています。これにより手術が難しい患者さんにも治療の選択肢が広がっています。治療は専門医のチームで決定し、肝機能を守ることが最優先です。
生活の質を保つためには栄養管理と適度な運動、禁煙とアルコール制限が重要です。家族や友人のサポートも重要で、不安や痛みのセルフケアを含めた総合的なケアが求められます。
診断と治療のポイント
診断のポイントは画像検査と血液検査を組み合わせて腫瘍の場所と大きさ、機能状態を評価することです。AFPは診断の補助情報として使われることが多いですが必ずしも原因とはなりません。
- 治療の基本
- 手術局所治療血流塞栓術など各病期で選択
- 全身治療は進行例で検討
以下は治療の具体例を表にまとめたものです。
検査の流れとしてはまずリスク評価を行い、必要に応じて画像検査を受けます。診断が確定したら治療方針の決定に移ります。
予防の観点からは予防接種と生活習慣の改善が重要です。肝炎ウイルスの治療やワクチン接種、適切な体重管理、糖尿病の治療などが長い目でみると肝臓癌を減らす助けになります。
肝臓癌の同意語
- 肝臓がん
- 肝臓に発生する悪性腫瘍の総称。転移性を除く原発性の癌を指すことが多い。
- 肝臓癌
- 肝臓にできる癌の表現。日常的には原発性の肝がんを指すことが多い。
- 肝がん
- 肝臓にできるがんの略称。日常的に広く使われる表現。
- 肝癌
- 肝臓に生じる悪性腫瘍で、肝臓がんと同義。表記ゆれ。
- 肝細胞癌
- 肝臓の主要な原発性癌の病型で、最も多いタイプ。英語で hepatocellular carcinoma の和訳。
- 原発性肝がん
- 肝臓に原発して生じたがんの意味。転移性ではなく肝臓自体が発生源。
- 原発性肝癌
- 肝臓で発生した原発性のがん。肝細胞癌などを含む総称。
肝臓癌の対義語・反対語
- 健康な肝臓
- 肝臓に病変がなく、機能が正常な状態を指します。
- 肝臓がんではない
- 肝臓に悪性腫瘍(癌)が存在しない状態を意味します。
- 良性肝腫瘍
- 肝臓に腫瘍はあるが悪性ではなく良性である状態。肝臓癌の対義語として使われることがあります。
- 非悪性肝疾患
- 肝臓に病変はあるが悪性(癌)ではない状態。
- 肝機能正常
- 血液検査などで肝機能が正常範囲にある状態。
- 健全な肝臓
- 肝臓の組織・機能が健全で、病変が認められない状態。
- 正常な肝組織
- 肝臓の組織が病的変化を伴わず、正常な構造を保っている状態。
- 肝臓病なし
- 肝臓に疾病がなく、癌を含まない状態。
- 良性病変のみ
- 肝臓に病変はあるが悪性ではなく、良性病変のみが認められる状態。
- 肝臓の正常状態
- 肝臓の機能と構造が通常の範囲内で正常な状態。
- 肝臓癌なし
- 肝臓に癌が認められない状態。
肝臓癌の共起語
- 肝細胞癌(HCC)
- 肝臓で最も多い原発性の癌。肝臓癌の代表的タイプで、血管新生を伴うことが多い。
- 原発性肝癌
- 肝臓自体に発生する癌。転移性癌とは別の、肝臓が発生源の癌を指す。
- 肝内胆管癌
- 肝臓の胆管から発生する癌。肝細胞癌とは別の主要な肝癌のタイプ。
- 胆管癌
- 胆管(胆道)にできる癌。肝内・肝外を含むが、肝内胆管癌は肝内の癌を指すことが多い。
- 肝炎
- 肝臓の炎症。慢性肝炎は肝癌リスクを高める要因の一つ。
- 乙型肝炎
- HBV感染。長期間続くと肝癌リスクが高まる。
- C型肝炎
- HCV感染。長期感染で肝硬変・肝癌のリスクが高まる。
- 肝硬変
- 慢性的な肝障害が繊維化して進行した状態。肝癌リスクを高める要因。
- アルコール性肝疾患
- 長期間の過度な飲酒による肝疾患。肝癌リスク要因の一つ。
- NAFLD/NASH
- 非アルコール性脂肪肝疾患。脂肪肝が炎症・繊維化へ進むと肝癌リスクが上がる。
- 肝機能
- 肝臓の働き全体のこと。機能が落ちると治療選択に影響する。
- 腫瘍マーカー
- 血液中のがんの指標。診断・経過観察に用いられる。
- AFP(α-フェトプロテイン)
- HCCで上昇する代表的な腫瘍マーカー。診断補助として使われる。
- DCP / PIVKA-II
- もう一つの腫瘍マーカー。HCCの補助的指標として用いられることがある。
- 画像検査
- 腫瘍の位置・大きさ・広がりを確認するための検査。CT・MRI・超音波が含まれる。
- 超音波検査
- 腹部を音波で観察し、腫瘍の存在を初期に評価する検査。
- CT(コンピュータ断層撮影)
- 腫瘍の形状・広がりを立体的に見る画像検査。
- MRI(磁気共鳖画像)
- 軟部組織の詳細を評価する画像検査。肝腫瘍の性質を区別しやすい。
- 生検
- 組織を採取して病理診断を行い、がんの種類を確定する検査。
- 血液検査
- 肝機能や腫瘍マーカーを総合的に評価する血液検査。
- AST/ALT
- 肝臓の酵素。数値の上昇は肝障害の目安となる。
- ビリルビン / ALP / GGT
- 胆道系・肝機能の目安となる血液指標。黄疸の有無などを反映。
- MELD / Child-Pugh
- 肝機能の重症度を評価する指標。治療方針・移植適応の判断に使われる。
- BCLCステージ
- 肝細胞癌の進行度と治療方針を決める代表的な分類。
- 治療法
- がんを治療する総称。手術・アブレーション・TACE・薬物療法などを含む。
- 手術療法 / 肝切除
- 腫瘍を物理的に取り除く外科治療。肝機能が許す場合に適用。
- 肝移植
- 重度の肝機能障害があるときの選択肢。限定的な適応。
- アブレーション / RFA
- 局所的に腫瘍を焼灼する治療。小さな腫瘍に有効。
- TACE
- 経動脈から化学薬を投与し血流を遮断する、未切除肝癌の標準治療の一つ。
- 分子標的治療
- がん細胞の成長を特定の分子経路で抑制する薬物療法。
- 免疫療法
- 免疫系を活性化して腫瘍を攻撃する治療法。
- 再発
- 治療後に腫瘍が再び現れる現象。治療戦略の再評価が必要になることが多い。
- 予後
- 病気がどの程度回復・生存できるかの見通し。治療の結果を示す指標。
肝臓癌の関連用語
- 肝臓癌
- 肝臓で発生する悪性腫瘍の総称。代表的には肝細胞癌と胆管癌がある。
- 肝細胞癌
- 肝臓癌の中で最も多いタイプ。慢性肝炎ウイルス感染や肝硬変が主なリスク要因。
- 肝内胆管癌
- 肝臓の胆管に発生するがん。進行が早く治療が難しいことが多い。
- 肝転移
- 他の臓器のがんが肝臓に転移して生じる病態。原発巣の治療が重要。
- 肝硬変
- 長年の慢性肝疾患により肝臓が硬くなり機能が低下する状態。肝癌の重要なリスク因子。
- HBV感染
- 乙型肝炎ウイルスの感染。肝臓癌リスクを高める要因。ワクチンで予防可能。
- HCV感染
- 丙型肝炎ウイルスの感染。慢性化すると肝硬変や肝癌の原因となる。
- NAFLD/NASH
- 非アルコール性脂肪肝疾患。肥満などが背景で肝癌リスクを高めることがある。
- アルコール性肝疾患
- 長期間の過度な飲酒が原因。肝硬変や肝癌リスクを高める。
- 肝機能障害
- 肝臓の機能が低下している状態。治療適否や薬の安全性に影響する。
- AFP
- αフェトプロテイン。肝細胞癌の血清マーカーとして使われる。
- AFP-L3
- AFPの糖鎖異形体。肝癌診断の補助に用いられることがある。
- DCP(PIVKA-II)
- DCPとしても知られるPIVKA-II。肝癌の腫瘍マーカーの一つ。
- 超音波検査
- 肝臓を音波で画像化する非侵襲的検査。腫瘍の大きさや位置を把握するのに有用。
- CT
- Computed Tomography の略。断層画像で腫瘍と血管の関係を評価する画像検査。
- MRI
- Magnetic Resonance Imaging の略。高精度で肝腫瘍の性質を詳しく評価できる画像検査。
- 肝生検
- 腫瘍の組織を少量採取し病理診断を行う検査。確定診断に役立つ。
- RFA
- ラジオ波焼灼療法。腫瘍を熱で壊す局所治療。小さな肝腫瘍に適用。
- PEI
- 経皮的エタノール注入療法。腫瘍にアルコールを注入して壊す治療。
- TACE
- 経動脈化学塞栓療法。肝動脈へ薬剤を投与し血流を遮断して腫瘍を縮小させる療法。
- TARE
- 経動脈放射線療法。肝動脈へ放射性物質を投与して腫瘍を局所治療する方法。
- 放射線治療
- がんに対して放射線を照射する治療。肝癌にも適用されることがある。
- 肝切除
- 腫瘍を含む肝臓の一部を外科的に切除する治療。適応は腫瘍の数・位置と肝機能で判断。
- 肝移植
- 病変が広範囲の場合や肝機能が極端に低い場合に肝臓を移植する治療。
- ソラフェニブ
- 分子標的治療薬の一つ。肝細胞癌の第一選択薬として使われることが多い。
- レンバチニブ
- 分子標的治療薬。病期に応じてソラフェニブの代替として用いられることがある。
- カボザンチニブ
- 分子標的治療薬。進行肝癌の治療選択肢の一つ。
- レゴラフェニブ
- 再発・難治肝癌に使われる分子標的薬。
- 免疫チェックポイント阻害薬
- 免疫系の働きを高めてがんを攻撃する薬。肝癌にも適用が広がっている。
- ニボルマブ
- 免疫チェックポイント阻害薬。肝癌治療にも使用されることがある。
- ペムブロリズマブ
- 免疫チェックポイント阻害薬。肝癌治療の選択肢の一つ。
- アテゾリズマブ+ベバシズマブ
- 免疫療法の組み合わせ。肝細胞癌の治療選択肢として注目されている。
- BCLC分類
- 肝細胞癌の病期分類の一つ。治療方針を決定する際に用いられる。
- TNM分類
- 腫瘍の大きさ・転移・リンパ節の状態で病期を表す分類。治療計画に役立つ。
- 5年生存率
- 治療開始後5年間生存している人の割合。予後の目安を示す指標。
- 腹水
- 腹腔に液体が貯まる状態。肝硬変や進行肝癌の合併症として現れる。
- 黄疸
- 皮膚や白目が黄色くなる症状。胆道系の障害や腫瘍のサインとなることがある。
- 肝性脳症
- 肝機能障害により脳機能が低下する重篤な合併症。治療と管理が必要。
- リスク要因
- 肝癌発生に影響する要因。肝硬変・肝炎・肥満・糖尿病・過度のアルコール摂取など。
- 検診・早期発見
- 高リスク群に対して定期的な画像検査と血液検査を行い早期に発見する取り組み。



















